日本女性语的变迁.docx
《日本女性语的变迁.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《日本女性语的变迁.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
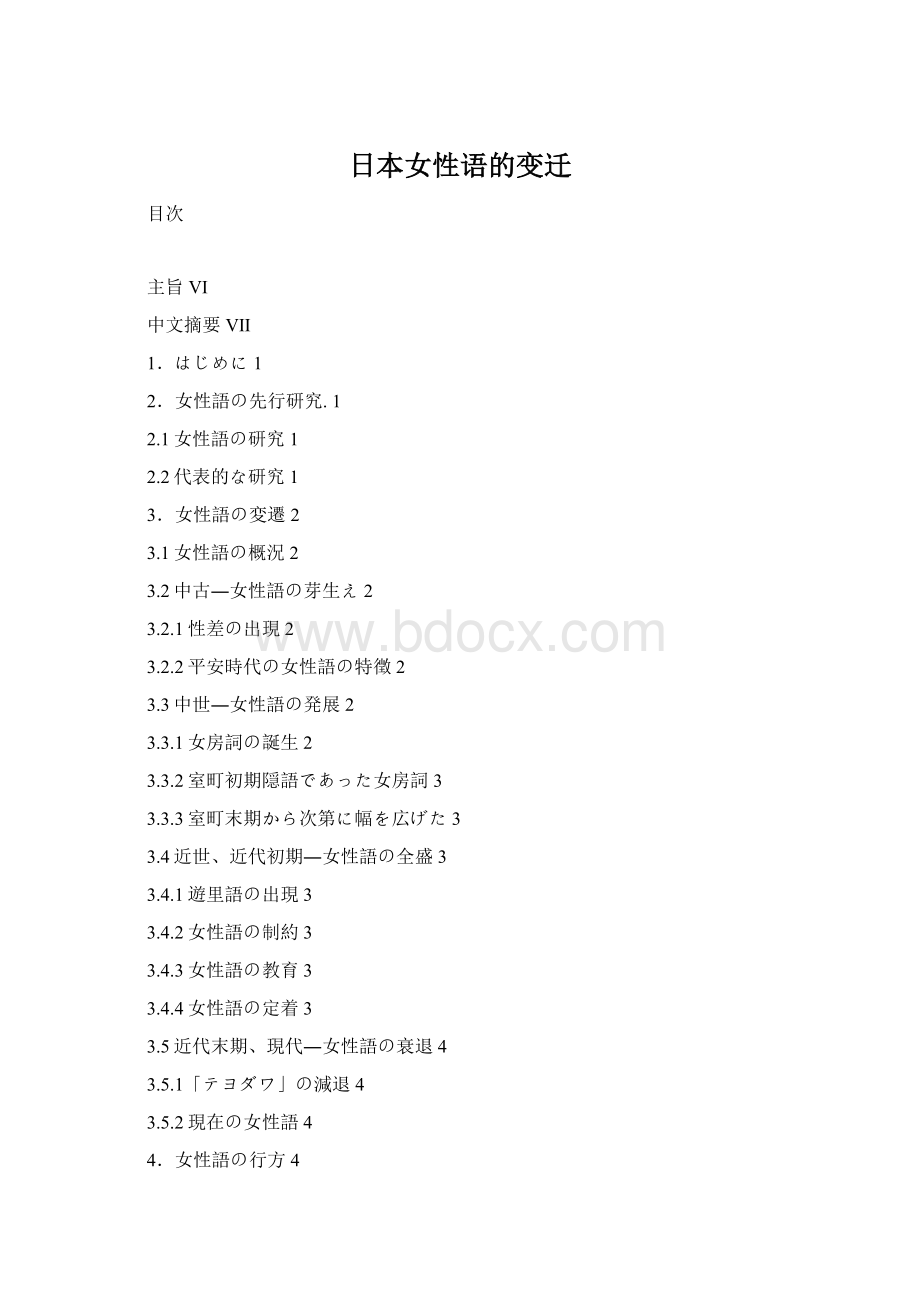
日本女性语的变迁
目次
主旨Ⅵ
中文摘要Ⅶ
1.はじめに1
2.女性語の先行研究.1
2.1女性語の研究1
2.2代表的な研究1
3.女性語の変遷2
3.1女性語の概況2
3.2中古―女性語の芽生え2
3.2.1性差の出現2
3.2.2平安時代の女性語の特徴2
3.3中世―女性語の発展2
3.3.1女房詞の誕生2
3.3.2室町初期隠語であった女房詞3
3.3.3室町末期から次第に幅を広げた3
3.4近世、近代初期―女性語の全盛3
3.4.1遊里語の出現3
3.4.2女性語の制約3
3.4.3女性語の教育3
3.4.4女性語の定着3
3.5近代末期、現代―女性語の衰退4
3.5.1「テヨダワ」の減退4
3.5.2現在の女性語4
4.女性語の行方4
4.1研究者の見方4
4.2筆者の見方4
5.終りに5
参考文献6
謝辞7
主旨
日本語の「女性語」が特殊な言葉行為として存在している。
その言葉現象は深刻な歴史と文化背景を含む。
女性用語の言葉と表現形式は男性用語と違う一般用語である。
優雅、親密、礼儀、体面など特徴がある。
「女性語」をめぐって分析すれば、規範的な日本語の勉強を助けることができる。
この論文が各時代における女性語の変遷を中心となり、また、女性語形成変遷の社会的背景を分析して、女性語と日本語を一層認識できるようになる。
キーワード:
女性語、変遷、女房詞、遊里語、伝統文化、集団意識
中文摘要
在日语中存在着“女性语”这一特殊的语言行为。
这种语言现象有着深刻的历史与文化背景。
女性用语是语言和表现形式有别于男性用语的一般用语。
其特点是优雅、亲密、有礼、体面。
分析研究女性语现象,有助于学习规范的日语。
本论文以各时代女性语的变迁为中心,同时通过分析女性语形成变迁的社会背景,对女性语和日语能有更进一步的认识与了解。
关键词:
女性语;变迁;女房词;游里语;传统文化;集团意识
1.はじめに
現代日本語において衰退しつつあるようにもみえるが、いまだに整った女性語の体系が存在している。
特に日本語の文法として定着した敬語表現等は、短い期間に消えることなく、これからも長く生き続けるのであろう。
だから、「女性語」については、まだまだ研究する余地と価値が大いにあると思われる。
日本における女性語研究の歴史は、女房詞や遊里語などに関する伝統的な女性語研究に始まり、徐々に女性語の研究が盛んになった。
ただし、女性語形成変遷の社会的背景等についてはほとんど言及していない。
また、多くの研究者は自分の研究領域に縛られ、単一的視点から女性語を考察する傾向にある。
日本語の女性語は長い歴史を持った言語現象で、女性語の変遷とその社会の背景を結んで検討するが必要である。
本論文は女性語形成変遷の社会的背景等体系的に研究する一つの試みである。
女性語の変遷を概観すると、日本語の性差は古代にはなく、平安時代から徐々に性差の兆しが見え始め、室町時代に女房詞が成立し、それを手本に江戸時代の公家、武家、富裕町人の娘の女性語が出来上がった。
明治時代は国家の教育の中で女性のことばの枠をはめ、性差が確立した。
それがまた、1945年の敗戦と女性解放をきっかけに、ことばの制約が取り除かれてきた。
そして現代において女性語は男性化、中性化の傾向が見られる。
2.女性語の先行研究
日本語における女性語研究がどのように進められてきたか、先行研究を踏まえ、振り返ってみよう。
2.1女性語の研究
日本における女性語研究の歴史は、1970年代以前、女房詞や遊里語などに関する伝統的な女性語研究に始まり、1970年代以後、欧米からフェミニズムの視点が導入されてからは、特に、1980年代以降、女性の社会進出とともに女性語の研究が盛んになった。
それに対して、今中国国内では日本語の研究が盛んになりつつある一方、女性語に関する学術論文が少なく、女性語を日本語の独特な言語現象の一つとして取り扱い、概略的な紹介が多いことである。
2.2代表的な研究
(1)明治以後集団語として女房詞を取り上げたのは、管見によると、安藤正次「異名隠語の研究を述べて特に斎宮忌詞を論ず」(1913)が初めてだと思われる。
(2)また、菊澤季生も女性語というものに早く注目していた。
菊澤は「婦人の言葉の特徴に就いて」(1929)で女性語に関する論文を発表し、この論文で菊澤は「婦人語」を主題にし、女房詞を性別に基づく集団語と見なした。
(3)真下の『婦人語の研究』(1948)は女性語に関して書かれた初めてのまとまった文献として研究史上重要な意味を持つ。
(4)寿岳は「現代国語の位相~男性語と女性語」(1963)、「女性語と敬語」(1966)、「女らしいことば」(1966)等を相次いで執筆し、研究の発展に大きく貢献した。
(5)井出は「女の文章と女らしさ―木村治美の文章のケーススタディ」(1981)、「待遇表現と男女差の比較」(1982)、「女らしさの言語学―なぜ女は女性語を使うのか」(1983)、『女性の敬語の言語形式と機能』(1985)、「言語行動のとらえ方~男女差研究の理論モデル」(1986)など多くの論文を発表し、社会言語学的な観点7から女性語に取り組んだ。
(6)1990年代に入っても、遠藤の研究は絶えることなく、次々と研究成果を発表した。
『女のことばの文化史』が発表した。
翌年、また『気になります、この「ことば」』(1998)を著した。
3.女性語の変遷
3.1女性語の概況
日本語の「女性語」は日本女性の中でいつも使う言葉と相応な言葉表現形式である。
古代から、日本語が女性だけ使う言葉が存在した。
女性用語は男性用語と比べて、濃い感情色彩、高い敬語程度、優しい、婉曲的な特徴がある。
同じ内容だが、表現形式が違う。
日本語では、敬語表現、感嘆詞、終助詞、名詞及び接辞などの様々な面において、女性は男性と違う表現を用いる。
どの国の言語にも性別による言葉の違いが多少あるが、日本語ほど男性語と女性語を細かく分ける言語はないと言ってよい。
3.2中古―女性語の芽生え
3.2.1性差の出現
男女のことばの相違が見え始めたのは平安時代であるとか、女性語が平安時代から盛んになり出したとかという考え方が、一般的に認められている。
奈良時代において、「君」は尊敬の呼び方である。
女性が男性を尊敬して「君」と呼んだのは、女性語の先駆的現象だと見るべきものである。
平安時代の女性は対等以下を呼ぶ時、柔らかい感じがする対称の人称代名詞の「そこ」を最も好んで使ったとされる。
3.2.2平安時代の女性語の特徴
平安時代の女性語の特徴として挙げられるものは、一つは女性は漢語の使用を控えること、もう一つは、平安時代の男性専用の自称代名詞「なにがし」に対し、女性は対等以下を呼ぶのに、主に柔らかい感じの「そこ」を使っていたと述べている。
その他、語彙や文法面からみたことばの性差は見られなかった。
要するに、平安時代においては女性語はまだそれほど顕著なものではなかった。
3.3中世―女性語の発展
3.3.1女房詞の誕生
室町時代に、女性語史上最も注目すべき「女房詞」が現れた。
女房詞とは、もと宮中や院の御所に仕える女房たちの間に行われた特殊な言葉だった。
それは女房たちの仲間うちの言葉であり、隠語的なものとも言えるものだった。
3.3.2室町初期隠語であった女房詞
室町時代の初期から宮中の女官たちの間で用いられていた「女房詞」は特殊な言葉、彼女たちの仲間うちの言葉で、隠語的なものと言えるものだった。
女房詞を使うことでグループ内の関係はより緊密になり、一体感がもてるようになるが、外部に対してはより希薄な関係になり、排他的になる作用を果たす。
3.3.3室町末期から幅を広げた
室町末期から、女房詞が一般下層へと次第に幅を広げたのである。
隠語としての性格は薄れ、上品なことばのサンプルとして迎えられるようになった。
時代がくだるにつれて、そういう御所ことばは次第に使われなくなるが、そのうち現代一般女性の言葉として今現在まだ用いられているものもある。
「おしろい、おなか、おひや」等がそれである。
要するに、女房ことばが語彙の面で後の女性語に大きな影響を及ぼしたことはいうまでもない。
3.4近世、近代初期―女性語の全盛
3.4.1遊里語の出現
江戸幕府は、江戸の吉原、京都の島原、大阪の新町に公認の遊里を開かせた。
18世紀末には6000人に及ぶ遊女がこれらの廓で働いていた。
その遊女たちによって創造された「遊里語」も敬語の面で後の日本語に影響を与えたのである。
彼女たちの作った遊里語の主なものは敬語で、それは遊女が客に対する待遇表現として不可欠のものであった。
3.4.2女性語の制約
江戸時代には、幕府の政策、男尊女卑という儒教の指導理念のもとで、女性の言葉がコントロールされるようになった。
女の生き方、考え方を細かく規定した女訓書が幾種も出され、弱き性、劣る性とされた女性は、女房詞を手本とした「女らしい」美しい、上品なことばを強制されていく。
女性の漢語、漢字の使用に対しては、江戸時代までは始終批判的な態度を取っていた。
3.4.3女性語の教育
明治時代は国家的教育の中で女性のことばの枠をはめ、性差が確立した時代である。
明治時代は文明開化とともに導入された人権思想も男女平等観も、富国強兵と軍国主義に対抗できない時代で、女と男は教育もことばも区別された。
この時期に、漢字や漢語が女性に解放されたという日本語の歴史においても画期的なことが起った。
3.4.4女性語の定着
「男女に別あり」という背景には、性別を強調する日本社会は女性語が定着した。
「男女に別あり」というのは、もともと儒教的な考え方である。
江戸時代に武士階級から庶民にまで広がって、明治時代には民法によって国民文化として制度化され、日本人全体が規制されることになった。
言葉やしぐさにまで、性別による差が作られ、男らしさ、女らしさの違いが強調されてきた。
3.5近代末期、現代―女性語の衰退
3.5.1「テヨダワ」の減退
近代末期から現在まで女性のことばの変遷の大きな流れは、「テヨダワ」の減退に代表されるように、女性専用とされる語の使用の減少の流れでもあった。
特に、女性専用形式は、すでに衰退したり、あるいは現在急速に衰退に向かっているものが多いということが分かった。
3.5.2現在の女性語
現在では、年齢と職業などにより、日本人女性の言葉使いが多様化している。
またもう一つは、同一人物でも、時や場所や場合によって、時には意図的に男性的表現を使用することがあるし、また時には女性的表現を使用することもある。
女性は自分の女らしさを強調したければ女性語を使い、あえて強調したくなければ女性語を使わず、より中性的なものを使えばよい、といった性質のものであろう。
4.女性語の行方
4.1研究者の見方
「女性語」の今後の展開に関しては、研究者や文学者によって様々な見方があるようである。
一つは、「女ことばは日本語の特徴であり、味わいの一つであって、この先も無くならないであろう、または無くしてはいけない」という見解である。
もう一つは、「女ことばとは差別の象徴であり、“女らしさ”や“日本女性のすばらしさ”という枠に女性を縛り付けておくためのもの」というような見方である。
さらには、古代の日本語に性差がなかったころへ戻ろうとしている、と見る人もいるようである。
4.2筆者の見方
確かに、戦後の女性語の変遷を見ると、若い女性の間では従来の女性特有の文末詞の多くが用いられなくなった。
女性語は徐々に男性化、中性化する傾向が見られる。
一方、年配の女性の間では依然として使い続けている。
また、女性語の枠をもう少し広めて考えるなら、終助詞だけでなく、敬語表現