日汉互译1Word格式.docx
《日汉互译1Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《日汉互译1Word格式.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
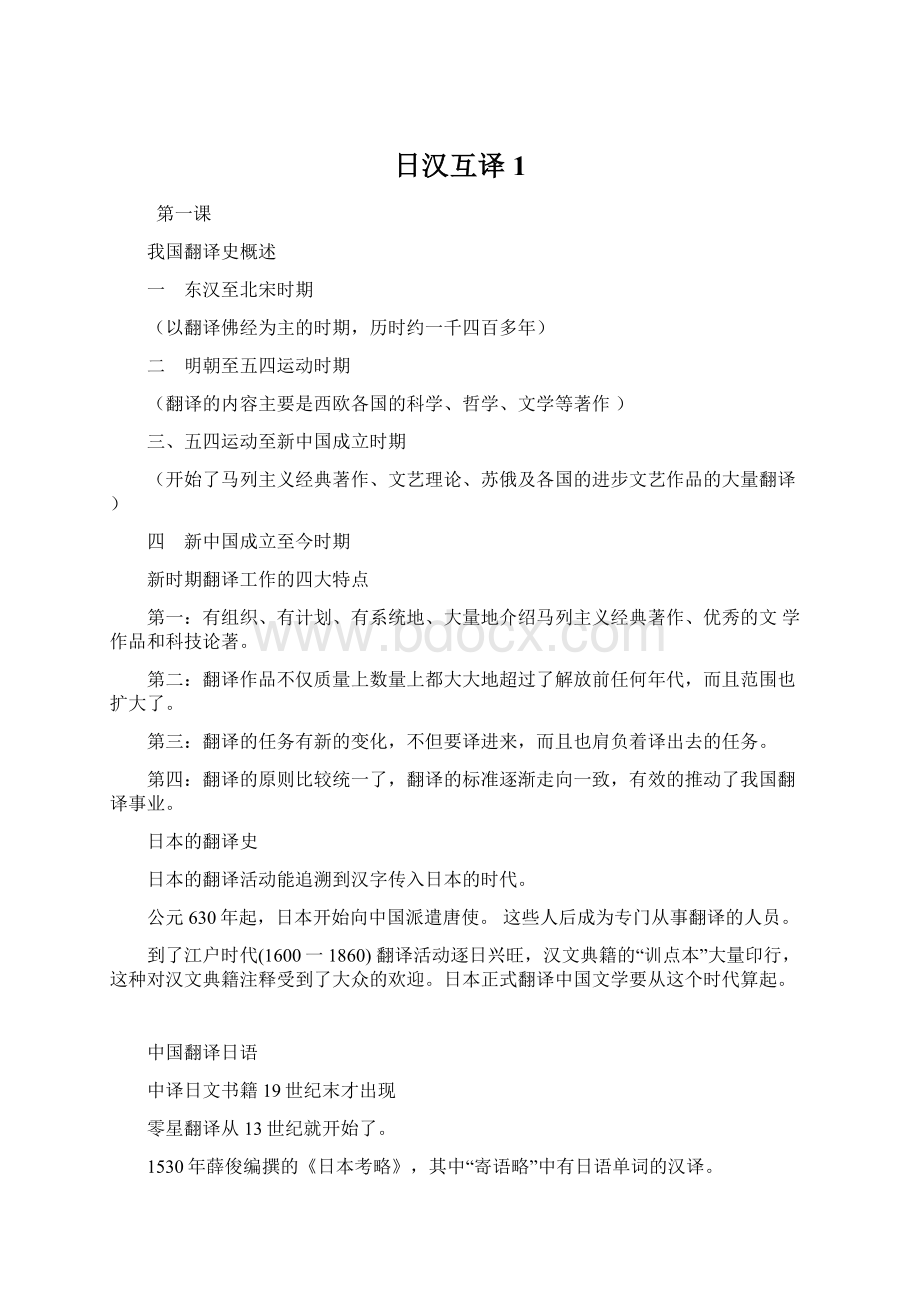
3)形式恰当,吸引读者
翻译的标准————信、达、雅
为什么严复所提出的“信、达、雅”可以作为翻译的标准?
原因如下:
①这个标准只用了三个字来概括,简明扼要,不空洞,不重叠,比较容易为人接受。
②许多学者先后提出的各种不同的标准,都没有超出“信、达、雅”的范畴,理论上的深度不够,没有哪一种能取代它。
③“信、达、雅”理论近百年来一直在我国的翻译工作中起着指导作用,现在还有强大的生命力。
“信”指的是忠实于原作的内容,把原作的内容全部地确切地表达出来,没有改变和歪曲的现象,没有增添和删节的现象,没有遗漏和阉割的现象。
“达”指的是用符合全民规范的译文语言来表达。
要做到“达”,译文必须是坦白流畅的现代语言,没有逐词死译、生搬硬套的现象,没有滥用陈腔滥调的现象,没有文理不通的现象。
“雅”是指风格。
要做到雅,译者不能对原作风格有任何的破坏和改变,不能以译者的风格代替原作的风格。
原作是朴素的,不能译成华丽的,原作是疏放的,不能译成严谨的。
原作的民族色彩、时代色彩、语体色彩、个人的艺术特点也应尽可能地保持下来。
文章三要素
第一是内容,内容指的是作品中所叙述的事实、说明的事理,描写的景物以及在叙述、说明和描写之中所反映的作者的思想、观点、立场和所流露的感情;
第二是形式,形式指的是语言形式,即作者所使用的词汇、语法、修辞手段的总和;
第三是风格,风格指的是民族风格、时代风格、流派风格、语体风格和作者个人的语言风格等等。
翻译的基本过程
概括起来大体可以分为:
(1)理解阶段
(2)表达阶段(3)校对阶段
理解阶段:
理解是译者利用原文语言的词汇、语法、修辞等知识,理解原文的内容和风格的过程,正确地理解原文是翻译的基础和前提。
忽略对原文的理解过程,往往导致:
(1)词义的误译(一词多义)
(2)逻辑关系的误译
(3)原文风格的误译
词义的误译:
eg:
雪子さん、もうお食事やお洗濯は止しにしてちょうだいね。
お式の日に手が汚いとみっともないってよく雑誌なんかにも書いてあるから。
误译:
雪子,你不要再做饭洗衣了。
杂志上都说了,在举行婚礼的大喜日子里,把手弄脏了多不像样子呀。
正译:
杂志上都说了,在举行婚礼的大喜日子里,把手弄粗糙了多不像样子呀。
逻辑关系的误译:
Eg:
肝臓には、オルニシンという物質が含まれている。
アンモニアと呼吸の結果生じた二酸化炭素とは、オルニシンと結合してシトルリンを生ずる。
译文一:
肝脏中含有乌胺酸。
呼吸时遇氨产生的二氧化碳,与乌胺酸结合生成瓜氨酸。
译文二:
氨以及呼吸时产生的二氧化碳,与乌胺酸结合生成瓜氨酸。
原文风格的误译:
我们从中午一直哭到黄昏。
老婆子们让我们去喝粥,我们还在哭。
老婆子们生气地说:
“哭什么?
再哭送你们去万人坑”
ぼくらは正午から夕方まで泣き続けた。
おばあさんたちにお粥を飲めと言われても、ぼくらはまだ泣いていた。
おばあさんたちは怒ってしまった。
「なに泣いてんの。
泣き止まなきゃ万人坑にほうり込むよ。
」
表达阶段:
表达即译者将自己所理解的原文内容用译文语言再现出来。
可以说理解是表达的基础,而表达的好坏又取决于理解得是否透彻。
如果说理解是翻译的基础和前提的话,表达则是翻译的结果。
校对阶段:
校对是指对译文的修改、推敲和润色。
具体步骤如下:
(1)对照原文逐字逐句的修改
(2)脱离原文,反复阅读和修改
(3)请专业人员帮忙阅读修改
(4)整体检查、修改
翻译工作者的基本条件
1)良好的外语基础是做好翻译工作的先决条件。
2)较高的母语水平是做好翻译工作的根本条件。
3)广博的知识积累是做好翻译工作的重要条件。
4)翻译的理论和技巧是做好翻译工作的必要条件。
第二课
第一节词语的翻译
一、多义词的翻译
不论是日语还是汉语,一词多义、一词多用、习惯用法等情况都是很普遍的。
因此,在翻译时应根据上下文逻辑、所译语言词汇搭配习惯来选择词义。
如:
●体が弱い●力が弱い●気が弱い
体弱力气小懦弱
●英語に弱い●機械に弱い●甘いものに弱い
英语不好。
不擅长(操纵)机器。
不能吃甜食。
●この地方の建物は地震に弱い这个地区的建筑物经不起地震。
筆をとる/席をとる/後をとる/
执笔 占座接班
金をとる/陣をとる/床をとる/
收费布阵铺床
鳥をとる/血をとる/写真をとる/
捉鸟抽血照相
休暇をとる/食事をとる/婿をとる/
请假用餐聘女婿
汚れをとる/ 帽子をとる/
去污 脱帽
事務をとる/ メモをとる/手間をとる/
办事 记录费工夫
舟の舵をとる/雑誌をとる/満点をとる/
掌舵订杂志得满分
寸法をとる/機嫌をとる/
量尺寸讨人喜欢
彼の説をとる/手をとって教える/
采取他的说法手把手教
二、同形词的翻译
日语中的很多汉语词汇,与中文的词汇同形、同义,这为我们从事日语翻译带来了很大的方便。
但是,要注意的是日语中还有很多汉语词汇,虽与中文的汉语词汇同形,但却不同义。
翻译过程中除了要求我们有过硬的日语水平,还要注意切忌望文生义。
不是很有把握的词一定要查阅辞典,并根据语境来选择适当的词义。
中日汉字比较:
1、形义相同:
科学 技術 世界 文化
2、形同义异:
①意义完全不同:
野菜 薬缶 検討 骨折
②意义部分不同:
愛人 助手
3、形异义同:
農繁期 人工衛星 赤外線 売買
4、日语特有汉字:
①用汉字自造:
返事 手当 見本 丹念
②自造汉字:
峠 辻 笹 込 栃 畠
○仕事がどんなに苦しくても、やっていく覚悟がありますか/
你们有没有不论工作如何艰难都坚持下去的觉悟吗?
(思想准备)
○
事情があって二人は別れることになった/因为有事情,两人分手了(某种原因)
○彼は一人の収入で妻子を養う/他靠一个人的收入养活妻子。
(妻子和儿女)
○彼は自分の行為に無関心です。
/他们对自己的行为不感兴趣。
(丝毫不在意)
○知り合いになってから一年ほど経て、神坂がある日僕のうちを訪ねてきまして、日本文化の社長がわからず屋でけちで、仕事が面白くない、腕を振る余地がなくて退屈だから、やめてどこかへ変わりたいという相談を持ちかけてきました。
译文:
我同神坂认识大约一年以后,有一天他到我家来,同我商量,说日本文化社的社长不近情理,又十分吝啬,他感到工作无趣,没有施展才能的余地,很是厌倦,所以想辞职,换个地方。
○「おまえは実にけちなやつだ。
けちな奴だということが俺にもだんだんわかってきた。
お前は強そうな人間の前へ出たら散々ぺこぺこして、弱いやつの前では威張り散らすようなやつだ。
……」
译文:
“其实,你是个卑鄙的家伙,这一点我是慢慢明白。
你对强者阿谀奉承,可对弱者却耀武扬威。
……”
○そのことがあってからのち、神坂さんは私に対して、とても邪慳になりました。
私のすることを一一けちをつけて、私がいない時には大森さんに向かって私の悪口を言って、二人を遠ざけようとなさるんです。
自那以后,神坂待我非常刻薄,对我做的每件事都要吹毛求疵,趁我不在就在大森面前说我的坏话,企图离间我们。
○「え?
どういう事なんだ。
あんたはもう絶望したなんていっていられる年頃でもないじゃないか。
けちな女学生みたいな事いうなよ。
“哎,怎么回事?
你已经过了说“已经绝望了”这种话的年龄了吧。
不要说那种像个幼稚的女学生似的话。
”
○九段坂の最寄にけちなめし屋がある。
春の末の夕暮れに一人の男が大儀そうに敷居にまたげた。
すでに三人のお客がある。
またランプをつけないので、薄暗い土間に居並ぶ人影もおぼろである。
九段坂附近有一家简陋的小饭馆。
春末的一个傍晚,有一个男人拖着疲惫的步子跨进这家饭馆的门槛。
里面已经有3个顾客了,油灯还没有点上,暗淡的殿堂里,人影朦胧。
○そのうちに一人来る、二人来る、だんだん二階から宿直部屋へ集まってくる。
見るとみんな眠そうに瞼をはらしている。
けちな奴等だ。
一晩位ねないで、そんな面をして男と云われるか。
一会儿,学生们零零星星地从2楼下来,到值班室集中。
看上去个个都眼泡红肿,一副没有睡醒的样子。
真是些不中用的家伙。
一个晚上不睡觉就这副熊样,还算是男子汉吗?
三、拟声拟态词的翻译
日语中的拟声拟态词很多,而中文中的象声词也不少。
但是,毕竟是两种不同的语言,在表达上存在着很多差异。
例如:
日语的拟声拟态词比汉语的象声词丰富,而且包罗万象,因此在互译时往往找不到很恰当的词与之对应。
①
尽量找相对应的拟声拟态词(象声词)
○空が暗くなり、雷がごろごろと遠くで鳴り始めた。
/天空暗了下来,远处响起了隆隆的雷声。
○たくあんをこりこり噛む。
/咯吱咯吱地嚼着淹萝卜。
○屋里静悄悄的,没有一个人。
/部屋の中はシーンと静まり返っていて、だれもいなかった。
○他美美地吧嗒吧嗒地吸着烟。
/彼はうまそうにタバコをすぱすぱ吸った。
②遇到没有对应的词汇时,可按照译文语言习惯,尽量把原文逼真、形象地表达出来。
○電灯がぱっとつきました。
灯一下子亮了起来。
○のろのろしていないで早くしなさい。
/别磨磨蹭蹭的,快点!
○
一日中歩いて、へとへとだ。
/走了一整天,累得精疲力尽的。
○顔をぐしょぐしょにして、泣いている/哭得满脸泪水。
注意:
译词要符合汉语表达习惯
(1)不能生造汉语拟声拟态词
●ぼわわあ、ぼわわあ、力のない汽笛が沖から響いてきた/
噗……啪啪,噗……啪啪,软弱的汽笛声从海里响起。
汉语的汽笛声一般说“呜呜”“嘟嘟”等,为迁就“ぼわわあ”而造出“噗……啪啪”是不妥的。
.
(2)译词要符合汉语习惯用法
●馬が「ひーん」とさお立ちになろうとするのを、そばからやっと押さえている。
那匹马“吁—吁—”地嘶叫着,正想前腿腾空直立起来时,幸好被旁边的人把它拖住。
汉语习惯称马叫为“咴儿咴儿”
●くりくりした男の子、背の高い女の子/园墩墩的男孩子,高身量的女孩子。
汉语习惯称“园墩墩”为“胖墩墩”
(3)符号(文字)应尽量用一般习惯使用的。
尽管汉语拟声拟态词的符号(文字)不统一,但总有使用频率高低之分,应尽量使用频率高的。
如“格登”和“戈登”,应使用“格登”;
“咯咯”和“格格”应使用“咯咯”;
“呵呵”和“嗬嗬”,应使用“呵呵”,“叽叽喳喳”和“唧唧喳喳”,应使用“叽叽喳喳”,“啰啰嗦嗦”和“噜噜苏苏”,应使用“啰啰嗦嗦”
四、成语、谚语、惯用语的翻译
关于成语、谚语、惯用语的翻译,首先要尽量寻找相对应的固定表达方式。
由于成语、谚语、惯用语多出自生活体验,若是从中国传到日本的典故,对于中国译者来说比较好理解、容易掌握,这种情况几乎都有对应的表现。
但是若出自日本,由于两国文化的不同,表达差异的存在,遇到这种情况只有根据内容,直白地把原文解释过去了。
○猫に小判/○二階から目薬/
对牛弹琴远水不解近渴
○鬼に金棒/○屋烏の愛
如虎添翼爱屋及乌
○瑞雪兆丰年/○卧薪尝胆/
大雪は豊作の兆し臥薪嘗胆
○饮水思源/水を飲むときにはその水の因ってくる源に思いをいたしなさい
○酒逢知己千杯少お酒は仲のよい友達に逢えば千杯も少ない
成语、谚语例
五里霧中 四面楚歌 大器晩成(字义皆同)
竜頭蛇尾 塞翁が馬 危機一髪(字异义同)
成竹 杞憂 蛇足(简化)
我田引水 和洋折衷 亭主関白(日本自造)
一か八か 住めば都 言わぬが花(日本固有)
百聞は一見にしかず 良薬は口に苦し (来自中国的谚语)
猿も木から落ちる 三人寄れば文殊の知恵(日本固有的谚语)
惯用语和成语、谚语的区别
1、惯用语:
①构成形式整齐②有完整的词尾变化。
③都是地道的日语。
2、谚语:
①有深刻的寓意。
②有出典。
3、成语:
①结构形式固定。
有特定概念。
②没有整齐的动宾结构。
③没有词尾变化。
④有典为据,多来自汉语。
青は藍より出でて藍より青し(谚语)
昨日は昨日、今日は今日(谚语)
三日坊主(成语)八方美人(成语)
首を長くする 足が棒になる
口が重い 痒いところに手が届く
油を売る 首を切る
手も足も出ない 根も葉もない
慣用句的翻译:
根据语境选择合适词语。
○世間は彼を天才だと思っていたらしい、矢田部郁子もその一人だ。
しかし私は彼を恥知らずだと思っていた。
どこかにうそがありごまかしがある。
彼のやっていることはその場限りのでたらめで、根も葉もないのだという気がしていた。
译文:
社会上的人们似乎把它当作天才。
矢田部郁子也是其中之一。
但是我却一直认为它是一个恬不知耻的家伙。
我总觉得他在某些地方说谎、骗人,他所作的事情都是些应付场面的胡闹,很不实在。
○「私は流行というものが大嫌いになりました」と郁子は言った。
「横田は流行をつくる人です。
しかしもともと流行などというものは、根も葉もないことです。
あなたはずっと前から、横田を嫌っておいででした。
あの人の仕事はその場限りのでたらめだって、ね、今は私もそう思います。
でもそのでたらめが、ちゃんと世間に通用して、彼の職業になっているんです。
“我对于时髦这东西变得非常讨厌了。
”郁子说,“横田是创造时髦的人。
但是时髦这东西本来就是无中生有的,您从很早以前就讨厌横田,您说他的工作都是应付场面的胡闹,是吧?
现在我也这样认为。
可是那种胡闹在社会上完全吃得开,已经成了他的职业了。
○ようやく眼がさめたな。
あの男の嘘にやっと気がついたという訳だ。
結婚する前に気がつけば、余計な回り道をしなくてもよかったんだ。
你总算醒悟了。
也就是说,你对他的谎言好不容易才识破了。
如果在结婚以前就
发觉的话,就可以不走这么些多余的弯路了。
○それまでだって、何だか変な気持ちでしたけど、そのとき本当に気がついたんです。
私が愛されているというのは嘘で、利用されているだけではなかったかしら……
我在以前虽然也有些奇怪的感觉,但是到这时才真正地感觉到了:
所谓爱我只是谎言,是不是只是在利用我?
○大丈夫だ。
何もない。
やはり君には気づかなかったのだろう。
安心したまえ。
“不要紧,没什么事。
大概他还是没有注意到你,放心吧!
第三课
第二节句子翻译(顺译)
所谓顺译,就是在原文词义、语序和思路的引导下,借水行舟进行翻译。
它的特点为:
原文与译语之间在词义、句子结构和思维方式上有很多相同、相近或相通之处,不需要作大的调整就能够顺流而下进行双语同步的语际转换,而译文本身亦符合译语的语法规则和习惯,通畅明了。
例1彼は妻をもらうまでの四五年に渡る争闘を考えた。
それから妻と結婚してから、母と妻との間に挟まれた二年間の苦痛な時間を考えた。
彼は母が死に、妻と二人になると、急に妻が胸の病気で寝てしまったこの一年間の艱難を思い出した。
他想到娶妻子之前曾与她的家庭进行了长达四、五年的斗争。
又想到与妻子结婚之后夹在母亲和妻子之间的痛苦难熬的两年工夫。
还想起母亲去世后总算与妻子两个人过日子了,妻子却突然患肺病卧床不起的这一年来的艰难时光。
例2対岸はまだ眠っているが、こちらの村はもう覚めた。
うしろの舎から煙が立ち上る。
今柵を出た家鴨は足跡を霜に印けて、くわっくわっ呼びながら、朝日を砕いて水に飛び込む。
对岸尚在沉睡,而这边的村庄已经醒来。
身后的茅舍炊烟升起。
家鸭出栏,足迹印在霜地上,呷呷鸣叫着,踏碎朝阳,扑进水里。
例3 私が皆さんに写真屋を紹介しようとするときに、この写真屋なら、皆さんに紹介しても悪くないだろうと考える。
こうした場合「この写真屋がうまいですが、一度かれの所へ行って、写真を撮ってもらってやってくださいませんか。
」こう言います。
「とってもらって」というと、皆さんがこの写真屋から恩を受けること、「やって」というと、写真屋へ恩を施すこと、「くださいませんか」というと、私が皆さんから恩を受けることを表すわけでありまして、恩の関係はこのように移動するのであります。
我打算给大家介绍一家照相馆,心想把这家介绍给大家准没错。
于是就会说:
“这家照相馆不错,请到他那儿让他替你们拍张照。
”这里的“替”,意为照相馆有恩于大家;
“让”则表明大家施恩于照相馆;
而“请”却表示我领大家的情。
人情关系就是如此变化。
例4 平底および三角フラスコは加熱、圧力に弱いから、加熱用には使用してはならない。
平底及三角烧瓶不耐加热、重压,因此,不可用于加热。
平底烧瓶和三角烧瓶不耐加热、加压,因此,不可用于加热。
例5 わたしの父は大酒家の部類だったと思うのだが、酒の上のことだから勘弁しろ、ということを許さなかった。
酒のうえのことだから勘弁しない。
酒中の失策を酒におしつけては、第一、酒が可哀相だという理屈であった。
我想我父亲是酒鬼的一种,但是因为是酒上的事,请原谅的事又不允许。
因为是酒上的事,不原谅。
如果把酒中的失策强加给酒,第一,酒太可怜了。
就是这么一个理由。
我父亲算得上海量,不过,他并不同意“酒后生事,情有可原”的说法。
正因为酒后生事,才不能原凉。
他认为把酒后的失着归罪于酒,别的不说,酒真是太倒霉了。
例8 こういう無味乾燥な学者などという者は、たいていが偏屈者であって、且つ皮肉屋である。
愛情に騙されることを怖がれ、愛情の傍にある陥穴について、いつも用心ぽくならざるを得ないのが普通である。
大凡那些从事枯燥无味工作的学者,多半是些古怪而又尖酸的人。
通常,他们莫不生怕上了爱情的钩,因而对于爱情布下的罗网总是要小心地提防。
大凡枯燥无味的学者,多半是古怪而又尖酸的人。
他们害怕因爱情上当受偏,所以通常不得不小心提防着与爱情一步之遥的陷阱。
例9 彼は、この自然と対照させて、今さらのように世間の下等さを思い出した。
下等な世間に住む人間の不幸は、その下等さに煩わされて、自分も下等な言動を余儀なくさせられるところにある。
与自然风光相对照,他又一次想到人世间竟有多么下等。
生活在下等的人世间的人们的不幸在于,在这种下等的影响下,自己的言行也不得不变得下等了。
对照自然的景色,他更感到世间的卑俗,和生活于这俗世的人们的不幸——一天到晚被包围在卑俗的气氛中,连自己也不能不做出许多卑俗的行径。
例10「あのね、お祖父様にね。
」栗梅の小さな紋附を着た太郎は、突然こう言い出した。
考えようとする努力と、笑いたいのをこらえようとする努力で、えくぼが何度も消えたり出来たりする。
--それが馬琴には、おのずから微笑を誘うような気がした。
穿着土红色小礼袍的太郎突然说道:
“我说呀,爷爷。
”他在一个劲儿想事情,同时又竭力憋着笑,所以脸上的酒窝一会儿露出来,一会儿又消失了——马琴看到他这副样子,不由得引起微笑。
“喂,爷爷!
”穿着紫褐色礼袍的太郎,突然叫了一声爷爷。
小脑袋好象在想什么,竭力忍住了笑,睑上小酒窝忽隐忽现,快把马琴逗乐了。
例:
それまでは個人として何かを言われればよかったものが、主婦になれば、○○さんの奥さんは、という言われ方に変わる。
確かに大変なことである、と同時に、素敵なことなのではないだろうか。
家庭を守るということが、変化のないつまらないものだという考え方は、私にはない。
私は三浦さんの奥さん、という言い方に誇りすら感じる。
译文一:
结婚之前,个人被别人议论点什么都没关系,但一旦成了主妇,就要被人家说某某先生的夫人怎样怎样了,这确实是一件大事,同时,不也是一件很好的事吗?
我没有那种认为守着家庭是一件没有变化的、无聊的事儿的想法。
我甚至从三浦先生的夫人这个称呼中感到了荣耀。
以前,我单身,别人称呼我什么都没有关系。
可是现在别人一开口,就是某某先生的夫人如何如何。
真是非同小可。
……
♦写真を撮ってもらって(だれに)
♦(お客さんが写真屋さんに)
♦てやる(だれに恩を)
♦(写真屋さんに)
♦てくださる(だれのために)
♦(わたしのために)
第四课
第3节句子翻译(倒译)
♦翻译中的变序,通常叫作倒译,即颠倒原文语序进行翻译。
♦一、变序的原因:
♦
(一)句法上的原因;
♦
(二)修辞上的原因;
♦(三)习惯上的原因
(一)句法上的原因:
中日文属于不同的语法体系,虽同用汉字,但是语法差异巨大。
在有宾语的句子中,这种差异格外明显。
中文是主一谓一宾,日文是主一宾一谓。
这个基本语序的不同,自然带来了谓语和宾语各自修饰语语序的不同,把基本语序扩大,中文就成了主语一状语一谓语一定语一宾语,日文则是主语一定语一宾语一状语一谓语。
例1 西に傾きかかった太陽は、①この小丘の裾遠く拡がった有明の入り江の上に、②長く曲折しつつはるか水平線の両端に消え入る白い砂丘の上に今は力なくその光を投げていた。
西斜的太阳,在小山丘脚下远远扩展开来的有明海海湾上,在漫长曲折的遥远的水平线两端消失掉的白色沙丘上,如今毫无气力地放出些光亮。
西斜的太阳无力地照射着在小山岗远处山嘴伸展开来的有明海海湾,照射着曲曲弯弯、隐隐约约地延伸在远处水平线上的白色沙丘。
例2 彼女は、五六日前に読みおわった藤村の「春」を思い出した。
単純なかの女の頭には、自分の夫の天分を疑うて見ることなどは知らずに、自分の夫のことをその小説の中の一人が、①自分の目の前へ---生活の隣へ、②その本の中から抜け出してきたかのようにも思ってみた……。
她想到了那本五六天之前