维新直後における制度変化と组织能力の进化.docx
《维新直後における制度変化と组织能力の进化.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《维新直後における制度変化と组织能力の进化.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
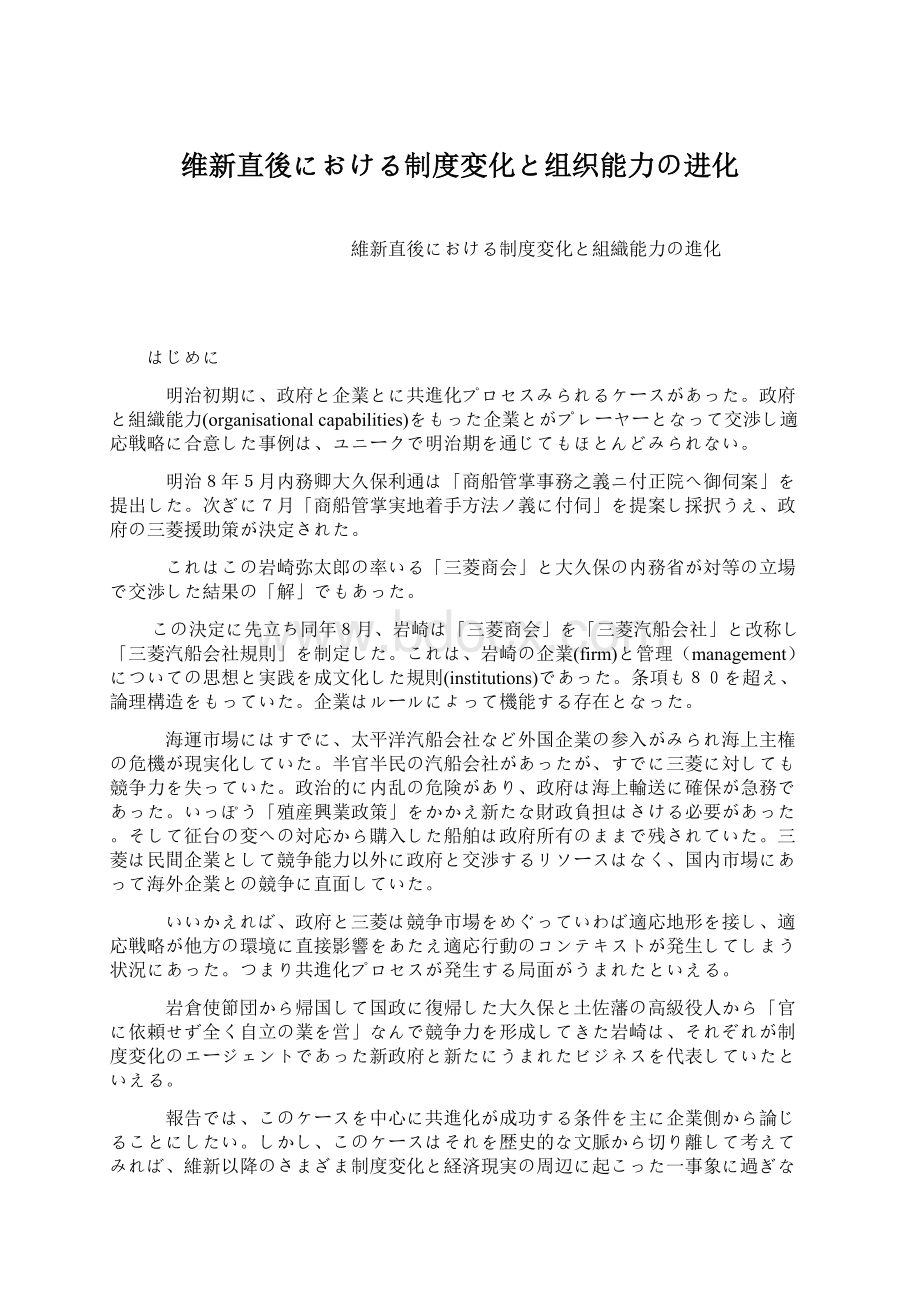
维新直後における制度変化と组织能力の进化
維新直後における制度変化と組織能力の進化
はじめに
明治初期に、政府と企業とに共進化プロセスみられるケースがあった。
政府と組織能力(organisationalcapabilities)をもった企業とがプレーヤーとなって交渉し適応戦略に合意した事例は、ユニークで明治期を通じてもほとんどみられない。
明治8年5月内務卿大久保利通は「商船管掌事務之義ニ付正院へ御伺案」を提出した。
次ぎに7月「商船管掌実地着手方法ノ義に付伺」を提案し採択うえ、政府の三菱援助策が決定された。
これはこの岩崎弥太郎の率いる「三菱商会」と大久保の内務省が対等の立場で交渉した結果の「解」でもあった。
この決定に先立ち同年8月、岩崎は「三菱商会」を「三菱汽船会社」と改称し「三菱汽船会社規則」を制定した。
これは、岩崎の企業(firm)と管理(management)についての思想と実践を成文化した規則(institutions)であった。
条項も80を超え、論理構造をもっていた。
企業はルールによって機能する存在となった。
海運市場にはすでに、太平洋汽船会社など外国企業の参入がみられ海上主権の危機が現実化していた。
半官半民の汽船会社があったが、すでに三菱に対しても競争力を失っていた。
政治的に内乱の危険があり、政府は海上輸送に確保が急務であった。
いっぽう「殖産興業政策」をかかえ新たな財政負担はさける必要があった。
そして征台の変への対応から購入した船舶は政府所有のままで残されていた。
三菱は民間企業として競争能力以外に政府と交渉するリソースはなく、国内市場にあって海外企業との競争に直面していた。
いいかえれば、政府と三菱は競争市場をめぐっていわば適応地形を接し、適応戦略が他方の環境に直接影響をあたえ適応行動のコンテキストが発生してしまう状況にあった。
つまり共進化プロセスが発生する局面がうまれたといえる。
岩倉使節団から帰国して国政に復帰した大久保と土佐藩の高級役人から「官に依頼せず全く自立の業を営」なんで競争力を形成してきた岩崎は、それぞれが制度変化のエージェントであった新政府と新たにうまれたビジネスを代表していたといえる。
報告では、このケースを中心に共進化が成功する条件を主に企業側から論じることにしたい。
しかし、このケースはそれを歴史的な文脈から切り離して考えてみれば、維新以降のさまざま制度変化と経済現実の周辺に起こった一事象に過ぎない。
また、いままでの経済史の通説では、政府の殖産興業政策と「財閥」の成立という物語で一括されてしまう事実である。
この点を考慮して、明治初期(明治10年頃まで)の制度変化の歴史のアウトラインを記述することにした。
重要な歴史的な事実をふまえ、経済史家ダグラス・ノースの視点にそくして、制度変化、成果、エージェントの特性について記述し、その特性を論じることにした。
また、組織能力の形成の歴史的研究についても紙面の許す範囲で触れることにした。
1.経済制度の発達段階
ダグラス・ノースは、交換形態と取引のルールのパターンを(1)小規模の村落貿易、(2)遠隔地貿易 (3)複雑で非個人的な交換形態の三つに分けている。
移行にともなって、取引コストを引き下げるような、制度的枠組み(institutionalarrangements)が再編成されると主張する。
たとえば、(2)の遠隔地貿易の成長では、エージェンシー問題と異質な世界での契約の遂行と執行の問題を解決ために、度量衡、身元保証、商慣習法裁判などが発達し、取引の安全性は向上され、取引コストは低下する。
ノースは、所有権が国家によって保証され、執行が裁判制度によって担保される制度変化が経済成長の前提であると考えている。
ノかれが「制度・制度変化・経済成果」で成功事例として紹介している制度変化には、合衆国の発展パターンの基本的な枠組みを準備した「東西条例」、レント・シーキング活動を減少し所有権の安全性を高め公正な司法システムを生み出したイギリスの議会制度がある。
このような視点にたって、維新直後の制度変化の評価を試みたい。
まず、交換形態と取引のルールのパターンついてであるが、(2)の段階には完全に到達していたといえる。
各藩の租税と物産は大坂に輸送され、大坂の米市場で全国の標準価格が形成され、大坂の問屋を通じて諸国物産の全国流通網が成立していた。
先物取引、為替手形、度量衡の統一、沽券、担保さらには紛争の裁判制度も成立していた。
海運業では、業者の慣習法であるが共同海損についても安定したルールまで機能していた。
つぎに所有権が国家によって保証され、執行が裁判制度によって担保されていたかであるが、「農地」については「田畑永代売買の禁令」等でみえるように所有権は制約されていたが、商業取引では所有権は安定し債権は保護されていた。
闕所は例外的で、大名貸は大商人の債権として保全されていたことを前提としたビジネスであった。
商家では、「家」制度のもと家産の継承がルール化され、家憲もつ商家も多く、帳簿をつけ実証的なデータに基づいたマネジメントが行われていた。
このように商取引は安定した制度的アレンジメントのもとで発達し、制度自体、あるいはそれをもとにうまれた商業的なスキルも先進的なものであったと評価できる。
ところが、維新期になって欧米列強の重圧を感じ、国際環境のなか日本のビジネスを考えると、その限界のほうが認識されるようになった。
制度を評価する認知モデルが変化したからである。
この流通システムは、大名領国制を前提にした商品流通であった。
大名には、専売制でみられるように経済政策の自律的な支配権が与えられていた。
大坂を中心とする全国的な流通網も藩の余剰生産物の物流に限られていた。
株仲間があり自由な経済活動が制限されていたし、各藩が藩札を発行しており取引コストが高かった。
非常に発達した商取引のシステムはあったが、領国の余剰生産物の流通の範囲だけが先進地域にすぎず、伝馬制、関所、津留、農地の所有権制限、農民の米穀販売禁止など封建的な制度も藩レベルの取引では多く残っていた。
新政府の経済基盤は脆弱で、欧米との生産技術の格差は絶望的なものであったので、「会社」や「銀行」などがない経済システム面での後進性も強く意識されることになった。
ノースの段階論では(2)のレベルを超え、先進地区の商人に限定すれば一部は(3)の段階に入っていたといえる。
商人が必要とする範囲で所有権の安定性があり、契約を執行する政治的、司法的な制度的アレンジメントが存在したからである。
しかし、それはいわば専門プレーヤーのなかだけで認定できることであり、市場が統一され近代的な統一民商法典と裁判制度があったわけでなかった。
維新政府は条約改正を目標とし、統一的法典整備を即座に着手したが、法典施行は遅れ旧制度と慣行が明治中期まで存続しえたことを考えると、財産法の分野では旧制度の完成度がむしろ高かったと推定される。
ノースは複雑で非個人的な交換形態の段階では、「資本市場の創出と大量の固定資本を伴う製造企業の発達は何らかの形態の強制力をともなう政治的秩序(coercivepoliticalorder)」が必要であると述べているが、まさにこの制度的な次元が明治初年の日本の経済制度では完全に欠落していたからある。
渋沢栄一で代表される明治の先進的な知識人は専らこの部分の後進性に着目したといえる。
比喩的にいえば、(3)の段階に片足は入っていたが後ろ足は(2)の最期のところに止まっていたといえよう。
これは、日本が工業化を経ていなかったことをいみする。
2.制度変化のエージェント
つぎに維新直後の制度変化のエージェントがだれだったか、どのような目的と思想をもっていたかを考えてみよう。
当時のビジネスマンは商人であった。
変革のエージェントを外部環境と相互作用する能力を備え、欧米との格差に問題認識があり対応する行動が可能なものと考えると、商人には絶無であった。
実際、既得権益のある伝統的商家および商人は、近代化産業の担い手に転換できなかった。
森村市左衛門、伊藤小左衛門、鹿島万平など幕末に商人であって時勢の変化が理解できたものもあったが、制度変化のエージェントたりえた在来商人は見られない。
鴻池、住友をのぞいて大坂の大商人はほとんど没落した。
三野村利左衛門(三井)や広瀬宰平(住友)らの努力は、明治初期から始まっているが、新政府の制度変化と近代技術に対応する段階であり、制度変化のエージェントとなるような実力は備えていなかった。
鉄道、紡績、鉱業分野で会社勃興の現象がみられるのは、明治19年以降である。
井上馨、渋沢栄一、大久保利通、伊藤博文、前島密、陸奥宗光などが制度変化の担い手であった。
井上、渋沢は民間人となり、商社(先取会社)や銀行(第一国立銀行)を経営したこともある。
大久保は殖産興業政策の中心人物であり、伊藤は、通商司、通貨、国立銀行制度、大隈は工部省の創設、前島は郵便と海運、陸奥は地租改正で制度変化のエージェントであった。
彼らの業績のなかでノースが制度変化の成功事例としてとりあげている北西条例や議会制度のような、すべてが一点に収斂するような基本的な制度変化をあげることは困難である。
統治権が全国に直接及ぶようになったことは、基本的変化であるが適応戦略のフィールドに関係するもので、戦略の具体的な内容を意味するわけではないからである。
明治10年までに実施された諸政策は「個体群」をなして相互作用し、中期以降の「企業の勃興」と「財閥」の成長を生んだということができる。
志士から官僚に転換したイノベーターは、一つの個体群を形成していた。
渋沢を除いてビジネスの経験はなく、多くは洋行の経験があり、維新直後に大蔵省等で経済問題を扱う官僚となった。
富国強兵と条約改正のため、①民間企業の発達が必要であると考えたこと、②政府の経済基盤が弱体であったが、逆に国家の法的な権力は無制限(絶対的)と考えたこと、③外資導入は行わないことは共通している。
しかし、各人の担当分野や時期、欧米との格差の大きさや民間セクターの反応の鈍さをどのように考えるか、啓蒙主義的な性行や権力に対する考え方などによって差異がみられた。
たとえば、明治初年商法司は農商を奨励し物産を興起するためには「農工商の業に干渉し大いに金融開通の策を施さん」とう目的のもとに設立された。
ここにはビジネスへの干渉について時期と条件見極めて手段を選ぶという思考はみられない。
他方、大久保利通は明治8年「商船事務管掌三態ノ区分」で、「政府は、人民が独歩成立できると判断したときは、ただ規則条例を制定し、人民が遵守するようにさせる。
これが政府の保護の内容となる」と述べている。
つまり、政府の保護(あるいは干渉)は、民間セクターが弱体の時期に行われ、自立すると後方にさがって「審判者」の機能にもどることが本来であると考えている。
新政府は、政策のバックボーンになるような理論を前提にて体系的に諸政策の立案と実施をおこなったのでないので、一見矛盾するような認識あるいは当時の現実から乖離した先進的な政策の実行、また現実の状況を考えて原則との妥協はかるような思考がみられることもしばしばあった。
ここでは、政府の会社法制を例に触れておきたい。
廃藩置県直前の明治4年6月に大蔵省が公刊した渋沢栄一の『立会(りゅうかい)略則』と行政手続きをみてみよう。
まず同著の内容を要約するとつぎのようになる。
共同出資で商社を設置することが、国内商業だけでなく海外貿易で重要である。
「自身一個の私論に固執」してはならない。
共同出資で会社を設立することは私権の領域に属すから、政府は「威権をもって推し付け、又は法制を以て縛るべからず」である。
政府みずから商業活動をなすことも弊害が大きい。
「会社」設立は、国法に触れなければ原則自由であるはずである。
損益は、株金の割合に応じて支払われるべきである(有限責任について言及なし)
しかし、設立認可の実務にあっては、員数、資本金、社中の業名、定約規則を明細に記載して、地方官に申請する。
地方官が審査し、書面を政府に廻し政府が免許を出す。
また、「会社」であっても政府が管理を派遣し、資金供給し保護する種類の会社があってよい。
為替会社、鉄道会社、郵船会社などがその例である。
渋沢は、公益のため共同出資を奨励し営業の自由を保障するが、免許の実務は厳格になって許可制近くなることや、特殊会社も認めるという内容であった。
政府のメッセージは、会社には①株仲間と異なる出資者が多数いなくてはならない、そして②会社は私益を追求するより公益を増進するためにあるという内容であった。
共同出資であるかどうかは実際に審査されたと推定される。
東京、大坂で設立出願した会社名で例外なく「藍商社」「魚産会社」「石油会社」など一般的な名称で、明らかに個人の名称を関しているのは明治六年段階ではみられないからである。
また、民間では、「会社」「商会」は「官許」であると考えられそれだけで信用を増したのでその理由で認可を申請するものもいたと予想される。
また明治6年を転機に会社設立が多くなったが、政府は会社に対する一般取締規則を制定しえなかった。
政府は社則を点検し発起人に身許調査も行ったが、申請数が増え、「会社」の信用を利用する不正行為が続出しはじめた。
執行能力がともなわないにもかかわらず、「会社」「商社」の官許を与えることはかえって、取引信用秩序を損なうということになり、明治7年4月以降は、将来の一般会社条例制定までは「人民相対に任す」方針に変更した。
政府は事実上認可制を停止し、当分市場での相互信頼に委ねること制度を変更した。
3.制度変化の成果
資本市場の創出とビジネスの発展をめざして明治初年から積極的であった新政府は、商法司(明治元-2年)と通商司(明治2-4年)では失敗した。
この失敗で共通しているのは、藩の領主権が強いこと、商人が消極的で能力が低かったこと、そして政府の干渉が大きかったことである。
これ以降の制度変化は、事業リスクを小さくし、取引コストを引き下げ、市場機会を拡大することに効果があったといえる。
職業選択の自由と移動の自由が具体的な制度によって保障された。
関所と伝馬制さらに旅行の禁止あるいは制限が撤廃された。
陸運会社の設立も認可された。
四民平等となり職業選択の自由が認められた。
江戸時代の国内専売の延長にあった藩商会所を禁止し、廃藩置県で藩が廃止され商業の担い手が商人であるとの原則が現実に実現された。
商工業では株仲間が解散され売価は自由となった。
このように営業の自由は保障された。
さらに地代、家賃および傭人給料も自由契約が原則とされた。
廃藩置県以降、このような経済的な自由権の保障は全国共通の法律に基づいて施行されたので、国内でのビジネス活動に共通のルールができそれが取引コストを引き下げたといえる。
政府は、藩札、藩債を処分し十進法に基づく統一通貨制度をさだめた。
また地租改正によって、農地のみならず市街地、武家屋敷にも課税標準にしたがって税が課せられた。
戸籍と土地登記は、統一的なフォームで整備された。
太政官布告の「代人規則」は、総代理人と部理代理人とを区別し、委任状と実印で代理人が20歳以上であることが必要と定められた。
明治6年に「金穀貸借請人証人弁償規則」が制定されが、請人証人の「弁済可致旨」という署名がなければ責任を負わなくてもよいという規定であったので、8年に改定された。
このように取引コストを引き下げる制度的なルールが公権力によって次々とだされて、それが全国に普及した。
しかし、経済自由権を保障し取引コストを引き下げる制度的変革だけで、工業化がスタートするとは明治の変革のエージェントは楽観していられなかった。
資本市場を創設し、固定資本投資をともなう企業が生まれるために、さらなる制度変化が必要だった。
一つはインフラの整備である。
外債を募り東京-横浜間に鉄道を敷設した。
また郵便事業を官営で始め全国的な郵便制度を確立した。
電信も官営の決定なされ、東京-横浜のサービス供給とともに公衆電報が始まり、明治6年には東京大坂から長崎を通じて海外へ電信できるようになった。
制度的なインフラもある。
株式取引条例が明治7年に制定された。
最初の取引所に関する成文法である。
欧米の制度を研究して制定されたが、ロンドン取引所の直訳的な輸入で実情に適さなかったといわれ、政府発行の公債証書や株券も少なくかったのですぐには「株式取引所」の設立には到らなかった。
もう一つは、海運、銀行、鉱山についての個別の事業法の制定である。
国立銀行条例が、銀行制度を移植し同時に不換紙幣を整理する目的で明治5年に設立された。
銀行設立と認可の条件があらかじめ明らかにされた。
それは、資本金4割を本位貨幣で保持し兌換準備にあて、残り6割を政府紙幣で準備しこれを金札引換公債証書と交換したうえで発券担保として政府に供託し同額の兌換銀行券を下付されるというものであった。
国立と名称があるが、国が認可した私資本の銀行であった。
しかし、認可基準が明確にされ「会社」の一つの標準になった。
鉱業は、金銀銅が貨幣鋳造や貿易決済・外貨獲得に必要であったので維新時より重視された。
政府は大阪の幕府銅産役所を接収して銅会所とし,幕領の兵庫の生野,新潟の佐渡両金銀山を官収した。
廃藩置県後、三池、高島炭坑、阿仁・院内(秋田)などの鉱山を官有とした。
その一方明治2年に、藩や幕府の統制下にあってそれまで私人に容易に許されなかった公算の採掘を一般私人に開放した。
明治5年に工部省が「鉱山心得書」、翌年同省は民間の鉱山を対象に「日本坑法」を制定した。
これは、鉱物、試掘、借区開坑、通洞、坑業、廃業、製鉱所建築、税納に区分し詳細な規定を準備した。
同法は、鉱物と鉱山は土地所有から分離し政府専有(「鉱山王国制」)としたうえで、日本人に対してのみ一時的特許として採掘を認めるという方針を明示した。
したがって、「請負の鉱山を以て私に借金の質物とする」ことは禁止された。
借区期間は15年とされ、西洋の機械を導入し、外国人技術者を雇用する手続きも定められた。
このように鉱業でも民間が参入しうる条件を法律によって明示し、あわせて事業とマネジメントの標準を示した。
海運では、貢租米の安全かつ大量な輸送のため、明治3年西洋型船舶所有者の保護を示達し、同時に「商船規則」を定めた。
これは蒸気船の購入から運航、荷の陸揚げ、荷物取引の届け出、外国船員雇用許可、出入港の届出などを規定している。
銀行、鉱山、海運は、それぞれ兌換銀行券、貨幣鋳造、郵便・貢租米と関連し公益性の高い分野であった。
しかし同時に、標準をさだめて民間人に事業機会を公開した。
価格・生産量をコントロールする統制をめざしたものではなく、許認可の規準やマネジメントの原則、標準を示したものであったといえる。
各事業別に事業機会とマネジメントを事前に制度化し、民間セクターの参入を準備した。
銀行、鉱山、海運の分野でみられた事業法の制定は、「資本市場の創出と大量の固定資本を伴う製造企業の発達」を目的として、制度的変革が急ピッチで進んでいたことを意味しよう。
これらの成果を確認しておきたい。
明治9年、国立銀行条例は改正された。
認可の高いハードルが取り外された。
銀行券の金貨兌換を取りやめた。
これは世界的な銀貨下落と輸入超過のため金が盛んに流出したためでる。
資本金の8割を公債証書で政府に供託しそれと同額の銀行券を発行し、後の2割を政府紙幣で保持して引換準備にあてればよいことになった。
銀行の設立は容易になり、国立銀行は明治12年末には193行にまで激増した。
また改正で国立銀行でなくても「銀行」の名称が利用できるようになったため、三井銀行など普通銀行も設立されるようになった。
鉱業の民間セクターのブレークは、明治17年以降に官有鉱山が民間に払い下げられてから始まった。
明治20年代の企業勃興期の石炭や金属の需要が鉱業への投資を誘発したし、技術水準も向上した。
明治25年政府は鉱区について重要な「日本坑法」改正がおこなった。
借区が15年と規定していたが、その権利を採掘権として永久の権利として認めることに制度変更した。
これは、安全に巨大な固定投資を行い、多数の坑夫を雇用し大事業を展開できることを可能にした。
海運業では民間の事業者がでるまえに、政府自ら蒸気郵船規則を定め、政府監督下に半官半民の「回漕会社」を設立し、政府所有船舶と大藩の委託船舶を用い、明治3年に大坂-東京の定期航路を開設させた。
同社は、郵便、貢租米の独占が認められ、運営資金を為替会社からの融資があった。
しかし、船舶が老朽で、蒸気船を用いた海運業の経験に乏しく一年で解散した。
4年に廻漕取扱所を設立し業務を継承した。
廃藩置県で各藩所有の蒸気船が集約されすべて政府所有となった。
同船舶を「会社」を創設しそれに貸与するというアイデアを大蔵省の渋沢が前島に提案、前島が会社設立から管理規定まで指導して、明治5年8月「日本郵便蒸気船会社」設立し同時に廻漕取扱所を廃止した。
政府所有船舶十数隻を代価25万、永年賦償還の条件で払い下げ、東京-大坂間の定期航路、函館-石巻の不定期航路に就航させた。
貢租米輸送は独占で、沖縄航路のため年額6千円の補助金が与えられた。
明治5.6年頃、同社の広島丸(1869トン)を洋上でみて、岩崎弥太郎は川田小一郎(のち日銀総裁)に「我社ではいつになったらこのような船をもてるのかと」慨嘆したといわれている。
しかし同社は明治7年末になると、岩崎の三菱会社との市場競争に敗れている。
政府は外国人による沿岸貿易への参入を取り締まるため明治3年に「不開港場取締心得方規則」を出している。
外国海運業による参入も本格的に始まっていた。
岩崎は、二つの外国の海運業者との競争に勝ち西南の役の政府需要に応え、三菱汽船会社を独占的な大企業に成長させた。
銀行、鉱業、海運では事業機会にアクセスできる条件をルール化し、必要なマネジメントを標準化することで、参入のコストを低下したといえる。
しかし、政府が、生産技術の未熟さから生まれる投資リスクを引き下げようとした施策が一定の分野でみられた。
工部省によって始められ内務省の殖産興業政策に引き継がれた。
造船(船舶修理)、セメント、ガラス、製糸、紡績、製糖などの分野で、官営模範工場が創設された。
これらは、採算にのる適正規模、技術水準、マネジメントなどモデルを民間に示したものといえる。
官営鉱山もふくめ、技術の伝播や事業リスクを低下に寄与したといえる。
赤字に耐えかねた政府は工場払下概則を出して官営工場の民営化に転換した。
しかし工場払下概則の条件が厳しく実情に適していなかったために進まず、同17年廃止した。
以後民間業者の取得が進み、生産性のある工場に転換された。
以上いくつかの制度変化を説明したが、個々の制度変化の相互作用について触れておきたい。
それぞれの制度変化が他の制度変化の与件となって影響しパーフォーマンスの差を生んだことから共進化のケースと認定することもできる。
相互作用がプラスのフィードバックを生んだ例でもある。
地租改正によって税は金納となり貢租米輸送の必要はなくなったが、物価を全国的に平準化しなければ実際の税率に格差が生まれることから、大蔵省も海運業の発達を期待した。
廃藩置県によって各藩が所有していた船舶が政府に集約され、規模の利益をはかるため「日本郵便蒸気船会社」が設立された。
『立会略則』著者である渋沢栄一が大蔵省にあって発案したビジネスモデルであった。
地租改正が、廃藩