日本神话に见る日本文化考.docx
《日本神话に见る日本文化考.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《日本神话に见る日本文化考.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
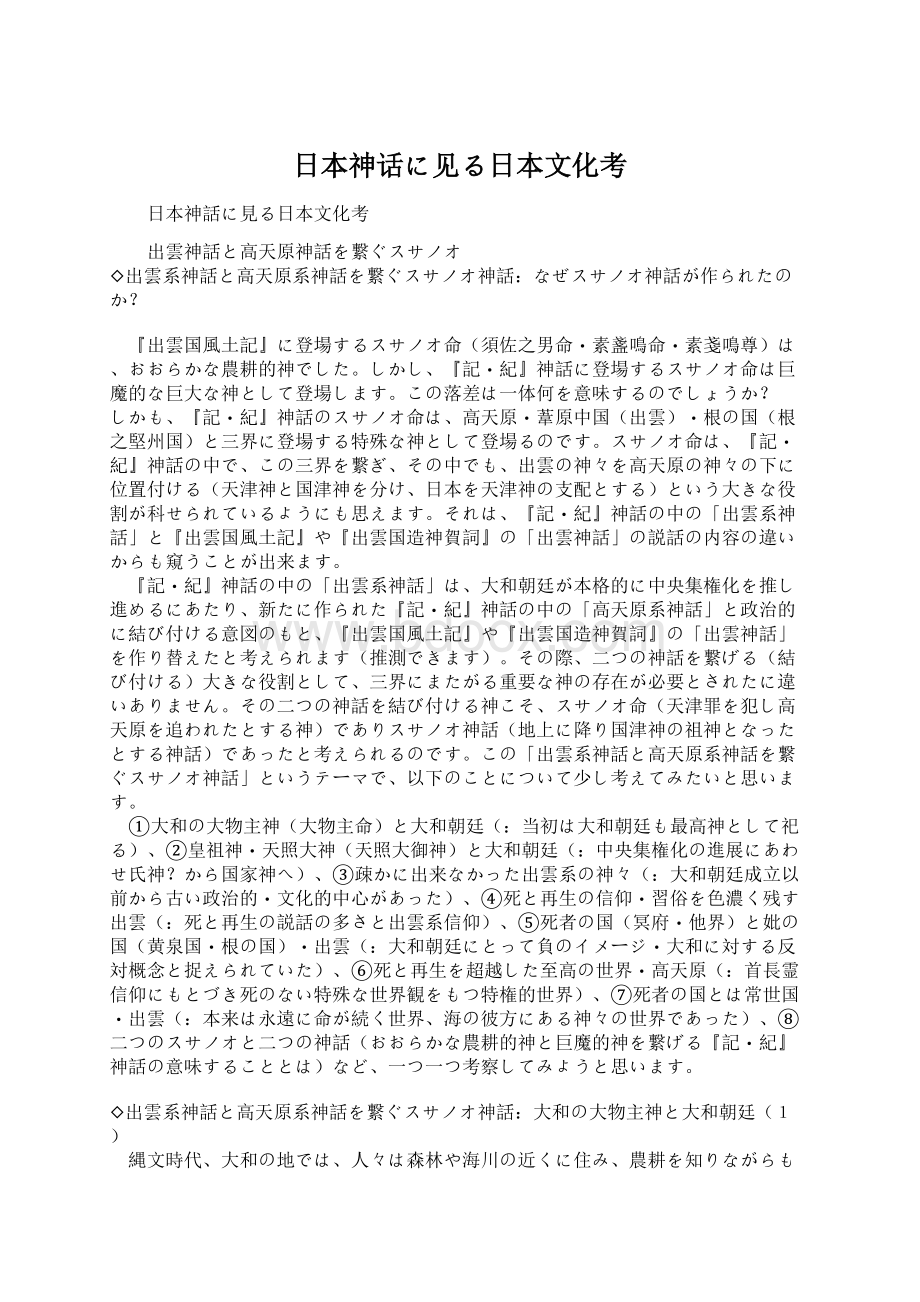
日本神话に见る日本文化考
日本神話に見る日本文化考
出雲神話と高天原神話を繋ぐスサノオ
◇出雲系神話と高天原系神話を繋ぐスサノオ神話:
なぜスサノオ神話が作られたのか?
『出雲国風土記』に登場するスサノオ命(須佐之男命・素盞鳴命・素戔鳴尊)は、おおらかな農耕的神でした。
しかし、『記・紀』神話に登場するスサノオ命は巨魔的な巨大な神として登場します。
この落差は一体何を意味するのでしょうか?
しかも、『記・紀』神話のスサノオ命は、高天原・葦原中国(出雲)・根の国(根之堅州国)と三界に登場する特殊な神として登場るのです。
スサノオ命は、『記・紀』神話の中で、この三界を繋ぎ、その中でも、出雲の神々を高天原の神々の下に位置付ける(天津神と国津神を分け、日本を天津神の支配とする)という大きな役割が科せられているようにも思えます。
それは、『記・紀』神話の中の「出雲系神話」と『出雲国風土記』や『出雲国造神賀詞』の「出雲神話」の説話の内容の違いからも窺うことが出来ます。
『記・紀』神話の中の「出雲系神話」は、大和朝廷が本格的に中央集権化を推し進めるにあたり、新たに作られた『記・紀』神話の中の「高天原系神話」と政治的に結び付ける意図のもと、『出雲国風土記』や『出雲国造神賀詞』の「出雲神話」を作り替えたと考えられます(推測できます)。
その際、二つの神話を繋げる(結び付ける)大きな役割として、三界にまたがる重要な神の存在が必要とされたに違いありません。
その二つの神話を結び付ける神こそ、スサノオ命(天津罪を犯し高天原を追われたとする神)でありスサノオ神話(地上に降り国津神の祖神となったとする神話)であったと考えられるのです。
この「出雲系神話と高天原系神話を繋ぐスサノオ神話」というテーマで、以下のことについて少し考えてみたいと思います。
①大和の大物主神(大物主命)と大和朝廷(:
当初は大和朝廷も最高神として祀る)、②皇祖神・天照大神(天照大御神)と大和朝廷(:
中央集権化の進展にあわせ氏神?
から国家神へ)、③疎かに出来なかった出雲系の神々(:
大和朝廷成立以前から古い政治的・文化的中心があった)、④死と再生の信仰・習俗を色濃く残す出雲(:
死と再生の説話の多さと出雲系信仰)、⑤死者の国(冥府・他界)と妣の国(黄泉国・根の国)・出雲(:
大和朝廷にとって負のイメージ・大和に対する反対概念と捉えられていた)、⑥死と再生を超越した至高の世界・高天原(:
首長霊信仰にもとづき死のない特殊な世界観をもつ特権的世界)、⑦死者の国とは常世国・出雲(:
本来は永遠に命が続く世界、海の彼方にある神々の世界であった)、⑧二つのスサノオと二つの神話(おおらかな農耕的神と巨魔的神を繋げる『記・紀』神話の意味することとは)など、一つ一つ考察してみようと思います。
◇出雲系神話と高天原系神話を繋ぐスサノオ神話:
大和の大物主神と大和朝廷(1)
縄文時代、大和の地では、人々は森林や海川の近くに住み、農耕を知りながらも、狩猟採集を主たる生活手段としていました(縄文文化)。
縄文の人々は自分たちの生活を豊かにしたり、また災いをもたらしたりするもの(精霊、霊魂、霊鬼、霊威)を、すべからくカミと見なし、そのカミは恵みと恐れの神(森羅万象、自然には創造と破壊、荒ぶる力と和らぐ力を繰り返します。
その自然の摂理の圧倒的な姿の背後に人智を越えた大いなるもの、聖なるものの存在を感じ取るのです)としていたようです(精霊崇拝・精霊信仰)(※注1)。
原初の三輪山の神もこのようなカミであったと考えられます。
大和の御諸である三輪山は、御諸(みもろ)とは御室(みむろ)ともいわれ、神奈備山(かんなびやま、神山)のことです。
正体を蛇神とされる大物主(三輪山の神を、恐ろしき「モノ」=大物主と名付けたのは、大和朝廷の側であり、それは、決して本来的な名ではなかったと考えられます)が棲むというこの山麓は、実は太古からの太陽信仰(朝日信仰)の地でもあったのです。
(※注1)万物にカミなるものが存在するという思想は「アニミズム」と呼ばれていて、世界中のあらゆる民族の文化の古層に確認されています(マナイズム、自然崇拝、死霊崇拝などの原始的な宗教観念も、縄文人の信仰には祖霊信仰の要素があるとも)。
確かにアニミズムは近代合理主義とは相容れないものがありますが、現代科学でも解明できない自然界の神秘や、大地震などの災害、眠る時に見る夢や熱狂してトランス状態に陥る人間の心理のなかに見ることができます。
特に、アジアそして日本では近代文明が発達し、合理化が進んでも、習俗や祭りなどの中にアニミズム的な意識が濃厚に残っています。
縄文時代は土偶・ストーンサークル・ムラ集団の形などの研究により、アニミズム的な世界(精霊崇拝的な世界)に人々が生きていた時代であるとされていますが、縄文時代が過ぎ時代が変わっても、人間の無意識的な古層の中にはその時代の魂(アニミズム的な世界=精霊崇拝的な世界)が今も生き続けているようです。
『古事記』に記されているオホゲツヒメのような説話や大祓のような儀礼のなかに、縄文文化の土偶や土器などに見られる宗教的・精神的活動を読み取る学者がいます。
土偶は最も一般的な説として、妊婦を表し女性の産む力を大地に感染させて、作物や獲物の豊穣を祈る呪具であったと考えられています(死んだ妊婦の霊を慰撫するとする説もありますが)。
また、ほとんどの土偶が壊れた状態で出土することから、土偶を身代わりに破壊することにより災いや疫病を祓ったのではないかと考えられ、人形(形代)に穢れを移して水に流す神道の祓えに極めて近い儀礼の起源を読み取ることができそうです(ただ、神道の人形の祓えに発展したかは議論があり、中国から渡ってきた習俗ともされています)。
また、土偶が大地の恵みを司る女神(大地母神)を表現しているとする説もあります。
土偶の破壊の跡から、殺されることによって人に穀物をもたらしたオホゲツヒメのような女神の説話を思い出すことができます(※注1)。
『古事記』に登場するオホゲツヒメ(大気都比売神)は、スサノオ命(須佐之男命・素盞鳴命)をもてなすために口や尻から食べ物を出しましたが、汚物を食べさせようしたと誤解され、スサノオ命に殺されてしまいます。
そして、その死体から蚕や稲・栗・小豆・麦・豆が出てきたのだとしています。
『日本書紀』ではウケモチ(保食神)で、ツクヨミ命(月夜見尊)に斬殺されたとしています(※注2)。
すると、こうしたオホゲツヒメなどの説話は縄文時代の宗教的儀式の名残りなのでしょうか。
しかし、大地母神的土偶信仰も形代的土偶信仰も弥生時代には継承されず(伏流水のように継承され)、なぜか『記・紀』神話に突然復活したかのように登場します(さなざまな意見があります)。
(※注1)縄文時代の初期から女性像の土偶が作られており、大地母神の崇拝があったと考えられます。
しかし、それが縄文時代中期になると、作った土偶を破片にし、方々の場所に分けて処理していたようです。
当時の人々にとって栽培という行為は、大地である女神の体を害することにより、その死体の破片から毎年、作物が生え出してくるということを意味していました。
弥生時代になると、稲を始めとする五穀が最も大切な作物になり、神話も五穀の始まりを説明するものへと変っていきました。
それが、『記・紀』に記されているオホゲツヒメやウケモチの説話になったと考えられます。
この部分は縄文時代の神話を受け継いでおり、女神の体から生み出された作物は、神話が編纂された当時の農業を反映して、五穀の起源を説明しているようです。
(※注2)ツクヨミ命は、『日本書紀』によると、男の月神で乱暴な神とされます。
食物の神・ウケモチ(保食神)を殺し、姉神のアマテラス(天照大神)から「悪しき神なり」と罵られ、それ以来日月は昼と夜で別々に住むようになったと語られています。
そのウケモチから粟・稗・稲・麦・大豆・牛・馬・蚕などができたので、アマテラスはこれらで農耕を始め、養蚕を始めさせたといいます。
このようなタイプの説話は、ハイヌウェレ型説話に属し、南方に多く
◇出雲系神話と高天原系神話を繋ぐスサノオ神話:
大和の大物主神と大和朝廷(3)
縄文土器(蛇体装飾の土器)には、縄文人の世界観(死生観・宇宙観)が表れていそうです。
(蛇はシャーマニズムとも深く関係し、シャーマンは自分の霊力を示すために、蛇を手なずけていたようです)。
それは、蛇に象徴される死と再生の円環的世界観(森の思想・命の共生と循環)です。
これは森とともに生き、森の永劫の死と再生の循環の中に身を委ねていた縄文人にとって自然な感覚であったと思われます。
蛇は死と再生(復活・循環)を繰り返す大地の霊そのものであると考えられていたようです(森が破壊されていくとともに、蛇を神とする世界観は失われ、蛇を邪悪のシンボルとみなされていきます)(※注1)。
縄文後期以降になると、縄文土器は、突如として消滅してします(おどろおどろしいまでの情念の造形=荒ぶる藝術から、静謐さと単調さの造形=寡黙な職人の工芸へと変化)。
しかし、なぜか神話・説話・民話のなかに再び甦るのです。
その例として、『常陸国風土記』に出てくる蛇神・ヤト(夜刀神)、諏訪地方に伝承されていた蛇神・ミシャグジ、出雲系神話のヤマタノオロチ(八俣大蛇)、それと大和・三輪山のオオモノヌシ(大物主神)です。
夜刀神や八俣大蛇は蛇神であり、自然の猛威を神格化した自然神とされ、ともに英雄によって退治される悪神とされています。
これは、猛威をふるう縄文の神を弥生人が退治したという説話とも考えることができそうです。
(※注2)。
(※注1)古代人にとって蛇は、旺盛な生命力・繁殖・豊穰のシンボルとして考えられていたようです。
蛇は古い皮を脱ぎ捨てて脱皮を行う生き物であることから、新しい身体を得て生まれ変わる様子に、古代人は再生・治療・永遠の命を見ていたと考えられます。
蛇信仰にまつわる伝承は多く、夜刀神伝承、ミシャグジ伝承、八俣大蛇伝承、箸墓伝承などがあり、蛇の古語「カカ」から類推すると、鏡(蛇の丸い目)、案山子(蛇をデフォルメ)などは蛇を見立てたものと考えられ、正月の「鏡餅」は蛇がトグロを巻いた形とされ、関西に多い丸餅は蛇の卵の造形であるとも云われています。
ふと身の回りを見渡すと、現在の日本の習俗や行事に蛇の象徴(カミの具象としての蛇)に溢れていることに気付きます。
時代が下り文明化されていく中で、蛇信仰は表面から姿を消していきますが(やがて稲作文化の拡大とともに、蛇信仰は水の神や農耕神の信仰へと変質していきます)、蛇信仰そのものは隠された形で脈々と今日まで受け継がれきたのです(今日に至るまで、隠れた地下水のように脈々と流れ続けて、日本の文化や日本人の精神構造に深く根を下ろしてきたのです)。
◇
(※注2)日本には太古から蛇信仰があったことは知られています(縄文人が蛇に寄せた強烈な思いの源は、生命の根源・強さに対する憧れや希求、生命力と再生力への崇拝、死と再生の循環のシンボル、水と母なる大地への信仰など、それらすべてが凝集して神与のものと考えられ、その象徴が蛇として捉えられたようです。
)。
縄文土器の縁や把手に無数の蛇が描かれていますし、そもそも縄文の「縄(なわ)」そのものが蛇の表現ではないかとされています(注連縄なども)。
全国には山そのものを御神体とした神社も多く、それらを「神奈備山(かんなびやま、神山)」とか「御諸(みもろ)・御室(みむろ)」と呼びます。
その代表例が大和の三輪山で、この三輪という名前そのものが蛇がトグロを巻いている姿(円錐形の姿)を表しているとされています。
また三輪山の神・オオモノヌシ(大物主神)は古来より蛇神で、水神・雷神であるとされています。
◇出雲系神話と高天原系神話を繋ぐスサノオ神話:
大和の大物主神と大和朝廷(4)
三輪山を御神体(山そのものが御神体=神奈備山)とする大神神社(おおみわじんじゃ)は奈良県の桜井市にあります。
三輪山は、奈良盆地をめぐる青垣山(倭は 国のまほろば たたなづく 青垣 山隠れる 倭し 美し)の中でもひときわ形の整った円錐形の山(高さが四百六十七メートル、周囲十六キロメートル、南は初瀬川、北は巻向川の二つの川によって区切られ、その面積はおよそ三百五十ヘクタール)で、古来より神の鎮まる山として御諸山(みもろやま)、美和山(みわやま)、三諸岳(みもろのおか)と称され崇拝されてきました(山内の一木一草に至るまで、神宿るものとして、一切斧を入れることをせず、松・杉・檜などの大樹に覆われています=千古不伐。
いまでも禁足地として神社の許可がないと登れないそうです)。
そうしたことから、大神神社に本殿はなく、拝殿裏の三ツ鳥居を通して直接に三輪山を拝する形になっているのです(※注1)。
境内は蛇との縁が深く、参拝に行くと拝殿下の手水所で、まず蛇に迎えられます。
蛇の口から出る水で清めをして拝殿に向かうと、右手に「巳の神杉」という大杉があります。
ここには蛇(巳=みいさん)が祭られていて、いつも蛇の好物であると言われる卵と酒が供えられています。
このように古来から、三輪山は根強く蛇信仰が残る山でした(※注2)。
(※注1)三輪山は山全体を神体山として古代信仰をそのまま今日まで伝えており、古代祭祀信仰の形態を知る上で重要な史跡です。
神社は拝殿のみがあって本殿はなく、三輪山の山中には三カ所の磐座があります。
中でも辺津磐座がその中心で、三ツ鳥居からこの辺津磐座までが古来から禁足地とされ、三輪山祭祀の中心の場所でした。
この禁足地からは須恵器や子持勾玉のほか、おびただしい量の臼玉が出土しています。
また大正七年(一九一八年)に発見された山ノ神遺跡は祭祀用の土製模造品のほか、無数の石製品・須恵器・勾玉・臼玉・管玉・小形銅鏡などが出土しています。
これらの遺跡は弥生時代に始まり、奈良時代に至る三輪山麓における古代祭祀の実態を示す貴重な遺跡とされています。
また神域内は、三輪山を中心に、天然記念物として価値のあるものや、重要文化財としての拝殿はじめ、名勝・遺跡・建造物を含む神社境内地としての史跡です。
(※注2)原始信仰においては、蛇は水の神・山の神の顕現として崇拝されていました。
また、蛇はその特異な姿形、脱皮という不思議な生態、強靭な生命力、その恐るべき毒などによって、古来、人々を畏怖させてきたばかりか、強烈な信仰の対象ともなってきました(蛇はその形から男性性を、脱皮するその生態からは出産=女性性が連想され、古代日本人は蛇を男女の祖先神として崇拝したようです。
神=蛇身<カミ>か?
)。
さらに、祖霊が住まう山(神奈備)を蛇がトグロを巻いた形として連想され(蛇の最も特徴的な姿がトグロを巻いた姿形です)、三角錐の山(円錐形の山)を拝むようになったと(信仰の対象となったと)考えられます(神奈備山信仰)。
大和の三輪山がその代表的な(典型的な)例です。
日本人にとってカミとは何か?
その問いは、古代日本人の死生観・世界観、ひいては日本人そのものを問うことになりそうです。
◇出雲系神話と高天原系神話を繋ぐスサノオ神話:
大和の大物主神と大和朝廷(5)
三輪山の山中には至る所に磐座があり、太古よりの多くの祭祀遺跡が出土しています(※注1)。
縄文時代には死と再生の循環を司る神霊・蛇神(大地の神霊)が広く信仰されていたことでしょう。
三輪山もそうした蛇神信仰の象徴としての神奈備山(蛇がトグロを巻いた姿形)であったのです(※注2)。
また、そうした神が磐座に降る(宿る)とする信仰が起こり(磐座信仰)、その遣いの蛇神、雷神の信仰へと発展していきます。
弥生時代になると、稲作の普及と共に水神(雷神・蛇神)、日神信仰(太陽・陽光信仰)も入り、最終的に大物主神へと人格化されていったようです。
三輪の神は古代よりこの地方の祖神として崇敬が篤かったのです(高天原系部族の来住以前に大和に住む先住民族が崇拝していた国魂の宿りし山=三輪山であり、火や水、死と再生を司る山の精霊であり蛇体の主=大物主でした)(※注3)。
(※注1)原始信仰では神木が神籬(ひもろぎ)とされ、巨石が磐境・磐座となり、精霊が来臨し鎮座して神奈備山になりました(自然崇拝のナショナリズム)。
磐座は神の降り立つ巨石の寄り代のことであり、神奈備山は神の住まう山のことです。
このような信仰は、自然物を通じて感じられる「隠れ身の神性」への畏敬の念であったようです。
具体的なモノの背後に感るインスピレーション、聖なるものの感覚です(モノ=精霊と古代の人々は考えていました)。
大神神社には今でも本殿がありませんが、それは三輪山自体が御神体だからです。
その後、剣や鏡、勾玉などを用いて豊穣を呪術する呪物崇拝のフェティシズム、巫術で精霊やカミと交流する術を身に付けた巫覡(ふげき)が行うシャーマニズム(原初的体験、脱魂=他界飛翔=エクスタシー、憑霊=神懸り=ポゼッション、忘我=恍惚=トランスを通して、超自然的な世界と人間界の交流を可能にする)などの信仰が混在し、弥生時代における稲作生産の発展のもとで祖霊信仰も生まれてきます。
(※注2)太古より、山は人間の生活圏であるとともに神の領域でした。
山に入るにはきびしい禁忌が科せられ、限られた時、限られた人以外は立ち入ることのできない神聖な場所でもあったのです(禁足地、神域)。
ことに神の坐す神奈備と呼ばれる山は特別に崇められました。
たとえば、三輪山や富士山のような円錐形をした山や、二上山や筑波山のように二つの峰をもつ山は、神の坐す山として信仰の対象となり、山そのものが神(神体山)であったのです。
こうした考えは古くから人々に、常世国(他界・異界)から依り来る神が山を目印として寄りつく場所だと考えられていたものと考えられます。
次第にそこに神が常住するのだと認識されるようになっていったようです。
このことからも、神の坐す聖なる山(神奈備山・神山)とは、神の世界と人間の世界との境目として神と人とが交わる場所だということがいえそうです。
(※注3)太古より山に超自然的存在を見出す、アニミズム的観念ともいうべき自然物信仰があったことは、日本だけでなく普遍的な精神観・宗教観でした。
超自然的存在に畏れ多いとする観念のなかに、畏怖・畏敬の念を抱く原初的山岳信仰を窺うことができます。
古代には、人は亡くなると肉体から霊魂が離れ、その霊魂は祖先として残された家族を見守るとされています。
そのことから生存者は、自分達を守護してくれる祖先の霊を尊く崇敬します。
ここに祖霊への信仰が成立するのです。
この際、祖霊があの世に行く前に集まる場所は山とされたり、時には山自体があの世とされ、祖霊の宿る場所とみなされるケースが、全国各地に残されています。
このことからも、山は畏れ多い場所と考えられ、祖霊信仰における信仰対象に位置付けられました。
古代の信仰には、山は神の宿る場所、もしくは神そのものであるとする精神観がありました。
こうした神奈備山信仰から、人は畏れ多いということで山には踏み入ることがありませんでした。
そこで山麓や平野部から山を崇めようとする信仰形態が生まれたと考えられます。
ここから禁足地という概念と、麓から神祭りを行なう山麓祭祀が発生するのです。
◇出雲系神話と高天原系神話を繋ぐスサノオ神話:
大和の大物主神と大和朝廷(6)
三輪山の大物主神の信仰は、三輪山周辺を支配していた火・水・死と再生を司る山の神の精霊であり(雷神・蛇神でもあります)、高天原系部族の来住以前に大和に住む先住族が崇拝していた国魂の神でした。
また、ヤマトタケル命(倭建命)の説話では、伊吹山の荒ぶる神を退治しようと出かけたところ、その山の神は大蛇となって道を遮り、雲をおこし、雹を降らせたといいます。
山の神は蛇体となるだけでなく、時には白猪や白鹿となって現れます。
このように日本の山の神は、三輪山の大物主神や伊吹山の荒ぶる神のように、山の神→蛇、坂の神→鹿などと、神の使い(attribute)・神の具現としての山河の荒ぶる姿として登場してきます(世界の神話にも多く見られます)(※注1)。
『記・紀』神話のなかには、大物主神の出現をどのように描写しているのでしょうか。
オホナムチ命(大穴牟遅命・大穴持命・大己貴命)の国作り説話のなかで、海を照らして依り来る神(この時に海を光して依り来る神ありき『古事記』。
時に神しき光、海を照らして、忽然に浮かび来る者あり『日本書紀』)と述べています。
海を照らす神は、豊穣をもたらすマレビトであり、原初の太陽神・海神であったのです。
古代の人々にとって自然がそのまま神(太陽・大地・山・火・水・樹木・岩石など自然のすべてに神が宿るとするアニミズム)であり、神がそのまま自然であったのです。
人間はこの自然の懐に抱かれ、生きてきたのです(生かされてきたのです)(※注2)。
(※注1)神話の世界は、アニミズム(精霊崇拝)や普遍的な自然信仰を底流にし、宇宙の成り立ちから歴史上の事実と思われることへの探求、自然の力や人間の死後と再生への探求へと広がりをみせます。
そのイメージは、経験的、客観的、合理的にみれば意味のない抽象的なもの(神話的、非合理的な思考によるもの)に思えるかもしれませんが、神話学者のジョゼフ・キャンベルが述べているように、「詩的な、神秘的な、形而上的な」感覚をもってみれば、神話をイメージした古代人の死生観や世界観の精神構造(精神世界、民族の深層意識を語り継いだ物語)が浮かび上がってきます。
古代の人々は、死と再生の円還的循環(生命の永遠、霊魂の再生と循環)を通して、自然を畏敬し(共生し)、自然(生命の再生と循環システム、生きとし生ける者はすべて大地から生まれ大地に還る、多様性の中の共存)の懐に抱かれ調和してきたのです。
しかし、現代文明は神話的、非合理的な思考法から脱却すところから、学問研究の諸分野が形成され、近代的文明が形成されていきました。
こうした科学技術の発展と文明の進歩(生命の最内奥の仕組みから宇宙空間の構造の研究と知識)は、人間の自然への畏敬の念を奪い(科学技術の発展は、自然を支配できると考えるようになった)、地球環境の汚染と破壊をもたらしています。
現代人は、今一度、古代の人々が自然と宇宙の間に神秘で偉大な生命力を直感した壮大な想像力を思い起こさなければならないのかもしれません(古代の人々は、物質的なものよりも霊魂の方がより現実的と感じて、個人それぞれが魂の完成に力を注いでいたのかもしれません)。
神話が伝えてくれる古代人の精神(感性)が、一元的文化(アメリカ文化を代表する今日的な世界状況)によって席捲される中、多様な文化(マルチ・カルチャリズム)の広がりをもたらし、多様性の中の共存の理念を築いてくれるかもしれません。
(※注2)自然=神は、人間の想像を超えた(人智を超えた)計り知れぬ力を持ち、人間に豊かな恵みを与え、ときには底知れぬ猛威を振るいます。
それゆえ古代の人々は、自然の恵みに感謝をし、自然の猛威に畏怖し、ただその怒りを鎮める以外になく、その自然の偉大な力が神として崇拝されたのです。
自然からするとどうしようもなく小さな存在(無力な存在)でしかない人間は、豊かな想像力(プリミティブな心性)を大いに働かせ、太陽・大地・山・火・水・樹木・岩石など自然のすべてに対して、生き生きとした自然観を心象風景としてとられたのです(原初的な自然観)。
古代の征
◇出雲系神話と高天原系神話を繋ぐスサノオ神話:
大和の大物主神と大和朝廷(7)
東アジアの照葉樹林帯(※注1)では、採集や狩猟など山や森での営みには必ず山の神の加護を祈っていたようです。
例えば、焼畑の造成(森林を伐採・火入れ)に先立っても山の神に供物と祈りを捧げてきたようですし、村の男たちが総出で狩猟に出かけ、獲物の多寡で豊凶を占う儀礼的狩猟の慣行も広くみられました。
また、死んだ人の魂が、山の頂上へ上ってい