日本人の風呂文化について.docx
《日本人の風呂文化について.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《日本人の風呂文化について.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
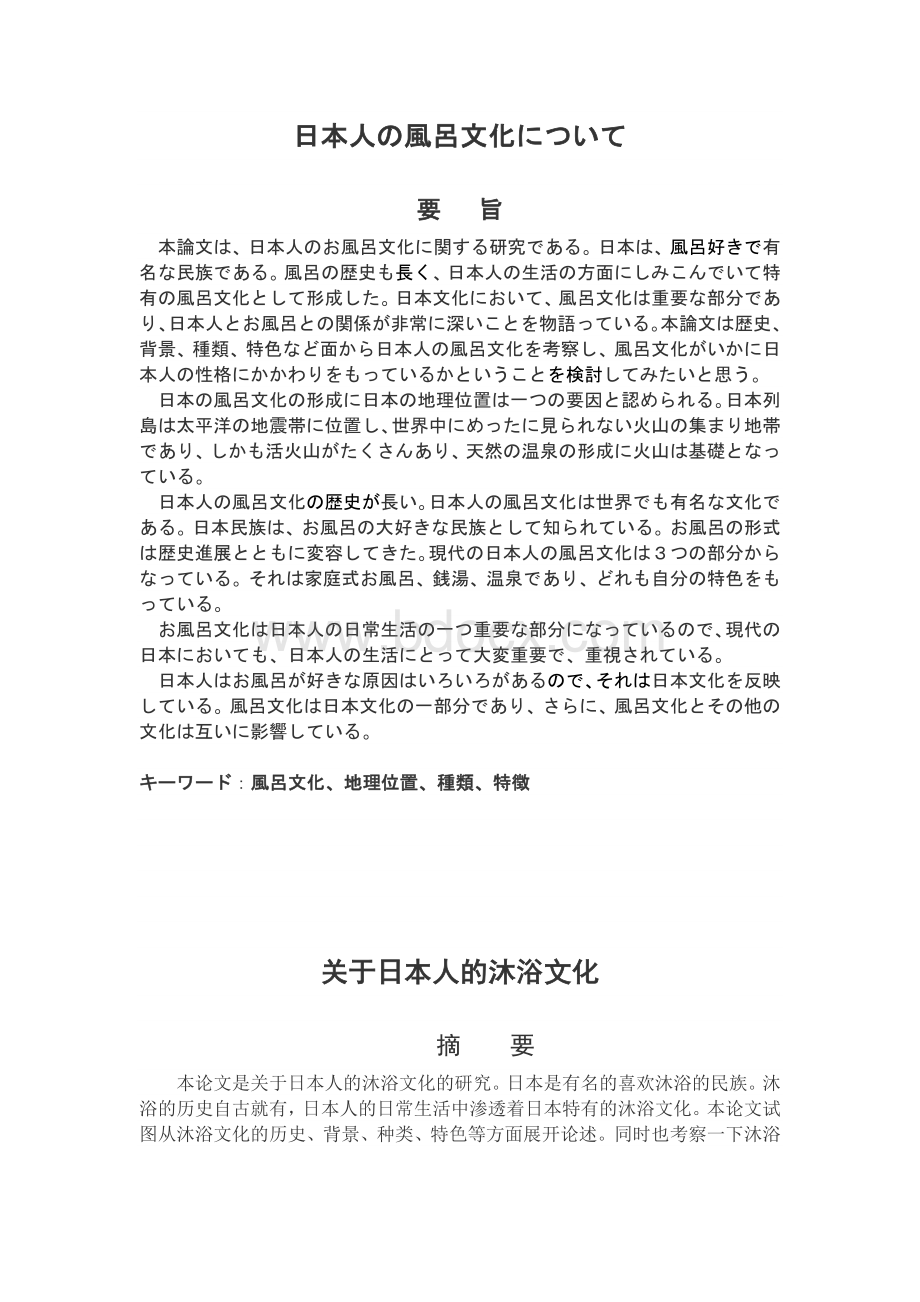
日本人の風呂文化について
要旨
本論文は、日本人のお風呂文化に関する研究である。
日本は、風呂好きで有名な民族である。
風呂の歴史も長く、日本人の生活の方面にしみこんでいて特有の風呂文化として形成した。
日本文化において、風呂文化は重要な部分であり、日本人とお風呂との関係が非常に深いことを物語っている。
本論文は歴史、背景、種類、特色など面から日本人の風呂文化を考察し、風呂文化がいかに日本人の性格にかかわりをもっているかということを検討してみたいと思う。
日本の風呂文化の形成に日本の地理位置は一つの要因と認められる。
日本列島は太平洋の地震帯に位置し、世界中にめったに見られない火山の集まり地帯であり、しかも活火山がたくさんあり、天然の温泉の形成に火山は基礎となっている。
日本人の風呂文化の歴史が長い。
日本人の風呂文化は世界でも有名な文化である。
日本民族は、お風呂の大好きな民族として知られている。
お風呂の形式は歴史進展とともに変容してきた。
現代の日本人の風呂文化は3つの部分からなっている。
それは家庭式お風呂、銭湯、温泉であり、どれも自分の特色をもっている。
お風呂文化は日本人の日常生活の一つ重要な部分になっているので、現代の日本においても、日本人の生活にとって大変重要で、重視されている。
日本人はお風呂が好きな原因はいろいろがあるので、それは日本文化を反映している。
風呂文化は日本文化の一部分であり、さらに、風呂文化とその他の文化は互いに影響している。
キーワード:
風呂文化、地理位置、種類、特徴
关于日本人的沐浴文化
摘要
本论文是关于日本人的沐浴文化的研究。
日本是有名的喜欢沐浴的民族。
沐浴的历史自古就有,日本人的日常生活中渗透着日本特有的沐浴文化。
本论文试图从沐浴文化的历史、背景、种类、特色等方面展开论述。
同时也考察一下沐浴文化对日本人性格的影响。
日本人与沐浴有着密不可分的关系,可以说,沐浴文化在日本的文化中占有很重要的地位。
日本的地理位置是日本沐浴文化形成的一个重要因素。
日本列岛位于太平洋的地震带,是世界少有的火山聚集地带,因此有非常多的活火山。
这是天然温泉形成的基础。
日本的沐浴文化有很长的历史,也是有日本特色的文化。
日本民族是热爱沐浴的民族。
沐浴的形式随着历史的变化而变化。
而沐浴文化经过长时间的演变,形成了现代的三种沐浴形式,即家庭式沐浴、公共浴室和温泉,每一种都有独有的特色。
日本的沐浴文化对于现代日本人的日常生活有着非常重要的作用,日本人也相当重视沐浴文化。
沐浴文化已经成为日本人日常生活的重要组成部分。
日本人喜欢沐浴的原因有很多。
这些原因能反射出日本的文化。
沐浴文化是日本文化的一部分,而且,它们之间能互相影响。
关键词:
沐浴文化,地理位置,种类,特点
目次
一、序論6
二、本論6
1風呂文化の形成の原因6
1.1地理位置による原因7
1.2気候による原因7
2風呂文化の歴史8
3 現代の風呂文化の種類と特色9
3.1家庭式お風呂9
3.2銭湯10
3.3 温泉10
3.3.1温泉の歴史11
3.3.2温泉の特色12
3.3.3温泉と日本人の生活12
4日本人が風呂が大好きの原因13
4.1日本人の独特な清潔意識13
4.2日本人の独特な美意識14
4.3日本人の独特な交流方式14
5中日の風呂文化の比較15
三、結論16
参考文献17
謝辞18
一、序論
日本語を四年間、勉強した。
私は、日本の文化についても少しわかるようになった。
日本の地理位置、日本の気候、日本人特有の清潔意識、審美意識だけでなく、日本文化の中において、風呂文化は重要な部分である。
それは、日本人とお風呂との関係が非常に深いからである。
日本文化のそれぞれの方面の間に密接な関係がある。
本論文はいくつかの方面の考察を通じて、日本人の風呂文化への理解を深めていきたい。
本研究は、日本人のお風呂文化の形成の原因と発展と種類などを考察したいと思う。
日本のお風呂文化の形成に日本の地理位置は一つの要因と認められる。
日本列島は太平洋の地震帯に位置し、世界中にめったに見られない火山の集まり地帯であり、しかも活火山がたくさんあるので、天然の温泉の形成に非常に有利な条件をもっている。
日本人のお風呂文化の歴史が長い。
長期にわたって、お風呂の形式も変わってきた。
現代の日本のお風呂は3種類に分けられている。
それは、家庭式お風呂、銭湯と温泉であり、どれも自分の特色がある。
日本人はすべてお風呂が大好きである。
これも日本文化の特色の一つである。
日本人はお風呂が好きの原因はいろいろがあるが、日本の地理位置、気候など、仏教文化も一つの要因と認められる。
そのほか、いろいろな原因がある。
したがって、お風呂文化は日本文化の重要な部分である。
しかも、日本人の日常生活においても不可欠な存在となっている。
日本人のお風呂文化はほかの文化と同じ、時代の移り変わりを経て、人間の豊かな文化を積んで、新しい文明を創造した。
だがら、日本人のお風呂文化は日本の民俗文化の重要な部分となっており、日本人の生活習慣の一面を反映している。
二、本論
1風呂文化の形成の原因
日本人の風呂文化の形成はさまざまな方面の原因が考えられるが、その中で、日本の地理環境と気候は重要な原因と認められる。
1.1地理位置による原因
今から数十万年前には、日本列島はアジア大陸の一部であった。
その後、太平洋の周りで火山活動が盛んになり、富士山やそのほかの山がたくさんできた。
日本は太平洋北西部の島国で、北海道、本州、四国、九州など四つ大島と何千もの小さい島がある。
日本は地震が多く、地震国として有名である。
地震の起こる原因には、火山の爆発によるものと、地殻の変動によるものとがあるが、日本列島が環太平洋火山帯にあるので、火山活動も活発で、地殻の変動も多く、地震も多いのである。
日本列島は太平洋の地震帯に位置し、世界中にめったに見られない火山の集まり地帯であり、しかも活火山がたくさんある。
日本にはいくつかの火山脈が走っているため、地形は変化に富んでいる。
また、日本の国土の約4分の3が山に覆われ、南部から北部にかけてたくさんの火山地がある。
一般的には日本に7つ火山地帯があると認められる。
日本の多くの火山の中で、約80の活火山がある。
例えば伊豆半島の三原山、長野県と群馬県の境目に位置する浅間山など、世界で約840の活火山があるが、日本はそのうちの10分の1を占めている。
北海道から東北・関東地方、さらに九州地方にかけて火山が数多く分布されている。
火山の中には今でも噴火を続ける阿蘇山、三原山、浅間山などの火山がある。
また、火山活動によってできた湖や温泉も沢山あるので、保養地や観光地として利用されている。
活火山は天然の温泉の形成に火山は基礎となっている。
だから、日本の風呂文化の形成に日本の地理環境は一つの要因と言えるだろう。
1.2気候による原因
日本人はお風呂が大好きだと言われているが、その原因、日本の気候はもう一つの重要な原因のだと思う。
海に囲まれた島国であるため、全般に気温変化が穏やかで、降水量が多い海洋性気候を呈する。
日本はアジア大陸の東にあって、季節風帯にあるうえ、周囲が海に囲まれているので、夏も冬も季節風が雨や雪を降らせる。
中緯度の大陸東岸に位置するため、季節風の影響を強く受ける。
このため日本の気候は多雨多湿である。
日本の夏は、暑くて湿度も高い。
汗で体がべとべとしている時や雨に降られてぬれた時など、お風呂に入れば、さっぱりして気持ちがよくなるだろう。
また、寒い冬には、熱いお湯にしばらくつかっていれば、体が暖まってくる。
日本は中緯度地帯に位置するため、全体的に見ると気温が温暖で、四季の区別がはっきりしている。
気温が温暖なこと、地域によって気温の差が大きいこと、降雨量が多いこと、四季の移り変わりがはっきりしていることなどが日本の気候の主な特色である。
また、国土が細長い形になっているので、南北で気温に大きな違いがある。
だから、日本人は身体を暖かくするためによく温泉を利用するのだろう。
2 風呂文化の歴史
火山国である日本の各地に温泉が湧き出るところがたくさんある。
また、お風呂の歴史は、6世紀に仏教の伝来とともに、中国から伝わってきたといわれている。
仏教で、お風呂に入ることは「七病を除き、七福が得られる」といわれていることから、お風呂に入ることは健康に良いとされていた。
それから、お寺では「体を洗い清める」という大切な業の一つとして浴室が備えられるようになり、浴室のない庶民にも入浴を施したことから、お風呂に入るという習慣が始まったと言われている。
お風呂の習慣は世界のどこにもあるが、日本には仏教とともに中国から伝わってきたといわれる。
日本人の風呂文化は長い歴史がある。
日本の『古事記』や『日本書記』などの歴史文献に天皇が温泉に入ることに関する内容がある。
その内容は日本人は昔から温泉の利用を知っていると物語っている。
日本の風呂は銭湯、水浴、サウナ、シャワーなどさまざまな言い方や種類がある。
現代では、湯に浸かることを風呂に入るというが、歴史上では「湯につかること」と「風呂に入ること」とは全く別のことである。
現代の日本のお風呂の形式は三種類に分けられている。
それは、家庭式お風呂、銭湯と温泉である。
温泉の歴史はそれより長い。
日本人の入浴文化は、狩猟時代までさかのぼることができる。
狩猟時代の日本人は川や湖、海で浴びる。
平安時代、温泉を利用するようになった。
平安時代にバケツが出現した。
バケツの出現は、平安時代の入浴文化に重要な影響がある。
13の世紀鎌倉時代と14世紀の室町時代から、入浴は「風呂」と呼ばれ、入浴のは徐々に貴族から庶民に普及するようになった。
時代によって、広く流行するお風呂の形式も違っている。
江戸時代の銭湯文化は今でも有名である。
17世紀の江戸時代、実用性と娯楽性が一体に集中する「銭湯」文化は大きいな発展を遂げた。
明治維新の頃、日本は西洋の先進的な文化の導入が始まった。
日本政府が混浴を禁止するようになった。
同時に、洋風の浴室が現れ始めた。
日本には「湯あみ」という言葉があるが、「湯」と言う概念があるので、「湯」の概念の無い民族では「水浴」になる。
「水浴」は鳥類や哺乳類の動物一般での本能的行為であろう。
生命維持の一部である保健衛生という観点から埋め込まれた本能だったであろうが、知的能力の高い人類は、様々な理屈をつけて、入浴を生活の中の習慣にしたのである。
3 現代の風呂文化の種類と特色
日本の現代の風呂文化では主に三つの部分からできている。
それは家庭式お風呂、銭湯と温泉であり、それぞれ自分の特色がある。
3.1家庭式お風呂
家庭式お風呂は家でお風呂に入ることである。
日本では、中国人にとって、一番不思議なのは「父と娘が一緒にお風呂に入る」ということであるが、このような場面は日本のドラマにもよく出てくるそうである。
お父さんと娘が一緒にお風呂に入って、歌を歌ったりしている。
日本で父と娘が一緒にお風呂に入ることはとてもありふれていることである。
一般の家族では、家族皆が同じ湯を使うのが習慣である。
日本を訪れた外国人がその習慣を知らないので、入浴後風呂の栓を抜いてしまうことが多いようである。
順番は明確に決まっていないが、男性優先というのは伝統的なやり方である。
家庭式お風呂は世界のどこにもあるが、日本の家庭式お風呂は自分の特色がある。
男性優先など、父と娘が一緒にお風呂に入るなど、これは日本特有の家庭式お風呂である。
親と子供が一緒に裸でお風呂に入ることを通じて