日语论文格式.docx
《日语论文格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《日语论文格式.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
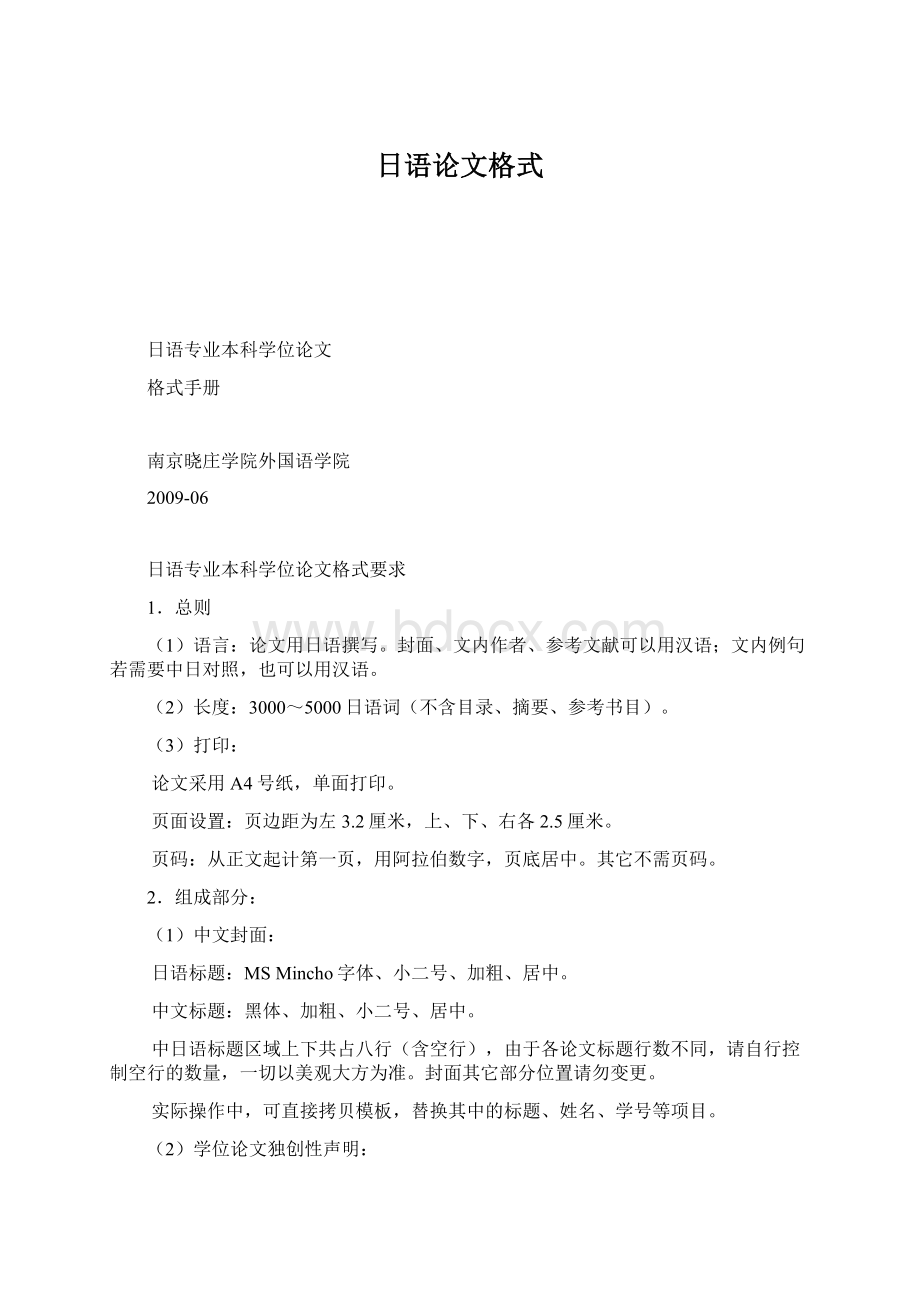
日语论文格式
日语专业本科学位论文
格式手册
南京晓庄学院外国语学院
2009-06
日语专业本科学位论文格式要求
1.总则
(1)语言:
论文用日语撰写。
封面、文内作者、参考文献可以用汉语;文内例句若需要中日对照,也可以用汉语。
(2)长度:
3000~5000日语词(不含目录、摘要、参考书目)。
(3)打印:
论文采用A4号纸,单面打印。
页面设置:
页边距为左3.2厘米,上、下、右各2.5厘米。
页码:
从正文起计第一页,用阿拉伯数字,页底居中。
其它不需页码。
2.组成部分:
(1)中文封面:
日语标题:
MSMincho字体、小二号、加粗、居中。
中文标题:
黑体、加粗、小二号、居中。
中日语标题区域上下共占八行(含空行),由于各论文标题行数不同,请自行控制空行的数量,一切以美观大方为准。
封面其它部分位置请勿变更。
实际操作中,可直接拷贝模板,替换其中的标题、姓名、学号等项目。
(2)学位论文独创性声明:
标题:
小二号宋体加粗
内容四号宋体
(3)中日文摘要与关键词
标题行:
MSMincho(汉语宋体),三号、加粗、居中。
正文:
MSMincho(汉语宋体),小四号。
整页均为1.5倍行距。
“摘要”与“关键词”加粗。
中文摘要200~300字,关键词3~5个。
日汉摘要、关键词内容要对应。
(4)目录页:
“目次”标题行:
MSMincho,三号、加粗、居中。
正文:
MSMincho,小四号、左顶格。
次层次比上一层次退后两空格。
整页均为1.5倍行距;标题空行处理请参见模板。
(5)正文内的日语大标题:
大标题前空两行,后空一行,均为五号空行。
大标题格式:
MSMincho,三号、加粗、居中。
(6)正文内容:
结构层次:
正文分为章、节、小节。
章的编号:
1.,2.,3.,…;节的编号:
1.1,1.2…,2.1,2.2…;小节的编号:
1.1.1,1.1.2…。
若小节以下还需分出层次,采用(i),(ii),(iii)标识。
章与章之间、节与节之间空一行,但小节及小节以下层次间不空行。
连续性标题也不空行。
小标题(章、节、小节):
左顶格、MSMincho、小四、加粗。
单独成行,无结尾标点。
大小写要求同论文正文大标题。
正文文字:
MSMincho、五号、行距固定值20磅。
(7)文献引用:
引用他人的原话,必须加引号,并在该内容后注明作者、日期和页码。
如果内容超过三行,采用段落引用的格式。
引用他人的观点,可以用阐释、概述的方法,并在该内容后注明作者和日期,页码可以不标注。
如果引用时,正文已经出现了作者,只需标出日期和页码。
(8)参考文献:
“参考文献”标题行:
MSMincho,三号、加粗、居中。
文献项目:
MSMincho(汉语宋体)、五号、单倍行距。
文献类型有专著、期刊、论文集、辞典、网络文献,详细说明参见模板。
顺序:
日文文献在前,中文文献在后。
日文按照作者假名顺序,中文按照作者汉语拼音顺序。
(9)謝辞:
“謝辞”行:
MSMincho,三号、加粗、居中。
正文:
MSMincho,小四号。
整页均为1.5倍行距。
III其它说明:
引文、夹注、表格等以模板中具体例子说明。
本手册对各类标题的字体、字号作了详尽说明,仅作资料备用,学生不必记忆。
在实际操作中,可直接使用WORD中的格式刷。
IV附录(论文模板)
分类号:
学校代码:
11460
学号:
06402112
南京晓庄学院
本科生学士学位论文
从日本枯山水庭园看日本人的审美观
日本の枯山水から見られる日本人の美意識
所在院(系):
外国语学院
学生:
方园
指导老师:
莫文水
研究起止日期:
2009年9月至2010年3月
二○一○年三月
学位论文独创性声明
本人郑重声明:
本论文是本人在导师指导下独立从事研究所取得的成果。
文中除以参引或注释形式标明出处者外,不含任何其他个人或机构已发表或未发表的著述或研究结果。
对本文的研究做出贡献的个人和机构,均已在“致谢”中加以说明。
本人完全了解,违反上述声明所引起的一切法律责任将由本人承担。
本人签名_______________
年月日
要旨
川端康成は日本では非常に有名な作家である。
彼の作品の中で、『雪国』は人々から高い評価を受け、昭和文学の代表作品と川端の作品群の中の最高傑作だと言われた。
本稿では『雪国』における島村が三回にわたって雪国に行った順序に沿い、主人公-駒子の生理、性格や運命の変化を分析することによって、小説の趣旨を導き出そうと思う。
『雪国』における駒子はとても清潔な雪国芸者であった。
彼女は東京でお酌をしていたうちに受け出され、ゆくすえ日本踊の師匠として身を立てさせてもらうつもりでいたところ、一年半で旦那に死なれた。
しかたがなく、彼女は雪国に帰り、三味線と踊を習い、時に大きな宴会に行き、生計をたてていた。
境遇はつらいが、彼女は生活と愛情に対する希望を失わなかった。
駒子は生活の不幸に耐え、始終希望を持ち、きれいに暮らして純真な愛情を求めようと努力していた。
しかし、筆者にして見れば、川端は駒子の清潔さ、純真さや生活と愛情に対する真面目さと努力を通して、徒労になるかもしれないが、どんなにつらくても諦めなく努力すれば、人生は有意義になり、美しくなるという生活態度、つまり生命の本質を表した。
キーワード:
清纯;希望;努力;徒労;生活態度
摘要
川端康成是日本非常有名的作家。
在他的作品之中,《雪国》受到了很高的评价,被称为大正文学的代表作品和川端作品群中的最高杰作。
《雪国》的主人公驹子在东京做陪酒女侍时被人赎出,主人打算安排她以后做个日本舞蹈的老师,不幸的是一年半后主人死了。
驹子无可奈何地回到雪国,学习三弦琴和舞蹈,有时候到宴会上陪酒以维持生计。
后来沦为艺妓。
虽然境遇很不好但她从来没有对生活失去希望。
她始终忍受着生活的不幸,为了生活地更加洁净一些,为了追求纯真的爱情而努力着。
因为她的追求和努力最后都变成了美丽的徒劳,所以很多人认为川端康成通过写驹子的悲剧来表达世界上的一切东西都是虚无的,人的努力都是徒劳这种思想。
但是笔者认为他是通过描写驹子的洁净、纯真以及对生活和爱情的努力和认真来表达这样一种思想:
虽然努力可能会变成徒劳,但是只有不论多苦都不放弃,锲而不舍地努力,人生才会有意义,才会变的美丽。
关键词:
清洁;希望;努力;徒劳;生活态度
目次
1.はじめに.......................................................................................................1
1.1文化と茶文化の定義について
1.2研究の目的と意義
2.先行研究と問題提起.....................................................................................3
2.1先行研究
2.2問題提起
3.研究方法と資料収集.....................................................................................5
3.1資料収集
3.2研究方法
4.茶の起源と茶文化の発展..............................................................................7
4.1茶の起源
4.2茶文化の発展
5.日本の茶道
5.1唐代と谴唐使
5.2宋代と栄西
5.3明代闘茶の輸入と茶道の普及
6.結論......................................................................................................................9
参考文献..................................................................................................................10
謝辞...........................................................................................................................11
日本の枯山水から見られる日本人の美意識
1.はじめに
文化は人間の生活様式の全体である。
人類がみずからの手で築き上げてきた有形・無形の成果の総体である。
それぞれの民族・地域・社会に固有の文化があり、学習によって伝習されるとともに、相互の交流によって発展してきた。
そのうち、特に、哲学・芸術・科学・宗教などの精神的活動、およびその所産である(倉沢行洋,1990)。
文化は人類によって創造するとともに人類と社会の発展を進んでいる。
茶文化の定義について先学の大家たちはそれぞれ独自な定義を下しているが、その中に代表的な論述をまとめて、次のようになる。
茶文化は茶を担体として諸般の文化を伝え、茶と文化有機融和で、一定の時期の物質文明と精神文明を含んで体現することである。
“茶道は茶文化を直接に表現するの形式の一つである。
今の茶道は茶の湯によって精神を修養し礼法を究める道である”(任小明,1995:
34—35)。
鎌倉時代の禅寺での喫茶の儀礼を起源として、室町時代の村田珠光に始まり、武野紹鴎を経て千利休が大成、侘茶として広まった。
利休後は表千家・裏千家・武者小路千家の三千家に分かれ、ほかに多くの流派がある。
2.先行研究と問題提起
2.1先行研究
中国は茶の木を最も早く発見し、利用した国であり、お茶の祖国とも言われている。
文字の記載が示しているように、中国の人たちの祖先は3000余年前に茶の木を栽培し、利用するようになった。
しかし、いかなる種の起源と同じように、お茶の起源と存在は必然的に人類が茶の木を発見、それを利用する前からあったことであり、長い歳月を経て、発見、利用されるようになったのである。
人類がお茶を利用するようになった経験は、代々伝えられることによって、一部の地域からだんだんと他の地域へ広がっていった。
お茶は中国から日本へ、6世紀に伝えられた。
そして、9世紀に上流階級の間で、お茶が、一般的だったとされていた。
お茶は日本の伝統と仏教のことに結びついて、日本の茶道が創造された。
日本の生活文化と深い関わりを持つ、独自の様式がもっている。
茶道は、中国で生まれ日本で花開き実を結んだ、優れた生活文化である。
茶道の語が文献に初めて現れるのは唐代であるが、すでに唐代に於いて、茶道は単なる飲茶習俗の域から脱した高度な精神文化であった。
唐の時代、陸羽の『茶経』がその事を輝かしく証明している。
2.2問題提起
茶道の本になっている喫茶は、日常茶飯事という言葉がいみじくも示しているように、日常生活に中で繰り返される、ごくありふれた営みである。
そのありふれた営みを媒介として成立した茶道は、超俗のままで日常生活に密着した文化である。
それには哲学、宗教、美学、建築、工芸、料理、礼法などを含んでおり、実に総合性の文化芸術活動といっても過言ではない。
茶道とは、物質的な享受ばかりではなく、茶会を通して、茶礼を勉強し、品性を陶冶し、審美観と道徳観念を養成することができる。
この十数年茶道についての研究は盛行している、茶道だけを研究するのは多いが、日中両国の間の関係を含めて、日中交流をの歴史の流れの中で茶道を置いて研究することは少ないだ。
茶道の精神は広くて深い、内容は広範で、形式は多様である。
今まで茶道についての定義がいろいろあるけど、違い角度で見ると結論がちがう。
小論では、茶の日本での成長発展の過程を研究しながら、茶文化の日本へ伝えると成長の歴史、茶道大家の背景及び茶道の精神本質のあらわしなどの方面から中国は日本茶文化への影響について考えたい。
3.研究方法と資料収集
本研究は、先生方からのご指導と関係者の協力の上、さらに図書館、本屋とインターネットを利用し、茶文化,茶道等についての資料を集める。
茶道の歴史、人物、発展に関する資料や論文を検索し、その正しさを確認した上で採用する。
いろいろな茶文化についての文献を読んで茶文化についての資料を収集して、自分の目的によってその資料、観点、結論を選択的に採用する。
その資料に基づいて、茶文化の起源、発展、伝えの歴史を見つけて、日中両国茶文化についての交流、日本茶道は中国の伝統文化とのかかわりなどを研究したい。
さらに、茶文化の社会意義について探求したい。
茶道は中国から日本へ伝えられ、日本伝統文化の代表として、中国と日本両国の文化の特徴をもっている。
だから、茶道は日中交流の結晶や証明とも言われている。
今の日中関係は時々困境に陥っている。
中日両国の国情は異なり、異なる見解があるのは当たり前だとされている。
しかし、交流が足りないのも一つの重要な原因である。
日本の文化を理解することができなければ日本語を勉強するや日中交流の時もうまく行くはずがないであろう。
茶道について研究することによって、日本との文化理解を促進することに大きな意味を持っていると思う。
「茶は養生の仙薬なり。
延齢の妙術なり」栄西はそう述べていた。
茶を飲むと心神を爽快になって心臓をととのえ、万病を除くことができるという意味である。
これは生理的茶の効用である。
日常生活の中では、いろいろなものに惑わされたり、他のものに合わせて、自分を曲げている。
そして、そこでは自分を守るためにいろいろな余分な着物をどんどん重ね着してしまう。
茶道と言うものによってそのような無駄なものをすべて捨てて、本当に素の自分に戻る。
今の物質化世界には、競争が激烈になり、人心はそわそわしていて、心理は衡を失うことが容易になり、人脈は緊張に赴いた。
茶道の精神「和、敬、清、寂」などは今の世界に必要なものがつめられている。
だから茶道を提唱して、もっとも調和な社会を築くべきである。
今の世界で、茶道の意義を探求したい。
4.茶の起源と茶道の発展
4.1茶の起源
茶樹の起源に関しては近年科学的な研究の進歩から、大体その起源となった土地は割り出されている。
以前は茶樹の起源に関してはアッサム起源説が有力だった時期もあるようだが、現在ではほぼ中国をその発祥の地とすることにほぼ異論はないようである。
そういった中で橋本実氏はおおよそ茶樹の起源の中心地を雲南・四川に特定している。
(橋本実著『茶の起源を探る』淡交社)
中国は茶の木の原産地であるが、しかし、中国のこの面における人類に対する貢献は、主に最も早くお茶という植物を発見し、それを利用し、それを中国、アジア及び全世界で輝く独特な茶の文化に発展させたことにある。
中国は茶の呼称、お茶についての知識、茶の木の栽培、加工技術を世界に伝えたのであり、世界各国の茶は、直接あるいは間接に、中国の茶とつながりがある。
4.2茶文化の発展
三国以前茶文化は啓蒙する。
茶は物質形式として他の人文科学にしみ込んで、それで茶文化を形成することが出現していた。
晋代、南北朝茶文化の萌芽。
文士は飲茶ことが勃興につれて、茶に関連した詩詞歌賦も多く出て、茶はすでに一般的形態とした。
唐代の茶文化の形成。
780年陸羽は「茶経」を著したことは、唐代の茶文化形成のシンボルである。
それは茶の自然と人文科学の二重性を含めて、飲茶芸術を研究して、儒、道、仏を飲茶中に入って、中国茶道精神を創造していた。
唐代の茶文化の成形は禅の勃興と関連している、寺院は飲茶を提唱、寺周囲に茶の木を植え、茶の礼を制定して、茶の堂を設けて、茶の端を選んで、専ら茶の活動を行う。
宋代茶文化の栄え。
宋代の茶には大きい発展がすでにあって、茶文化の発展を推進して、文士中出に専門飲茶社会団体を顕わしている(高旭晖、刘桂華,2003:
218)。
役人組成した「スープ社」が、仏教徒の「幹人社」など。
宋太祖は特にちゃを好んで、宮廷に茶の機関を設立する。
茶は貴重品として国外使節に与賜う。
つきましては下層社会、茶文化はさらに活発で、民間の斗の茶の風は起きて、お茶を煮る、採集、加工などいろいろな変化が起きた。
当時、唐代の団茶に成り代わって、碾茶(ひきちゃ)あるいは挽茶(ひきちゃ)と呼ばれた抹茶が主流となっており、匙でかき混ぜたり、茶筅やササラ状の竺副師という道具などで点てて飲んでいる。
時代の変遷につれて、大陸茶文化の新しい形式は次第に日本茶文化に連動していた。
日本茶文化の発展は中国大陸茶文化の発展によって、発展してきたといっても過言でもない。
日本茶道史の第一時期には、現在の茶道の形式をとっていなかった。
喫茶はただ天皇、貴族、高級僧侶などの上層社会が唐風先進文化を模倣した風雅的なことにすぎない。
第二時期の初期に入り、寺院茶、書院茶、闘茶を経て、茶文化の内容はだんだん豊富になってきた。
中国の茶道の栄えの影響によって、その上に、日本芸道成立の影響を受けて、日本茶道の草創期を完成した。
5.儒教、道教、仏教と茶道
茶道思想は儒学、道教、仏教など諸家精華を融合する。
「一生墨客として、幾世は茶の仙」と述べるの陸羽は儒学、道教、仏教を受け取って、唐代文化の特色とを結びついて、茶文化の基礎を定め、茶道精神を創造する。
「和敬清寂」お茶の精神をあらわす禅語である。
千利休が唱えたといわれる。
「和」「敬」は主客相互の心得であり、「清」「寂」は茶庭や茶室に関連する心得である。
「和」は同士がお互いに仲良く協調し合うということ。
5.1道教と茶道
生の術は周囲の環境をいつも再調整しつづけるところに生まれる。
道家は浮き世をありのままに受け入れ、儒教徒や仏教徒と違って、この世の悲しみや苦しみの中に美を見いだそうとする。
老子は虚の内にのみ本質的なものが存在すると主張した。
例えば一個の部屋の実在性は、屋根や壁によって囲まれた何もない空間にこそあるので、屋根や壁にあるわけではない。
水差しの存在価値は、水を入れることのできる空間にあるのであって、水注しのデザインや材料にあるわけではない。
虚は全てを含むから万能といえる。
虚、つまり何もない空間のみで”運動”が可能になる。
自分を無にして人を自由に立ち入らせることのできるものは、どんな状況をも支配することになる。
それは、全体は常に部分を支配できるからである。
それと言うのは心や思想を育てるによって、自分解放と言う意味です。
茶道の理想はそれと同じである。
岡倉天心によると(『茶の本』から)、「それは本質的に不完全なものの崇拝であり、われわれが知っている人生というこの不可能なものの中に、何か可能なものをなし遂げようとする繊細な企てである。
」とのことである。
そして、茶道の底流は「禅」であり、その奥には道教(老荘思想)があるとのことである。
茶道の全ての理想は、人生のささいな出来事の中に大いなるものを認識するという禅の概念から来ている。
道家思想は茶道の審美的理想の基礎を築き、禅はそれを実際的なものとしたのである。
5.2儒教と茶道
鎌倉時代には儒教の一つである朱子学が日本に伝わり、主に禅僧の間で学ばれた。
これは、日本に入ってきた仏教は、すでに中国において、儒学や老荘思想、道教の影響をうけていたからである。
日本人は、鎌倉期には、儒教・仏教・神道を一体とみていたようだ。
やがて、室町時代の末期には、儒教は禅宗から独立しはじめていった。
しかし、本格的には、国家が安定期に向かった江戸期に広まっている。
江戸幕府は朱子学を官学と定め、各藩でも藩校が作られ、朱子学は盛んになった。
儒教が盛んになるにつれ、朱子学だけでなく、陽明学派や古学派、折衷学派などの流派も発生したり広まったりした。
資料によって武士道や茶道が儒教の大きな影響を受けていた。
儒家思想は中国諸家思想の綱領で、茶道思想の主体である。
儒家の思想は世界をえこひいきしなく取り扱う態度を要求して、これはちょうど茶の本性である。
儒家の“中庸”と“仁礼”を茶道を導入させて、飲茶のとき思想を交流して、調和雰囲気創造して、両方の友情を増進することを主張する。
飲茶の中で自己を調べて、自己反省して、自分と世界を客観的に認識する。
内省して、理解することを強めて、調和を促進して、友好を増強する。
6.結論
茶は中国で生まれ、中国で始めて飲用された。
茶文化は中国文明の発展につれて、啓蒙、形成、繁栄そして普及してくる。
奈良時代に遣唐使や留学僧らが日本へ持ち帰って、発展できた。
この時期には、唐代の文化は栄えているから、天皇、貴族、高級僧侶などの日本の上層社会が唐風先進文化を模倣した風雅的なものになった。
茶道は形式から見ると、中国の宋代形式が残っている、発展の過程から見ると、ずっと中国とかかわっている、精神から見ると、儒、道、禅といろいろな所が共通している。
時代の変遷につれて、大陸茶文化の新しい形式は次第に日本茶文化に連動していた。
茶文化の発展史は日中交流の歴史で、日本茶文化の発展は中国大陸茶文化の発展によって、発展してきたといっても過言でもない。
茶道は生まれから、ずっとその存在の社会の経済、政治特に文化に大きな影響をしている。
茶は人間の生理の必要を満足するほかに、人間の心理的な必要を満足することもできる。
茶道によって伝統的文化を発揚して、人脈を調整する、コミュニケーションを促進して、社会気風を浄化する、それに、国際交流を促進することができる。
だから、茶道を大力提唱することを期待する。
参考文献
[1]池田弧二郎.希望表明形式による意思表示[J].言藉生活,1959(4).【期刊】
[2]臼田甚五郎.のシンタクスと辞典[Z].昭和46年.【辞典】
[3]倉沢行洋.芸術の哲学[M].東方出版社,1990.【专著】
[4]久松真一.日本語能力試験の広場.http:
//momo.jpf.go.jp/jlpt/j/about.html【网络文献;若无作者,以文献标题首字母排序】
[5]益岡隆志.日本語文法の諸相[M].くろしお出版,2000.
[6]陈玉泉.日语中委婉语的语用方式概述[A].福建省外国语文学会2002年会论文集[C],2002.【论文集】
[7]高旭晖、刘桂華.茶文化学概论[M].合肥:
安徽美术出版社,2003.【两位作者】
[8]任小明.中日茶道的差异[J].南京晓庄学院学报,1995.
[9]周文武等.中国茶道[M].杭州:
浙江大学出版社,2003.【三位以上作者】
謝辞
本論文の結びにあたり、本研究を行うことにおいて、指導教官の王精誠先生から細かいご指導をいただき、誠に感謝いたします。
大変お世話にまりました。
また、日本語科の張長安先生や宮本先生からも貴重なご意見をいただきました。
ご指導、尽力をいただいて、感謝の意を表します。
またこの四年間に親切に教えてくださった日本語科の先生かたに心から感謝いたします。
どうもありがとうございました。