源氏物语 12 须磨.docx
《源氏物语 12 须磨.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《源氏物语 12 须磨.docx(39页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
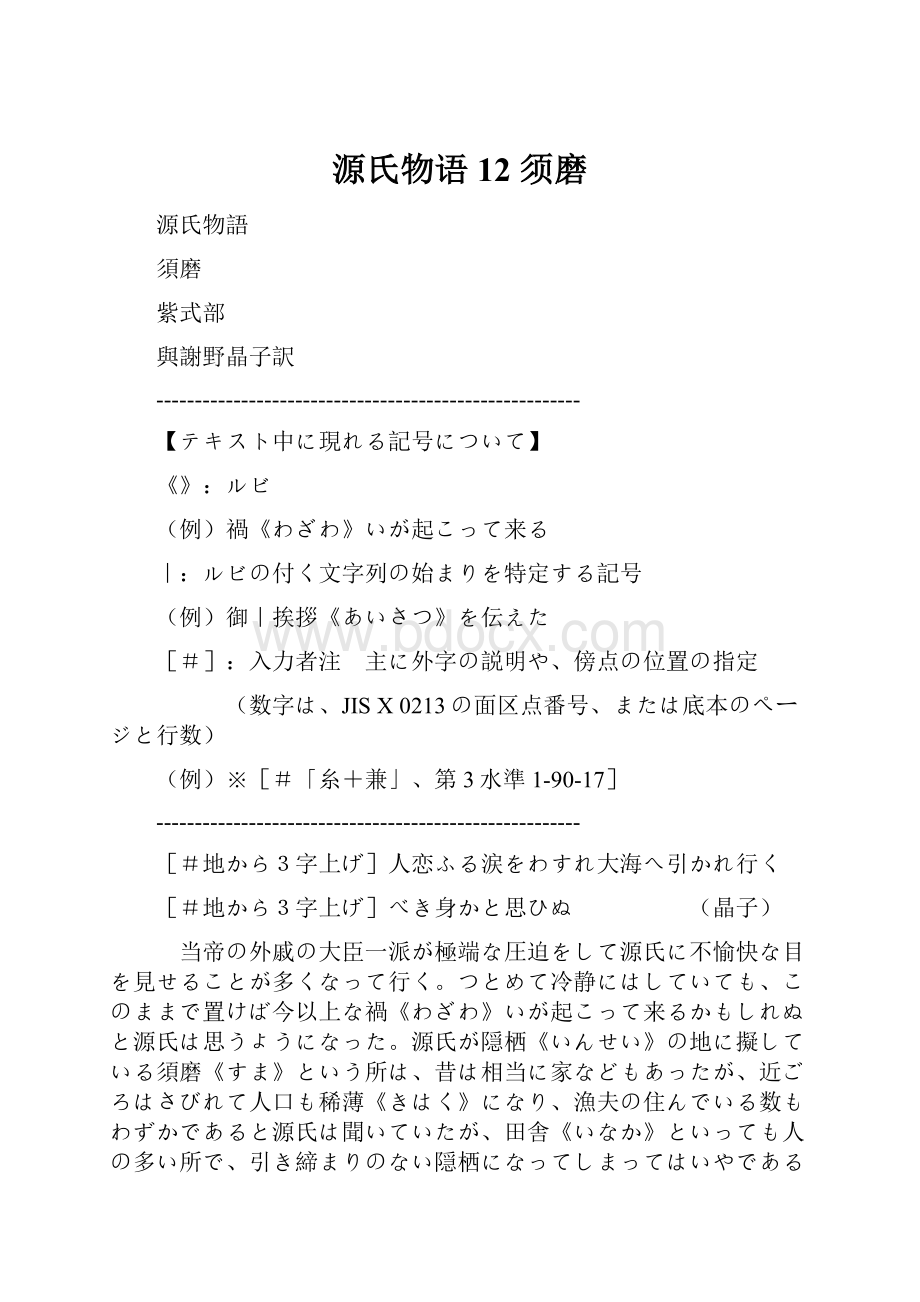
源氏物语12须磨
源氏物語
須磨
紫式部
與謝野晶子訳
-------------------------------------------------------
【テキスト中に現れる記号について】
《》:
ルビ
(例)禍《わざわ》いが起こって来る
|:
ルビの付く文字列の始まりを特定する記号
(例)御|挨拶《あいさつ》を伝えた
[#]:
入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定
(数字は、JISX0213の面区点番号、または底本のページと行数)
(例)※[#「糸+兼」、第3水準1-90-17]
-------------------------------------------------------
[#地から3字上げ]人恋ふる涙をわすれ大海へ引かれ行く
[#地から3字上げ]べき身かと思ひぬ (晶子)
当帝の外戚の大臣一派が極端な圧迫をして源氏に不愉快な目を見せることが多くなって行く。
つとめて冷静にはしていても、このままで置けば今以上な禍《わざわ》いが起こって来るかもしれぬと源氏は思うようになった。
源氏が隠栖《いんせい》の地に擬している須磨《すま》という所は、昔は相当に家などもあったが、近ごろはさびれて人口も稀薄《きはく》になり、漁夫の住んでいる数もわずかであると源氏は聞いていたが、田舎《いなか》といっても人の多い所で、引き締まりのない隠栖になってしまってはいやであるし、そうかといって、京にあまり遠くては、人には言えぬことではあるが夫人のことが気がかりでならぬであろうしと、煩悶《はんもん》した結果須磨へ行こうと決心した。
この際は源氏の心に上ってくる過去も未来も皆悲しかった。
いとわしく思った都も、いよいよ遠くへ離れて行こうとする時になっては、捨て去りがたい気のするものの多いことを源氏は感じていた。
その中でも若い夫人が、近づく別れを日々に悲しんでいる様子の哀れさは何にもまさっていたましかった。
この人とはどんなことがあっても再会を遂げようという覚悟はあっても、考えてみれば、一日二日の外泊をしていても恋しさに堪えられなかったし、女王《にょおう》もその間は同じように心細がっていたそんな間柄であるから、幾年と期間の定まった別居でもなし、無常の人世では、仮の別れが永久の別れになるやも計られないのであると、源氏は悲しくて、そっといっしょに伴って行こうという気持ちになることもあるのであるが、そうした寂しい須磨のような所に、海岸へ波の寄ってくるほかは、人の来訪することもない住居《すまい》に、この華麗な貴女《きじょ》と同棲《どうせい》していることは、あまりに不似合いなことではあるし、自身としても妻のいたましさに苦しまねばならぬであろうと源氏は思って、それはやめることにしたのを、夫人は、
「どんなひどい所だって、ごいっしょでさえあれば私はいい」
と言って、行きたい希望のこばまれるのを恨めしく思っていた。
花散里《はなちるさと》の君も、源氏の通って来ることは少なくても、一家の生活は全部源氏の保護があってできているのであるから、この変動の前に心をいためているのはもっともなことと言わねばならない。
源氏の心にたいした愛があったのではなくても、とにかく情人として時々通って来ていた所々では、人知れず心をいためている女も多数にあった。
入道の宮からも、またこんなことで自身の立場を不利に導く取り沙汰が作られるかもしれぬという遠慮を世間へあそばしながらの御慰問が始終源氏にあった。
昔の日にこの熱情が見せていただけたことであったならと源氏は思って、この方のために始終物思いをせねばならぬ運命が恨めしかった。
三月の二十幾日に京を立つことにしたのである。
世間へは何とも発表せずに、きわめて親密に思っている家司《けいし》七、八人だけを供にして、簡単な人数で出かけることにしていた。
恋人たちの所へは手紙だけを送って、ひそかに別れを告げた。
形式的なものでなくて、真情のこもったもので、いつまでも自分を忘れさすまいとした手紙を書いたのであったから、きっと文学的におもしろいものもあったに違いないが、その時分に筆者はこのいたましい出来事に頭を混乱させていて、それらのことを注意して聞いておかなかったのが残念である。
出発前二、三日のことである、源氏はそっと左大臣家へ行った。
簡単な網代車《あじろぐるま》で、女の乗っているようにして奥のほうへ寄っていることなども、近侍者には悲しい夢のようにばかり思われた。
昔使っていた住居《すまい》のほうは源氏の目に寂しく荒れているような気がした。
若君の乳母《めのと》たちとか、昔の夫人の侍女で今も残っている人たちとかが、源氏の来たのを珍しがって集まって来た。
今日の不幸な源氏を見て、人生の認識のまだ十分できていない若い女房なども皆泣く。
かわいい顔をした若君がふざけながら走って来た。
「長く見ないでいても父を忘れないのだね」
と言って、膝《ひざ》の上へ子をすわらせながらも源氏は悲しんでいた。
左大臣がこちらへ来て源氏に逢《あ》った。
「おひまな間に伺って、なんでもない昔の話ですがお目にかかってしたくてなりませんでしたものの、病気のために御奉公もしないで、官庁へ出ずにいて、私人としては暢気《のんき》に人の交際もすると言われるようでは、それももうどうでもいいのですが、今の社会はそんなことででもなんらかの危害が加えられますから恐《こわ》かったのでございます。
あなたの御失脚を拝見して、私は長生きをしているから、こんな情けない世の中も見るのだと悲しいのでございます。
末世です。
天地をさかさまにしてもありうることでない現象でございます。
何もかも私はいやになってしまいました」
としおれながら言う大臣であった。
「何事も皆前生の報いなのでしょうから、根本的にいえば自分の罪なのです。
私のように官位を剥奪《はくだつ》されるほどのことでなくても、勅勘《ちょっかん》の者は普通人と同じように生活していることはよろしくないとされるのはこの国ばかりのことでもありません。
私などのは遠くへ追放するという条項もあるのですから、このまま京におりましてはなおなんらかの処罰を受けることと思われます。
冤罪《えんざい》であるという自信を持って京に留まっていますことも朝廷へ済まない気がしますし、今以上の厳罰にあわない先に、自分から遠隔の地へ移ったほうがいいと思ったのです」
などと、こまごま源氏は語っていた。
大臣は昔の話をして、院がどれだけ源氏を愛しておいでになったかと、その例を引いて、涙をおさえる直衣《のうし》の袖《そで》を顔から離すことができないのである。
源氏も泣いていた。
若君が無心に祖父と父の間を歩いて、二人に甘えることを楽しんでいるのに心が打たれるふうである。
「亡《な》くなりました娘のことを、私は少しも忘れることができずに悲しんでおりましたが、今度の事によりまして、もしあれが生きておりましたなら、どんなに歎《なげ》くことであろうと、短命で死んで、この悪夢を見ずに済んだことではじめて慰めたのでございます。
小さい方が老祖父母の中に残っておいでになって、りっぱな父君に接近されることのない月日の長かろうと思われますことが私には何よりも最も悲しゅうございます。
昔の時代には真実罪を犯した者も、これほどの扱いは受けなかったものです。
宿命だと見るほかはありません。
外国の朝廷にもずいぶんありますように冤罪にお当たりになったのでございます。
しかし、それにしてもなんとか言い出す者があって、世間が騒ぎ出して、処罰はそれからのものですが、どうも訳がわかりません」
大臣はいろいろな意見を述べた。
三位《さんみ》中将も来て、酒が出たりなどして夜がふけたので源氏は泊まることにした。
女房たちをその座敷に集めて話し合うのであったが、源氏の隠れた恋人である中納言の君が、人には言えない悲しみを一人でしている様子を源氏は哀れに思えてならないのである。
皆が寝たあとに源氏は中納言を慰めてやろうとした。
源氏の泊まった理由はそこにあったのである。
翌朝は暗い間に源氏は帰ろうとした。
明け方の月が美しくて、いろいろな春の花の木が皆盛りを失って、少しの花が若葉の蔭《かげ》に咲き残った庭に、淡く霧がかかって、花を包んだ霞《かすみ》がぼうとその中を白くしている美は、秋の夜の美よりも身にしむことが深い。
隅《すみ》の欄干によりかかって、しばらく源氏は庭をながめていた。
中納言の君は見送ろうとして妻戸をあけてすわっていた。
「あなたとまた再会ができるかどうか。
むずかしい気のすることだ。
こんな運命になることを知らないで、逢えば逢うことのできたころにのんきでいたのが残念だ」
と源氏は言うのであったが、女は何も言わずに泣いているばかりである。
若君の乳母《めのと》の宰相の君が使いになって、大臣夫人の宮の御|挨拶《あいさつ》を伝えた。
「お目にかかってお話も伺いたかったのですが、悲しみが先だちまして、どうしようもございませんでしたうちに、もうこんなに早くお出かけになるそうです。
そうなさらないではならないことになっておりますことも何という悲しいことでございましょう。
哀れな人が眠りからさめますまでお待ちになりませんで」
聞いていて源氏は、泣きながら、
[#ここから2字下げ]
鳥部《とりべ》山燃えし煙もまがふやと海人《あま》の塩焼く浦見にぞ行く
[#ここで字下げ終わり]
これをお返事の詞《ことば》ともなく言っていた。
「夜明けにする別れはみなこんなに悲しいものだろうか。
あなた方は経験を持っていらっしゃるでしょう」
「どんな時にも別れは悲しゅうございますが、今朝《けさ》の悲しゅうございますことは何にも比較ができると思えません」
宰相の君の声は鼻声になっていて、言葉どおり深く悲しんでいるふうであった。
「ぜひお話ししたく存じますこともあるのでございますが、さてそれも申し上げられませんで煩悶《はんもん》をしております心をお察しください。
ただ今よく眠っております人に今朝また逢ってまいることは、私の旅の思い立ちを躊躇《ちゅうちょ》させることになるでございましょうから、冷酷であるでしょうがこのまままいります」
と源氏は宮へ御|挨拶《あいさつ》を返したのである。
帰って行く源氏の姿を女房たちは皆のぞいていた。
落ちようとする月が一段明るくなった光の中を、清艶《せいえん》な容姿で、物思いをしながら出て行く源氏を見ては、虎《とら》も狼《おおかみ》も泣かずにはいられないであろう。
ましてこの人たちは源氏の少年時代から侍していたのであるから、言いようもなくこの別れを悲しく思ったのである。
源氏の歌に対して宮のお返しになった歌は、
[#ここから2字下げ]
亡《な》き人の別れやいとど隔たらん煙となりし雲井ならでは
[#ここで字下げ終わり]
というのである。
今の悲しみに以前の死別の日の涙も添って流れる人たちばかりで、左大臣家は女のむせび泣きの声に満たされた。
源氏が二条の院へ帰って見ると、ここでも女房は宵《よい》からずっと歎《なげ》き明かしたふうで、所々にかたまって世の成り行きを悲しんでいた。
家職の詰め所を見ると、親しい侍臣は源氏について行くはずで、その用意と、家族たちとの別れを惜しむために各自が家のほうへ行っていてだれもいない。
家職以外の者も始終集まって来ていたものであるが、訪《たず》ねて来ることは官辺の目が恐ろしくてだれもできないのである。
これまで門前に多かった馬や車はもとより影もないのである。
人生とはこんなに寂しいものであったのだと源氏は思った。
食堂の大食卓なども使用する人数が少なくて、半分ほどは塵《ちり》を積もらせていた。
畳は所々裏向けにしてあった。
自分がいるうちにすでにこうである、まして去ってしまったあとの家はどんなに荒涼たるものになるだろうと源氏は思った。
西の対《たい》へ行くと、格子《こうし》を宵のままおろさせないで、物思いをする夫人が夜通し起きていたあとであったから、縁側の所々に寝ていた童女などが、この時刻にやっと皆起き出して、夜の姿のままで往来するのも趣のあることであったが、気の弱くなっている源氏はこんな時にも、何年かの留守《るす》の間にはこうした人たちも散り散りにほかへ移って行ってしまうだろうと、そんなはずのないことまでも想像されて心細くなるのであった。
源氏は夫人に、左大臣家を別れに訪《たず》ねて、夜がふけて一泊したことを言った。
「それをあなたはほかの事に疑って、くやしがっていませんでしたか。
もうわずかしかない私の京の時間だけは、せめてあなたといっしょにいたいと私は望んでいるのだけれど、いよいよ遠くへ行くことになると、ここにもかしこにも行っておかねばならない家が多いのですよ。
人間はだれがいつ死ぬかもしれませんから、恨めしいなどと思わせたままになっては悪いと思うのですよ」
「あなたのことがこうなった以外のくやしいことなどは私にない」
とだけ言っている夫人の様子にも、他のだれよりも深い悲しみの見えるのを、源氏はもっともであると思った。
父の親王は初めからこの女王《にょおう》に、手もとで育てておいでになる姫君ほどの深い愛を持っておいでにならなかったし、また現在では皇太后派をはばかって、よそよそしい態度をおとりになり、源氏の不幸も見舞いにおいでにならないのを、夫人は人聞きも恥ずかしいことであると思って、存在を知られないままでいたほうがかえってよかったとも悔やんでいた。
継母である宮の夫人が、ある人に、
「あの人が突然幸福な女になって出現したかと思うと、すぐにもうその夢は消えてしまうじゃないか。
お母《かあ》さん、お祖母《ばあ》さん、今度は良人《おっと》という順にだれにも短い縁よりない人らしい」
と言った言葉を、宮のお邸《やしき》の事情をよく知っている人があって話したので、女王は情けなく恨めしく思って、こちらからも音信をしない絶交状態であって、そのほかにはだれ一人たよりになる人を持たない孤独の女王であった。
「私がいつまでも現状に置かれるのだったら、どんなひどい侘《わ》び住居《ずまい》であってもあなたを迎えます。
今それを実行することは人聞きが穏やかでないから、私は遠慮してしないだけです。
勅勘の人というものは、明るい日月の下へ出ることも許されていませんからね。
のんきになっていては罪を重ねることになるのです。
私は犯した罪のないことは自信しているが、前生の因縁か何かでこんなことにされているのだから、まして愛妻といっしょに配所へ行ったりすることは例のないことだから、常識では考えることもできないようなことをする政府にまた私を迫害する口実を与えるようなものですからね」
などと源氏は語っていた。
昼に近いころまで源氏は寝室にいたが、そのうちに帥《そつ》の宮がおいでになり、三位中将も来邸した。
面会をするために源氏は着がえをするのであったが、
「私は無位の人間だから」
と言って、無地の直衣《のうし》にした。
それでかえって艶《えん》な姿になったようである。
鬢《びん》を掻《か》くために鏡台に向かった源氏は、痩《や》せの見える顔が我ながらきれいに思われた。
「ずいぶん衰えたものだ。
こんなに痩せているのが哀れですね」
と源氏が言うと、女王は目に涙を浮かべて鏡のほうを見た。
源氏の心は悲しみに暗くなるばかりである。
[#ここから2字下げ]
身はかくてさすらへぬとも君があたり去らぬ鏡のかげははなれじ
[#ここで字下げ終わり]
と源氏が言うと、
[#ここから2字下げ]
別れても影だにとまるものならば鏡を見てもなぐさめてまし
[#ここで字下げ終わり]
言うともなくこう言いながら、柱に隠されるようにして涙を紛らしている若紫の優雅な美は、なおだれよりもすぐれた恋人であると源氏にも認めさせた。
親王と三位中将は身にしむ話をして夕方帰った。
花散里《はなちるさと》が心細がって、今度のことが決まって以来始終手紙をよこすのも、源氏にはもっともなことと思われて、あの人ももう一度逢いに行ってやらねば恨めしく思うであろうという気がして、今夜もまたそこへ行くために家を出るのを、源氏は自身ながらも物足らず寂しく思われて、気が進まなかったために、ずっとふけてから来たのを、
「ここまでも別れにお歩きになる所の一つにしてお寄りくださいましたとは」
こんなことを言って喜んだ女御《にょご》のことなどは少し省略して置く。
この心細い女兄弟は源氏の同情によってわずかに生活の体面を保っているのであるから、今後はどうなって行くかというような不安が、寂しい家の中に漂っているように源氏は見た。
おぼろな月がさしてきて、広い池のあたり、木の多い築山《つきやま》のあたりが寂しく見渡された時、まして須磨の浦は寂しいであろうと源氏は思った。
西座敷にいる姫君は、出発の前二日になってはもう源氏の来訪は受けられないものと思って、気をめいらせていたのであったが、しめやかな月の光の中を、源氏がこちらへ歩いて来たのを知って、静かに膝行《いざ》って出た。
そしてそのまま二人は並んで月をながめながら語っているうちに明け方近い時になった。
「夜が短いのですね。
ただこんなふうにだけでもいっしょにいられることがもうないかもしれませんね。
私たちがまだこんないやな世の中の渦中《かちゅう》に巻き込まれないでいられたころを、なぜむだにばかりしたのでしょう。
過去にも未来にも例の少ないような不幸な男になるのを知らないで、あなたといっしょにいてよい時間をなぜこれまでにたくさん作らなかったのだろう」
恋の初めから今日までのことを源氏が言い出して、感傷的な話の尽きないのであるが、鶏ももうたびたび鳴いた。
源氏はやはり世間をはばかって、ここからも早暁に出て行かねばならないのである。
月がすっとはいってしまう時のような気がして女心は悲しかった。
月の光がちょうど花散里《はなちるさと》の袖の上にさしているのである。
「宿る月さへ濡《ぬ》るる顔なる」という歌のようであった。
[#ここから2字下げ]
月影の宿れる袖《そで》は狭くともとめてぞ見ばや飽かぬ光を
[#ここで字下げ終わり]
こう言って、花散里の悲しがっている様子があまりに哀れで、源氏のほうから慰めてやらねばならなかった。
[#ここから1字下げ]
「行きめぐりつひにすむべき月影のしばし曇らん空なながめそ
[#ここで字下げ終わり]
はかないことだ。
私は希望を持っているのだが、反対に涙が流れてきて心を暗くされますよ」
と源氏は言って、夜明け前の一時的に暗くなるころに帰って行った。
源氏はいよいよ旅の用意にかかった。
源氏に誠意を持って仕えて、現在の権勢に媚《こ》びることを思わない人たちを選んで、家司《けいし》として留守《るす》中の事務を扱う者をまず上から下まで定めた。
随行するのは特にまたその中から選ばれた至誠の士である。
隠栖《いんせい》の用に持って行くのは日々必要な物だけで、それも飾りけのない質素な物を選んだ。
それから書籍類、詩集などを入れた箱、そのほかには琴を一つだけ携えて行くことにした。
たくさんにある手道具や華奢《かしゃ》な工芸品は少しも持って行かない。
一平民の質素な隠栖者になろうとするのである。
源氏は今まで召し使っていた男女をはじめ、家のこと全部を西の対へ任せることにした。
私領の荘園、牧場、そのほか所有権のあるものの証券も皆夫人の手もとへ置いて行くのであった。
なおそのほかに物資の蓄蔵されてある幾つの倉庫、納殿《おさめどの》などのことも、信用する少納言の乳母《めのと》を上にして何人かの家司をそれにつけて、夫人の物としてある財産の管理上の事務を取らせることに計らったのである。
これまで東の対の女房として源氏に直接使われていた中の、中務《なかつかさ》、中将などという源氏の愛人らは、源氏の冷淡さに恨めしいところはあっても、接近して暮らすことに幸福を認めて満足していた人たちで、今後は何を楽しみに女房勤めができようと思ったのであるが、
「長生きができてまた京へ帰るかもしれない私の所にいたいと思う人は西の対で勤めているがいい」
と源氏は言って、上から下まですべての女房を西の対へ来させた。
そして女の生活に必要な絹布類を豊富に分けて与えた。
左大臣家にいる若君の乳母たちへも、また花散里へもそのことをした。
華美な物もあったが、何年間かに必要な実用的な物も多くそろえて贈ったのである。
源氏はまた途中の人目を気づかいながら尚侍《ないしのかみ》の所へも別れの手紙を送った。
[#ここから1字下げ]
あなたから何とも言ってくださらないのも道理なようには思えますが、いよいよ京を去る時になってみますと、悲しいと思われることも、恨めしさも強く感ぜられます。
[#ここから2字下げ]
逢瀬《あふせ》なき涙の川に沈みしや流るるみをの初めなりけん
[#ここから1字下げ]
こんなに人への執着が強くては仏様に救われる望みもありません。
[#ここで字下げ終わり]
間で盗み見されることがあやぶまれて細かには書けなかったのである。
手紙を読んだ尚侍は非常に悲しがった。
流れて出る涙はとめどもなかった。
[#ここから2字下げ]
涙川浮ぶ水沫《みなわ》も消えぬべし別れてのちの瀬をもまたずて
[#ここで字下げ終わり]
泣き泣き乱れ心で書いた、乱れ書きの字の美しいのを見ても、源氏の心は多く惹《ひ》かれて、この人と最後の会見をしないで自分は行かれるであろうかとも思ったが、いろいろなことが源氏を反省させた。
恋しい人の一族が源氏の排斥を企てたのであることを思って、またその人の立場の苦しさも推し量って、手紙を送る以上のことはしなかった。
出立の前夜に源氏は院のお墓へ謁するために北山へ向かった。
明け方にかけて月の出るころであったから、それまでの時間に源氏は入道の宮へお暇乞《いとまご》いに伺候した。
お居間の御簾《みす》の前に源氏の座が設けられて、宮御自身でお話しになるのであった。
宮は東宮のことを限りもなく不安に思召《おぼしめ》す御様子である。
聡明《そうめい》な男女が熱を内に包んで別れの言葉をかわしたのであるが、それには洗練された悲哀というようなものがあった。
昔に少しも変わっておいでにならないなつかしい美しい感じの受け取れる源氏は、過去の十数年にわたる思慕に対して、冷たい理智《りち》の一面よりお見せにならなかった恨みも言ってみたい気になるのであったが、今は尼であって、いっそう道義的になっておいでになる方にうとましいと思われまいとも考え、自分ながらもその口火を切ってしまえば、どこまで頭が混乱してしまうかわからない恐れもあって心をおさえた。
「こういたしました意外な罪に問われますことになりましても、私は良心に思い合わされることが一つございまして空恐ろしく存じます。
私はどうなりましても東宮が御無事に即位あそばせば私は満足いたします」
とだけ言った。
それは真実の告白であった。
宮も皆わかっておいでになることであったから源氏のこの言葉で大きな衝動をお受けになっただけで、何ともお返辞はあそばさなかった。
初恋人への怨恨《えんこん》、父性愛、別離の悲しみが一つになって泣く源氏の姿はあくまでも優雅であった。
「これから御陵へ参りますが、お言《こと》づてがございませんか」
と源氏は言ったが、宮のお返辞はしばらくなかった。
躊躇《ちゅうちょ》をしておいでになる御様子である。
[#ここから2字下げ]
見しは無く有るは悲しき世のはてを背《そむ》きしかひもなくなくぞ経《ふ》る
[#ここで字下げ終わり]
宮はお悲しみの実感が余って、歌としては完全なものがおできにならなかった。
[#ここから2字下げ]
別れしに悲しきことは尽きにしをまたもこの世の憂《う》さは勝《まさ》れる
[#ここで字下げ終わり]
これは源氏の作である。
やっと月が出たので、三条の宮を源氏は出て御陵へ行こうとした。
供はただ五、六人つれただけである。