日语能力试文档格式.docx
《日语能力试文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《日语能力试文档格式.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
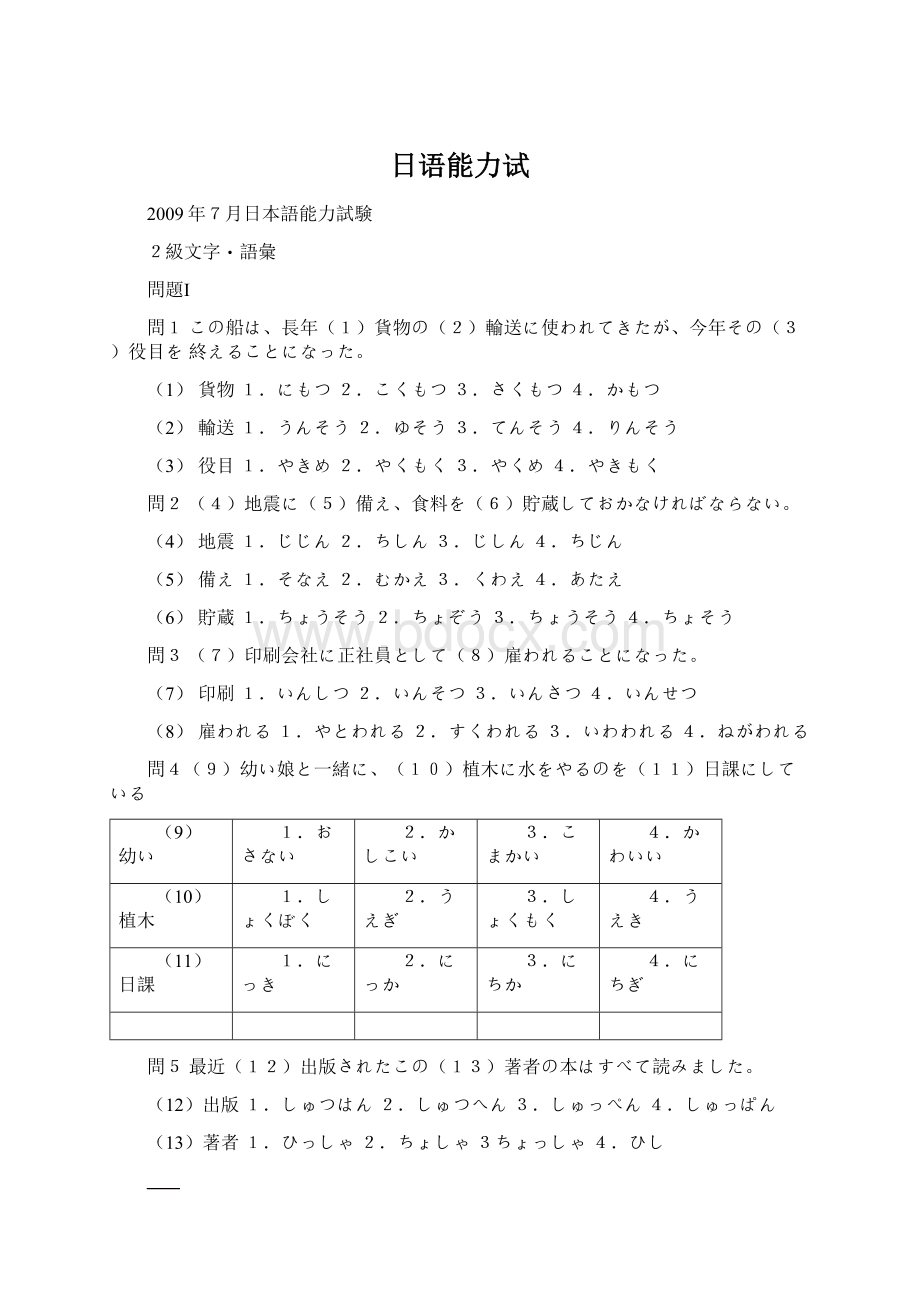
2.える
3.さぐる
4.けする
問7(16)順調に(17)回復しているので、もうすぐ(18)退院できるでしょう。
(16)順調
1.しゅんちょ
2.しゅんちょう
3.じゅんちょう
4.じゅんちょ
(17)回復
1.かいふう
2.かいほく
3.かいふく
4.かいほう
(18)退院
1.たんいん
2.だいいん
3.だんいん
4.たいいん
問8子供のころは、空を見上げて、(19)宇宙のことをいろいろ(20)想像したものです。
(19)宇宙1.うっちょう2.うちゅう3.うちょう4.うっちゅう
(20)想像1.そうぞう2.しょうぞう3.そうじょう4.しょうじょう
問題Ⅱ次の文の__をつけた言葉、どのような漢字を書きますか、その漢字を1.2.3.4から一つ選びなさい。
問1道で(21)さいふを(22)ひろった
(21)さいふ1.財袋2.材布3.財布4.材袋
(22)ひろった1.拾った2.捨った3.払った4.授った
問2このプリントに(23)あやまりがないか、(24)じむしょに行って(25)ちょくせつ聞いてみた。
(23)あやまり1.限り
2.誤り
3.残り
4.余り
(24)じむしょ1.治務所
2.事勤所
3.治勤所
4.事務所
(25)ちょくせつ1.直説
2.直接
3.触説
4.触接
問3(26)しょくよくがないようですね、どうしたんですか
(26)しょくよく1.食好2.食探3.食求4.食欲
問4(27)しんやに、階段から落ちて(28)こっせつしてしまった。
(27)しんや1.真夜
2.進夜
3.深夜
4.寝夜
(28)こっせつ1.肯切
2.骨切
3.肯切
4.骨折
問5今日は(29)すずしいが、日ざしが強かったので、(30)ぼうしをかぶって行った。
(29)すずしい1.凍しい2.涼しい3.寒しい4.寒しい
(30)ぼうし1.帽支2.冒子3.帽子4.冒支
問6この(31)そうちは、(32)じょうきの(33)いきおいが強くなると止まります。
(31)そうち1.装置2.総池3.装池4.総置
(32)じょうき1.乗気2.景気3.蒸気4.昇気
(33)いきおい1.慕い2.苦い3.勇い4.勢い
問7あの(34)いずみの水には、体によい(35)せいぶんが多く(36)ふくまれている。
(34)いずみ1.湖2.泉3.沓4.潮
(35)せいぶん1.成分2.清分3.正分4.性分
(36)ふくまれて1.含まれて2.組まれて3.込まれて4.包まれて
問8(37)ほうりつで(38)きんしされていることは、国によって(39)ことなります
(37)ほうりつ1.法立2.放立3.放律4.法律
(38)きんし1.停止2.禁止3.制止4.防止
(39)ことなります1.反なります2.違なります3.異なります4.差なります
問9今、彼は(40)ぼうえき関係の仕事をしている
(40)ぼうえき1.貿易2.賃易3.貿昜4.賃昜
問題Ⅲ次の文の____の部分に入れる最も適切なものを1.2.3.4から一つ選びなさい。
(41)練習でうまくできても、試合で実力をするのは難しいものだ。
1.発行2.発射3.発表4.発揮
(42)和室にふとんを____寝る。
1.かぶせる2.ひっぱって3.しいて4.のばして
(43)父は子供のころ____、食べるものに困っているそうだ
1.けわしくて2.あやしくて3.まずしくて4.こいして
(44)このガラスびんの____は2リットルです。
1.濃度2.容積3.水圧4.重量
(45)海____の道を通って家に帰った。
1.沿い2.建て3.向け4.付き
(46)A:
「部長、遅くなってすみません。
先日の会議のレポートができました。
B:
「それは______。
」
1.ごくろうさま2.えんりょなく
3.おまちどおさま4.おきのどくに
(47)緊張していたので、_____に話せなかった。
1.エチケット2.スタイル3.アクセント4.スムーズ
(48)夏になると、この山には_____と登山客がやってくる
1.別々2.続々3.点点4.着々
(49)あさまで寝ないで勉強していたので、授業中に眠くて何度も____が出た。
1.あくび2.せき3.しゃっくり4.くしゃみ
(50)長期にわたって____してきた二国間で、先週、初のトップ会談が行われた。
1.対照2.対策3.対面4.対立
問題Ⅳ次の51から55は、言葉の意味や使い方を説明したものです。
その説明に最も会う言葉を1234から一つ選びなさい。
(51)学習して完全にできるようになる
1.コーチする2.セットする3.マスターする4.プラスする
(52)気づかれないように何かをするようす
1.ぎっしり2.こっそり3.そっくり4.ぐっすり
(53)肉などが焼けすぎて黒くなる
1.こげる2.さびる3.とける4.くさる
(54)数えきれないほど多い。
1.整数2.複数3.無数4.偶数
(55)その状態を変えないで続ける。
1.普及する2.特定する3.保証する4.維持する
問題Ⅴ次の56から60の言葉の使い方として最も適切なものを1.2.3.4から一つ選びなさい。
(56)正直
1.かくさないで、正直な気持ちを話してほしい。
2.あの角を曲がって、10分ほど正直に行ってください。
3.この問題は難しいから、正直な答えが分かりません。
4.市場ではなく、農家から正直に野菜を買いたい。
(57)たしか
1.次の電車に間に合うかどうか、たしかをしてください。
2.引き受けた仕事は、たしかがんばりたい。
3.田中さんと初めてあったのは、たしか3年前のことだった。
4.人から聞いた話なので、たしかは分からない。
(58)展開
1.親友に悩みを展開して、気持ちが楽になった。
2.あの店のパンは、展開して2時間後に売り切れてしまう。
3.美術館へ古い絵画の展開を見にいった。
4.このドラマは話の展開が単純なので面白くない。
(59)散らかる
1.部屋が散らかっていたので、子供に片付けさせた。
2.この花は咲いてから四、五日で散らかる。
3.うっかりコップを倒してしまい、氷が散らかった。
4.もう夜も遅いから、散らかって明日まで集まろう。
(60)分解
1.ケーキを買ってきたから、みんな分解して食べましょう。
2.ラジオを分解して、音が出なくなった原因を調べてみた。
3.図書館の本は分野ごとに分解してならべてあります。
4.この虫は東部から南部にかけて広く分解している。
問題Ⅵ次の61から65の__をつけた言葉の意味に最も似ているものを1234から一つ選びなさい。
(61)父は、とても頭にきているようだ
1.驚いている2.悔やんでいる3.怒っている4.悲しんでいる
(62)その話は単なるうわさですから、信じてはいけません
1.むだな2.ただの3.うその4.ばかな
(63)この内容でよろしければ、サインをいただけますか。
1.許可2.署名3.承認4.注文
(64)先週の出張を中止したのはやむをえないことだった
1.しかたがない2.みっともない
3.もったいない4.とんでもない
(65)オリンピックが契機となり、スポーツがさかんになった。
1.ささえ2.すくい3.つながり4.きっかけ
2009年7月日语能力考真题(2级)
読解
人間には、二通りしかない。
まねをする人とまねをしない人。
まねをする人は、まねをじょうずにする人であるとは限らない。
できる、できないではない。
する人しない人の、二つなのである。
まねを「する人」というのは、こういう人だ。
たとえば、「犬がさ、腹を見せてさあ」と話す時に、腹を見せて、よろこぶ犬のようすを自分で楽しみながら(注1)実演する人のことである。
鳥でも、虫でもいい。
また、人のまねでもいい。
一つのようすを、顔や手、時に体全体をつかって、再現する人である。
「しない人」は、こんなものまねは絶対しない。
「する人」ができる、ちょっとしたことができない。
この違いはなんだろう。
「しない人」は、おそらく、こういう人だと思う。
人前でそんなことをしたら笑われてしまうから、しない。
(①)、(注2)プライドがあって、自分がそのときだけでも、自分以外のものになり変わること、化けることが、とてもはずかしいので、しない。
小さいときから、そういう「ふざけた」(注3)行為をすることを(注4)警戒していたので、しない。
あるいは、子供のときは「する人」だったが、社会的な地位が上がるうちに、「身体表現」とは(注5)無縁になり、そのうちに、②あんなことは、(注6)はしたないと思うようになったので、しない。
でも「しない人」のほとんどは、小さいときから「しない人」であると思う。
「しない人」は、その意味では③早くから「おとな」なのだ。
でも、ひとりのときに「おとな」であるのは、いいことだが、みんなでいるときに、あまりに「おとな」である人は、「おとな」とは言えないと思う。
もとろん、「する人」ばかりいても困るけれど、「する人」は「しない人」より心が自由であることはたしかだ。
いつまでも自分をにぎりしめていない人だから。
まわりを見渡すと、「しない人」が最近は多いように思う。
(注7)自己愛が進んでいる(注8)証拠であろう。
「ひとつ」しか自分の姿をもっていないためだろう。
話していることのなかみや考えはとてもやわらかいのに「しない人」がいる。
ほんとうは心がそれほどやわらかくないのだと思う。
これからも「しない人」はずっとしないだろう。
人が体をつかって、たとえちょっとしたことでも何かを表現するとき、その場の空気は明るくなる。
光が広がる。
それによって世界が、具体的に見え出す。
⑤自分の体は、自分だけのものではない。
もっとひろい場所に置かれたものである。
使いようによっては、みんなのものにもなるものなのである。
⑥それは自分にとっても、まわりの人にとっても、いいことであり、楽しいことなのである。
でも「しない人」はしない。
(慌川洋治『忘れられる過去』による)
(注1)実演する:
実際にやって見せる
(注2)プライドがある:
自分にほこりを感じている
(注3)行為:
行動、行い
(注4)警戒する:
ここでは、しないように気をつけている
(注5)~と無縁になる:
~をしなくなる
(注6)はしたない:
みっともない
(注7)自己愛:
ここでは、自分を大切にしようと思う気持ち
(注8)証拠:
本当であることを示すもの
問1本文中の、まねを「する人」はどんな人か。
(1)
1.どんなことでも上手にまねができる人。
2.犬や鳥や虫ほかの人のまねができる人。
3.喜ぶ犬のようすを見てそれを楽しむ人。
4.自分がみたようすを体を使って再現する人。
問2(①)に入る最も適切な言葉はどれか。
(2)
1.ただし
2.あるいは
3.ところが
4.したがって
問3②「あんなこと」とはどんなことか。
(3)
1.社会的な地位があがり、身体表現に消極的になること。
2.自分以外のものになり変わる、そのまねをすること。
3.ブランドがあり、ふざけた行為をすることを警戒すること。
4.おとなになってからも、ものまねをしないようにすること。
問4③「早くから『おとな』」である人はどんな人か。
(4)
1.子供なのに自分を握り締めていない人。
2.子供なのに体がおとなと同じぐらい大きい人。
3.子供のときから高い社会的な地位についている人。
4.子供の時から自分以外のものになろうとしない人。
問5④「『ひとつ』しか自分の姿をもっていない」とあるが、その「自分の姿」とはどのようのものか。
(5)
1.他人より自分の体のことを考える自分。
2.話の中身も考えもやわらかい自分。
3.常に理想的にふるまおうとする自分。
4.自由に楽しみながら身体表現をする自分。
問6「⑤自分の体は、自分だけのものではない」とはどういうことか。
(6)
1.自分の体は、親からもらったものならので大事にしなくてはいけない。
2.自分だけでなく、他の人々の自分のことを理解し大切にしてくれる。
3.まねをすることは、周りの人を楽しませ、より具体的に物事を伝える。
4.私たちは、他の人の役に立つように生きることを考えるべきである。
問7⑥「それ」とは何か。
(7)
1.身体表現はみんなのものでもあること。
2.身体表現が上手にできること。
3.身体表現をしなくてもかまわないこと。
4.身体表現をしなくても理解してもらえること。
問8本文の内容に合っているものはどれか。
(8)
1.楽しみながらまねをすることはいいことだ。
2.はずかしいのをがまんしてでもまねをすべきだ。
3.多くの人がまねができるようになってきている。
4.みんながまねをするようになり社会が明るくなった。
問題II
(1)①「まさか、そんな、冗談でしょ」と笑われそうだが、実は私はとても消極的で(注1)のろまな子供だった。
何をするにも人より時間がかかる。
(注2)学芸会では一番後列の端で小さくなっていた。
それが今や大勢の人前に立ち、一分一秒を争うテレビの世界で仕事をしているのだから、(注3)つくづく不思議に思う。
私が②変わっていくきっかけを作ってくれたのは、小学校5年生のときの担任の西村先生だった。
当時、食べるのも遅かった私は、(注4)給食の時間内に食事を終えることができず、いつも途中で片付けられてしまっていた。
それを見て先生は、「まだ残っているんだったら、食べていいよ」と声をかけてくださったのだ。
おかげで、私は(注5)5時限目が始まっても、給食を食べていていいことになった。
時には、それでも終わらなくて、6時限目も食べ続けていた。
人と同じでなくてもいい。
大切なのは、最後まで(注6)力を尽くすこと、と③そのとき学んだ。
百人の生徒がいれば、百の個性があり、百の(注7)ペースがある。
各人を比較しても仕方がない。
(注8)音痴でもいい、投げ出さずに心をこめて歌う。
算数ができなくても、自分の持てる力のなかで一生懸命やってみる。
その教えはクラス全員に伝わった。
私も少しずつ、のろまなりに自分のペースを作り、消極的ながらも一歩ずつ前に出ていくことをスタートさせたのだと思う。
子供の可能性というのは、限りないものだ。
得意な分野だけではなく、(注9)ひょっとすると苦手と思われる領域の内にも、大事に育ててあげれば大きく花開く芽のようなものが(注10)潜んでいるかもしれないことを、忘れてはいけない。
(注1)のろま:
動作や頭の働きがおそいようす、または、そのような人
(注2)学芸会:
劇や音楽などを発表する学校の行事
(注3)つくづく:
心から
(注4)給食:
学校で出される昼ごはん。
みんな一緒に教室で決まった時間内に食べる
(注5)5時限目:
5時間目。
給食の時間のすぐ後の授業
(注6)力を尽くす:
力いっぱいがんばる
(注7)ペース:
物事を進める速度
(注8)音痴:
歌が下手なこと、下手な人
(注9)ひょっとすると:
もしかしたら
(注10)潜む:
見えないが、確かに存在する
問1①「まさか、そんな、冗談でしょ」と言う人は、筆者をどんな人だと考えているのか。
(9)
1何でも積極的で、速いペースで物事をすませる人
2何でも消極的だが、速いペースで物事をすませる人
3何でも消極的で、遅いペースでしか物事ができない人
4何でも積極的だが、遅いペースでしか物事ができない人
問2②「変わっていく」とあるが、筆者はどのように変わっていったのか。
(10)
1苦手なことでも最後まで努力してうまくできるようになった。
2食べるのが速くなり忙しいテレビの世界に入れるようになった。
3給食で出る食事を時間内に食べることができるようになった。
4どんなことでもあきらめずに最後までがんばれるようになった。
問3③「そのとき」とあるが、いつか。
(11)
1西村先生が心配して声をかけてくださったとき
2西村先生の許可で給食を自分の速さで食べ終えたとき
3給食をほかの生徒とは別に一人で5時限目に食べたとき
4食べるのが遅すぎて給食を途中で片付けられてしまったとき
問4本文の内容に合っているものはどれか。
(12)
1子どもは大きくなるとともに変わらなければならない。
2子どもは食事をしたいときには食べるようにしたほうがいい。
3子どもは一人一人違っていてその違いを大切にしたほうがいい。
4子どもは消極的なら消極的なままでいても全く問題にならない。
(2)
「人の話を聞いてるのか!
!
あなたは上司(注1)などからこんなことを言われた経験はないだろうか?
じつは先日、とある喫茶店で、上司らしき人が部下らしき人に対して、(注2)このように怒鳴っている光景を目撃した。
その部下は終始(注3)うつむき加減で、(注4)一見すると(注5)神妙に上司の話を聞いているかのように思えた。
しかし、上司は怒った。
なぜなのか?
それは、上司が一生懸命いろいろなアドバイスをしているのに、部下が全くメモを取っていなかったからではないか。
(注6)通常、メモというのは自分のために取るものである。
大事なことをメモしておくことによって、記憶力を(注7)補完できるからだ。
しかし、メモの(注8)効用というのは、じつはこれだけではない。
私の経験からすると、聞き上手といわれる人は、必ず言っていいほど、人の話を聞くときはメモを取っている。
ときには、「すいません。
もう一度お願いします」とか、「それはどういう漢字を書くんですか?
」などと質問してまでメモを取るのである。
もちろん、これには先ほどの記憶力の補完という意味もあるが、じつは「あなたの話を真剣に聞いていますよ」という(注9)パフォーマンスの意味合いもあるのだ。
(堀内伸浩「ブレーク」読売新聞2007年10月29日付朝刊別冊による)
(注1)上司:
職場立場が上で、指示を与える人
(注2)目撃:
事件や出来事などを直接見ること
(注3)うつむき加減で:
少し下のほうを向いて
(注4)一見すると:
ちょっと見ると
(注5)神妙:
素直で心がけがいいようす
(注6)通常:
普通
(注7)補完:
補って完全なものにすること
(注8)効用:
役に立つはたらき
(注9)パフォーマンス:
ここでは、人の注意や関心を自分に向けるための行動
問1「このように怒鳴っている光景」とはどんな光景か。
(13)
1自分の話を真剣に聞いていないと思い、怒って大声を出している光景
2自分の話に対して何も言わないことに怒って、大声を出している光景
3許可なしに自分の話を聞いていると思い、怒って大声を出している光景
4他の人の話を聞いて自分の話を聞かないことに怒って、大声を出している光景
問2筆者の観察では、聞き上手とはどのような人か。
(14)
1相手の話を聞きながらメモを確かめる人
2相手の話をいつもメモを見ながら聞く人
3相手の話に対する質問をよくメモする人
4相手の話をいつもメモをしながら聞く人
問3筆者の考えでは、メモにはどんな効果があるか。
1相手を怒らせないようにするとともに、アドバイスを受け入れやすくする。
2相手を尊敬する気持ちを示すとともに、相手の信頼を得やすくする。
3後で思い出しやすくするとともに、相手に話を聞いていることを示す。
4後で質問しやすくするとともに、相手に話の内容を考えさせる。
問4筆者によれば、この「上司」はなぜ怒ったと考えられるか。
1「部下」が「上司」の話をただ聞いているだけだったから
2「部下」が「上司」の話を自分のためだけに聞いていたから
3「部下」が「上司」の話をメモを取りながら聞いていたから
4「部下」が「上司」の話を理解することができなかったから
(3)(次の文章は、遊漁船という船での仕事について説明した文章である。
)
その(注1)名称からもわかるように、遊漁船は利用者が「遊ぶ」目的で「漁」をするための船です。
「仕事」として「漁」をする漁船とは区別されています。
そして、釣りをするのが船の乗員である漁船と違い、遊漁船、乗員は(注2)一切釣りをしません。
釣り客に「釣り」を安全に楽しんでもらえるように釣り場に案内するのが、遊漁船業者の仕事なのです。
一口で言えば、「釣り」をテーマにした海上のサービス業と言えます。
そんな遊漁船業において、基本となる2つの重要なことがあります。
まず、(注3)大前提であるお客の安全を守ると言うことです。
日常生活を送っている。
陸地とは違い、不慣れな自然の海の上ではちょっとした(注4)軽ずみな行動によって(注5)危険にさらされることもあるからです。
次に、楽しんでもらうという点であげられるのが、お客に楽しく魚を釣ってもらうということです。
せっかく釣りにきているのですから、釣り客は少しでも多く魚を釣りたいと考えます。
中には、釣った魚を夕食のおかずにしようと、真剣に釣りをする客もいます。
このような釣り人を