日语城の崎にてにおける志贺直哉の死生観に.docx
《日语城の崎にてにおける志贺直哉の死生観に.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《日语城の崎にてにおける志贺直哉の死生観に.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
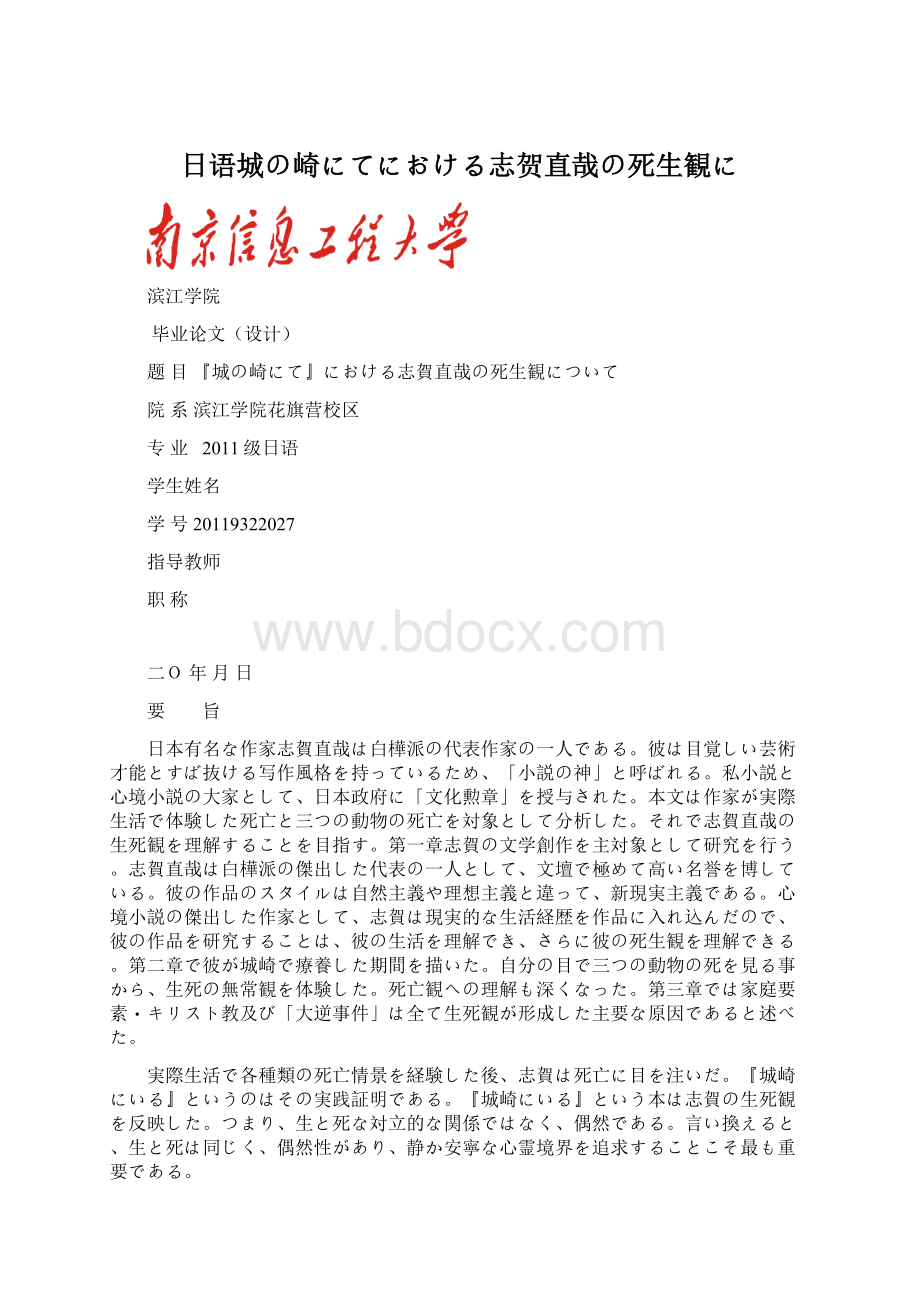
日语城の崎にてにおける志贺直哉の死生観に
滨江学院
毕业论文(设计)
题目『城の崎にて』における志賀直哉の死生観について
院系滨江学院花旗营校区
专业2011级日语
学生姓名
学号20119322027
指导教师
职称
二O年月日
要 旨
日本有名な作家志賀直哉は白樺派の代表作家の一人である。
彼は目覚しい芸術才能とすば抜ける写作風格を持っているため、「小説の神」と呼ばれる。
私小説と心境小説の大家として、日本政府に「文化勲章」を授与された。
本文は作家が実際生活で体験した死亡と三つの動物の死亡を対象として分析した。
それで志賀直哉の生死観を理解することを目指す。
第一章志賀の文学創作を主対象として研究を行う。
志賀直哉は白樺派の傑出した代表の一人として、文壇で極めて高い名誉を博している。
彼の作品のスタイルは自然主義や理想主義と違って、新現実主義である。
心境小説の傑出した作家として、志賀は現実的な生活経歴を作品に入れ込んだので、彼の作品を研究することは、彼の生活を理解でき、さらに彼の死生観を理解できる。
第二章で彼が城崎で療養した期間を描いた。
自分の目で三つの動物の死を見る事から、生死の無常観を体験した。
死亡観への理解も深くなった。
第三章では家庭要素・キリスト教及び「大逆事件」は全て生死観が形成した主要な原因であると述べた。
実際生活で各種類の死亡情景を経験した後、志賀は死亡に目を注いだ。
『城崎にいる』というのはその実践証明である。
『城崎にいる』という本は志賀の生死観を反映した。
つまり、生と死な対立的な関係ではなく、偶然である。
言い換えると、生と死は同じく、偶然性があり、静か安寧な心霊境界を追求することこそ最も重要である。
キーワード:
志賀直哉;死生観;城の崎にて
摘要
日本著名作家志贺直哉,白桦派代表作家之一。
以其惊人的艺术才华和高超的写作风格在日本被誉为“小说之神”,作为私小说和心境小说的大家,日本政府授予志贺“文化勋章”。
本文把作者在实际生活中所经历的死亡和三个小动物之死作文对象进行分析,旨在了解志贺直哉的生死观。
第一章,主要以志贺的文学创作为对象进行研究,他作为白桦派的代表之一在日本文学论坛上有很高的声誉,他作品的风格既不是自然主义也不是理想主义,而是新现实主义。
也就是大多从现实生活中取材,以自己的亲身经历或和自己有直接关系的生活中取材。
因此研究他的作品可以了解他的生活。
第二章描述了他在城崎疗养期间,亲眼看见的三个小动物之死,并且从中体验到了生死的无常观,以及对生死观有了从浅到深的理解。
第三章叙述了家庭因素、基督教生活,以及“大逆事件”都是志贺生死观形成的主要原因。
经历了实际生活中的各种死亡场景后,志贺对于死亡给予了很大的关注,《在城崎》就是很好的实践证明,并且在《在城崎》中,反应了志贺的生死观,即生和死不是对立的两极,而是偶然的,也就是说,生和死一样都具有偶然性,而追求平静安宁的心灵境界才是最重要的。
关键词:
志贺直哉;在城崎;生死观
要 旨
摘要
1.作者および作品について1
1.1作者について1
1.2作品について2
2.三つの動物の死を通じて志賀直哉の死生観を見る3
2.1蜂の死の静寂3
2.2鼠の死の時の努力と恐慌3
3.志賀直哉死生観変化の原因4
3.1家庭の原因4
3.1.1母の死4
3.1.2志賀直哉と父の関係5
3.1.3志賀直哉と祖父母の関係5
3.2基督教の原因6
3.3社会の环境7
3.3.1二戦の影響7
はじめに
日本において有名な文学評論家吉田精一は「志賀は日本心境小説の完成者であり、大正時代最も純粋的な文学家代表者です」と評価した。
芥川龍之介が自殺する前にも志賀文学は「精緻で、東洋的な文化伝統が流れて、このような特徴を持ていれば、一般精神的な、地道な作家だ」と肯定した。
早くも20世紀20、30年代の時に、魯迅、張資平、謝六逸等の人は志賀の文学作品を翻訳し、当時の中国人の成長に大きな影響を与えた。
李会珍は志賀直哉の死生観に対して、世間の精神的な乱れを経験して、死への恐怖を乗り越えて、静かな心境であると評価した。
王钦は、志賀直哉の作品に流れている死生観が読者に、死生問題を気にせずに全力で死と生に向き合うべきだと伝えようとしていると言った。
張思遠は、志賀直哉の作品に独自な魅力があり、『城の崎にて』での死の場面の描写から志賀の独特な生命観が察知できると言った。
命そのものへの愛、死を迎える時の沈着冷静、死生への尊重は志賀独特なものである。
志賀直哉の死生観の形成は単一の要素によるものではなく、家庭、社会、宗教等の影響を受けている。
現在、志賀直哉の「城の崎にて」についてはだいたい彼の心境の変化に関する研究であるが、このような変化はどのように生じたかについての研究は非常に少ない。
心境の変化を生じた原因についての研究に不足なところがあると思うので、志賀直哉の家庭生活、社会状況などの面からいっそう検討したい。
1.作者および作品について
1.1作者について
志賀直哉は小さい時から読書好きだが、一時キリスト教と文学の間に迷っているので、優秀な作品ができていなかった。
宗教に対する興味が弱くなった後、長年に抑えられてきた熱情が再び燃え、志賀直哉は自らの文学創作の道を始めた。
若いときの志賀直哉はずっと迷って、従事したい職業に対してはっきりと認識していなかった。
しかし、木下利玄などの人との付き合いが深めるとともに、彼は純文学に進軍することを決めた。
その後、明治37年に「菜の花と小娘」という処女作を書いた。
大学に入り、志賀直哉は昔の習慣を一切改め、目的のない読書をある文学作品に対するむさぼり読むに変わり、さらに自分の文学創作のために意識的に読む。
大学の間、志賀直哉は友達たちと共に「望野」という雑誌を創刊し、その後では「白樺」と改名した。
1920年、「白樺」の創刊に
際し、貴族の出身であるメンバーたちはヒューマニズムという立場に立ち、上流社会を否定し、自己主張を提唱する。
この雑誌も志賀直哉などの人が自らの文学スタイルを形成する基礎となった。
このときの志賀直哉は人の主観的能動性の発揮や、個性の展示を提唱し、ヒューマニズム向けの文学を推賞する。
作家として、彼の文学創作の道は長くて充実である。
長年文壇に活躍している作家として、彼なりの文学スタイルは後世に多くの不朽の名作に残った。
志賀直哉の生涯を見渡すと、大正時代の文学創作が収めた著しい成果は彼の日本近代文壇での地位を確定した。
1.2作品について
「城の崎にて」という小説は志賀直哉の心境小説の代表作の一つである。
この小説は作者の思想と心境に対する描写に偏り、作品には人生と未来への思考、及び楽観的な生活態度に満ちている。
「城の崎にて」では作者が怪我を受けて城の崎で療養する間、三匹の動物の死を経験したこと通して、自分が生死に対する見方を描写する。
同時に、志賀の死生観は絶えず変化していることも見える。
志賀直哉は心境小説の権威として、日本の文壇できわめて名誉を博している。
志賀直哉の文学創作の道に話を及ぶと、必ず心境小説という概念に言及する。
当時の文学では自然を主とするが、白樺派では理想主義を主張する。
彼らは外国文学の技法を勉強するかたわら、作品の粋を大いに取り入れる。
独特な個性を求める同時に、平凡な生活に隠れている真善美を掘り起こし、現実での偽悪醜を選り分ける。
白樺派の作家及びその作品は、日本文壇に極めて重要な影響を与えた。
白樺派が個人主義の確立を別にしたら、個人主義の存在は無意味である。
貴族から出身し、高等教育及び西洋文化の薫陶を受け、トルストイが好きで、キリスト教に参加したことがあるなどは白樺派の作家の共通点である。
志賀直哉を代表とする白樺派は緊密な思考方式と倫理的な創作スタイルを有している。
人にとって最も重要な使命は自己を実現することだと志賀直哉が思っている。
このため、彼は一貫して自然に回帰し、人の信念を真に明確することを強調し、すなわち彼は共産主義に実現を信じている。
同時代の他の作家と比べて、白樺派の作家が書いた作品はほぼ私小説で、そのうちでは志賀直哉の小説が一番有名である。
「志賀直哉が書いたものはだいだい日記みたいな文章で、それらの随筆はどれでも彼の実生活から取材したが、彼の加工を通して、意外に格調高い文学作品になった」という評価するもある。
これはちょうど「城の崎にて」という小説で証明された。
志賀直哉は療養院にいる間に経験した動物の死という現実生活でのことを潤色し、文章が生き生きと哲理に富むようになり、優秀な心境小説となった。
志賀の文学創作を主対象として研究を行う。
志賀直哉は白樺派の傑出した代表の一人として、文壇で極めて高い名誉を博している。
彼の作品のスタイルは自然主義や理想主義と違って、新現実主義である。
心境小説の傑出した作家として、志賀は現実的な生活経歴を作品に入れ込んだので、彼の作品を研究することは、彼の生活を理解でき、さらに彼の死生観を理解できる。
2.三つの動物の死を通じて志賀直哉の死生観を見る2.1蜂の死の静寂
小説では三匹の動物の死を描写した。
まずは屋根で忙しそうな蜂の巣の隣で、微動だにしない一匹の蜂の死骸がある。
その蜂がそこに死んだ三日間、周りの行き来する蜂たちは平然と自分の仕事をしており、活気に満ちたが冷淡であり、誰もこの小さな死体に邪魔されていなく、あるいは少し止まって昔の仲間を世話する蜂もいない。
このまま三日間の夜に暴雨が降ってから、やっと死骸が消えた。
「僕」の印象中、たぶん蜂の死骸は排水管を通して地上に流された。
それでも、足が縮こまって、触角が顔にくぼみ、泥まみれで静かにある隅に眠って、誰にも注意されていなかった。
これの際立った対照は外の相変わらず騒々しい生活で、精一杯の蜂たちは依然と毎日規則的に働いている。
少し残酷で情がないと見えたが、実は大自然の本来の姿を見抜けたさらに高い知恵である。
我々は誰でも死に直面しなければならなく、生死は自然界で最も普通なことで、別に驚く必要はない。
重要なのは、生きているうちに自分のことをちゃんとして、死んだときは平然として直面する。
自分に対しても他人に対してもこのような態度をとったら、超然とした死生観が得られる。
これは作者がずっと忙しくて仕事をしている蜂の死からそそられた死に対する一回目の思考である。
死は恐ろしくなく、死は生の友で、死が来たとき、我々は昔なじみを迎えるように死を迎え、どんな儀式も必要せず、平常心を持つべきである。
2.2鼠の死の時の努力と恐慌
しかし、それ以上の思考は命からがら逃げる鼠から引き出した。
「僕」は温泉の近くにある公園で散歩しているとき、人々が川から必死に逃げ惑っている大きな鼠を野次馬見物している場面を見た。
鼠にとって生の希望がもてないが、依然として人々の笑い声で必死に頑張っている。
一生懸命に努力すると、必ず生きられると思っているようで、首に串が刺された鼠は川の中心に泳いで行った。
しかし、周りの人々ではこの鼠は必ず死ぬと思っているので、石を鼠に投げてその痛ましい死を祝う。
鼠の死、あるいは死の直前の動騒は「僕」の落ち着いた心で巨大な波瀾を巻き起こした。
死その自身は静かだが、その静けさが来る前に、すべての命のある存在は必ずこのような恐ろしくて苦しいあがきを経験し、これも極めて自然なことである。
死に直面し、まだ生命力を残っている生物は必ず必死に抵抗し、むだだと知っていても甘んじらない。
これはごく普通な人情の常ではないのか?
このように見ると、平然として死の運命を受け入れることはもちろん高尚であるが、誰でも簡単にできるわけではない。
「僕」自身をいうと、蜂のように成り行きに任せると悟ったが、再び死に直面すると、必ず必死に抗争する。
しかし、これはいずれも死を直面するときの自然な態度だが、いったいどれがいいのか?
作者はここで少し動揺した。
このとき、さらにはっきりとした見識が入ってきたので、この問
題が無意味になってしまった。
これは、生でも死でも、成り行きに任せても必死に抗争しても、人が決定するのではなく、冥々の中の偶然の運命によって決まるのだ。
2.3いもりの死の偶然
この点は小説にある三番目の動物―イモリの死から見られる。
「僕」は川の真ん中にある石で一匹のイモリを見た。
「僕」はイモリを嫌いではないが、ふと思い立ってそれを川に追い戻したい。
それで、小石を拾ってイモリに向けて投げたとき、思いがけずちょうどそのイモリを殺してしまった。
「イモリが死んだ。
僕は思わずびっくりした。
僕が殺したのだ。
わざとではないが、確か僕が殺したのだ。
僕の心から言えない憂鬱が引き起こした。
」「僕」にとって、これはただの偶然事件だが、そのイモリにとっては不慮の災禍である。
前述した二つの死についての思考と比べて、今回の悟りはさらに高く、人生その本来の姿への思索だけでなく、自然を超える純粋な哲学への思索である。
成り行きに任せると必死に抗争するという二つの選べられる人生の態度で、どれがより「自然的である」問題の上、彼は浮世と自然を超える倫理を発見し、「生と死は二極ではなく、そこには差異がない」と感じた。
生と死は偶然な意外に支配され、人が必死に抗争してもあきらめて死を待っても同じで意味がない。
ここには「世間の出来事は常に変化する」、「生死は天命だ」という悲観的な人生観が現れた。
志賀はその後の「続々創作余談」で、この小説は「少し人生に飽きたとき書いたもの」と認めた。
3.志賀直哉死生観変化の原因
3.1家庭の原因
3.1.1母の死
志賀直哉は家庭生活を極めて重視する人である。
彼は小さいときから裕福な環境で育てられ、この豊かな子供時代は彼の後期思想の基礎である。
物質生活以外、感情要素も彼の成長で重要な地位を占めている。
祖父母は志賀直哉の兄の死は彼の両親が引き起こしたと思っているので、志賀直哉の一生を影響する二つのことがあった。
一つでは祖父母は前車の轍を踏まないために、自らで志賀直哉を育てることと決まった。
このように、志賀直哉は子供から兄の死に対して特別な理解を持っている。
二つでは兄がなくなった後、志賀直哉は長男になり、家族から大きな希望に寄せられたので、彼のプレッシャーが多くなった。
しかし、祖父母より育てる前に、母親は一生懸命に志賀直哉の世話をしている。
日本の東北も非常に寒く、母親が与えたかわいがるは日常生活で表している。
それでも、この無私の母性愛は志賀直哉が12歳になった年に終わった。
「運命の谷に推され、運命にからかわれたように」と彼は自分のことをそう形容した。
志賀は継母と祖母にも大変世話をされたが、十二歳に母親をなくなったという事実は彼に忘れられない影響を与えた。
子供時期の志賀にとって、母親の死は重い打撃で、耐えられない心の痛みを感じたに違いない。
このことから、彼はさらに深く生死を認識した。
志賀直哉の作品の主題の一つはいわゆる強烈な母性愛である。
彼は作品で何度も子供が母親への同情及び深い依頼感を生き生きとして描写した。
これは彼が純粋な母性愛に対する理解と謳歌を表すだけでなく、彼にとって母性愛の偉大と神秘も表せる。
このように、志賀直哉は実質の長男として、子供時代父母と離れてからずっと祖父母によって育てられてきた。
生みの母がなくなった後、祖母は母親の存在を取り代え、これも志賀直哉が父親と仲良くない原因の一つである。
生みの母の死によって、志賀はこの世の無常や、命の幻と万物の移転を痛感する。
その苦しみから解放するため、彼の無常観がだんだん形成し、さらにその後の一生を影響している。
3.1.2志賀直哉と父の関係
志賀直哉の父親は有名な実業家で、性格は保守的で、実利を重視する。
志賀にとって、父親は比較的に親しくなく、少し厳しいであり、父親への抵抗感もその後頻繁な衝突を引き起こした。
足尾鉱毒事件で、志賀は自分の目で事故の現場を見たい。
しかし、彼はその思いを父親に教えた後、厳しく阻止された。
そして、この問題から父親と激しい対抗を展開した。
この事件も志賀直哉と父親の不和の起点となった。
その後、志賀直哉は女中慕い合い、彼女と結婚することを決めた。
しかし、父親では家柄が釣り合う人を見つけたいので反対した。
父親の話はいつも彼に不快を感じさせ、彼は最後まで堅持すると決心した。
しかし、父親は彼をだまして勝手にその女中を実家まで送還した。
これを聞いた志賀直哉は非常に悲しくて怒った。
そして、父親との不和が頂点に達した。
大正元年、処女作品集「留女」の出版費問題で再度父親とけんかし、志賀が家出をした。
大正三年十二月に結婚し、翌年志賀家から離籍した。
彼はかつて「子供のときから祖父母のそばで育ち、父親とあまり親しくない。
これはたぶん僕が父親と不和になった原因の一つだろう」と言った。
しかし、志賀の心にはずっと父性愛を切に願っているが、一貫して固執な父親はいつも失望させる。
父親との微妙な関係は16年間続いた。
この16年間の不和はかえて志賀の文学創作の原動力となり、彼の抑えられ本性が解放された。
一方、新生活の安定も彼の死生観に調和の基礎を定めた。
3.1.3志賀直哉と祖父母の関係
祖母のやみくもな溺愛で、志賀直哉は思わず強い反逆の性格を形成した。
このことから、祖母との関係は志賀の死生観の形成に大きな影響を与えたと思う。
「或る朝」という作品は祖母の影響を受けて作成した。
この十ページもない作品は志賀直哉にとって極めて重要な意義がある。
ちょうどこと時期、彼は自らが書きたい内容及び創作技法を明確した。
この作品は祖母と口けんかした翌日の朝で出来上がり、内容から見れば祖母と関係する部分が非常に多い。
このことから、志賀直哉にとって祖母の影響が見えた。
また、「暗夜行路」という作品中で、「栄」というキャラクターは祖母と同じような年の女性で、身分以外でも祖母の性格の影が見える。
志賀は創作時いつも現実生活からモデルを見出す。
彼にとって、妻子以外最も親しい人は祖母だろう。
志賀は祖母の原型で創作するつもりがないが、無意識にその方向に向いた。
作品中他の人物の話から、「栄」の言行、性格などにいずれも祖母の姿が見える。
子供のときから祖父母のそばで大きくなり、祖父の行き届いた配慮によって志賀はすくすくと成長してきた。
しかし、明治26年、祖父は殺人罪容疑者として逮捕され、志賀の幼心に暗い影を投げかけた。
友達に笑われたくないため、彼は学校にも行かなく、祖父が潔白になって家に戻ったまでやっと釈然とした。
志賀直哉の生涯を見渡すと、幼年時期の出来事は彼にとって深い影響があるに違いない。
彼が家族をなくしたくない感じは、祖父が戻ってきたとき喜びすぎて思わず泣いたことから見られる。
3.2基督教の原因
明治維新以降、キリスト教は合法的宗教として正式に日本に認められた。
同時に、キリスト教の宣伝とともに、多くの日本の近代作家もキリスト教徒になり、日本の近代文学にごく深い影響を与えた。
志賀直哉はいわゆるその一人である。
彼はかつて宗教家の内村鑑三に影響され、キリスト教徒の生活を体験した。
内村鑑三は「正義に憧れ、虚偽を憎悪する」と主張し、青年時期の志賀直哉の倫理意識に深い影響を与えた。
「内村先生に会ってないと、僕の一生にはきっともっとつまずきがあり、もっと回り道をしたことだ。
」としか直哉がそう言った。
志賀直哉と内村先生との付き合いは7年間続き、彼の精神は内村先生に感化されたので、かなりのキリスト教意識を有している。
内村先生の影響で、志賀はキリスト教に深い興味を持ち、神の博愛と正義を自分の人生目標とされ、敬虔なキリスト教徒になろうと志を立てた。
この時期の志賀は文学とキリスト教の間に迷っている。
この意識はその後志賀に束縛と苦痛を与えたこともあり、彼がキリスト教への信仰が動揺した。
彼は真理を求める一方、このような苦痛に耐えられない。
その後の作品「暗夜行路」から、キリスト教の思想意識が志賀に与えた束縛及び彼の悩みが見られる。
また、キリスト教では人が懺悔意識を持たなければならないことを主張するが、志賀の性格は真実で、人に対して少しも虚偽を望まなく、すなわち「懺悔無用論」である。
その他、キリスト教徒が戦争に対する麻痺と冷淡な態度から、志賀は彼らの内心に隠している深い退廃を見た。
彼はキリスト教にある罪悪感及び贖罪論は自分の思考方式と全く違っていることを深く感じた。
信仰がなくなってから、志賀は新しい文学創作を始めた。
日本近代文学思想におけるキリスト教の重要な影響の一つはその主張である。
それは、自己を否定し、神に帰依する懺悔意識である。
しかし、この懺悔意識は個人主義を基調とする当時の日本文学と互いに対立している。
3.3社会の环境
3.3.1二戦の影響
1945年8月15日、日本の天皇は無条件降服と宣言した。
このため、多くの人は家族をなくなり、住宅を失い、生き続ける希望と自信もなくなって、体が虚無の存在になった。
志賀直哉は家で停戦の情報をもらった。
幸いに、志賀の家は戦火に及ばれていなく、家族もみな無事である。
しかし、空襲、停戦、外国軍隊の駐屯という一連の変化によって、志賀直哉の不安感が強くなったが、言論が次第に自由になった。
言論権の回復は人々が精神的圧力から抜け出せることを意味する。
戦後の日本は改革しなければならない。
この時代に身をおいた志賀直哉も絶対に沈黙しないと選んだ。
彼の当時の政治問題についての多くの言論は社会に深い影響を与えた。
作家として、人として、われわれは彼の戦争に対する痛切な憤りと悲しみを感じられる。
同時に、それらの憤りと悲しみが彼の死生観を深く影響していることも感じられる。
戦争が生じた死亡は彼を深く考えさせ、家族よりこれらの国人の死はさらに彼の死生観を影響し、異なる面から死の意味を理解させる。
3.3.2大逆事件の影響
幸徳秋水は志賀直哉と同じく内村鑑三に感化された者で、彼が会った「大逆事件」は一定の程度で志賀直哉を影響した。
特に秋水の死は志賀に無限な思考をもたらした。
製材所のある職人が爆弾を工場に連れてきたことが発見され、当局は「宮下太吉の社会主義は当時日本の社会主義の先駆者幸徳秋水から来る」ということを理由として、すべての労働組合を封鎖し、一切の先進的刊行物の出版を禁止し、幸徳秋水を含む22人の社会主義者を逮捕した。
その後、彼らに対して秘密審判を行い、「大逆無道、天皇を暗殺したい、暴動を起こす、天皇暗殺未遂」などの罪名を与えた。
大審院の一審で特別判決を下した後、幸徳秋水など24人は死刑、残った2人は有期懲役を宣告された。
このニュースが広げた後、日本国内外の世論が騒がしくなったので、大審院はやむなく天皇の名義で12人の死刑を無期懲役に変えた。
しかし、幸徳秋水など残った12人は絞首刑に処する。
日本の社会主義運動は今回の大規模な残酷によって厳しい打撃を受け、それから下り坂になった。
メディア関係者も自己保存のため、時事あるいは政治への風刺をやめたので、明治末年から大正初年日本文学史上の「冬の時代」が形成した。
事件が発生した後、志賀は日記でこのように書いた。
「昨日、24人の無政府主義者が死刑に処された。
これは日本の歴史においても珍しいことで、僕はさらにその報道を読む気もなかった。
これは歴史上でも想像できないことだった。
」
秋水は「大逆事件」で死刑に処され、四十歳の一生を終えた。
「死に対して、とても決然とした態度、さらに切実に死にたい心を持っているみたいだ。
」志賀直哉はこのように秋水の死を感嘆し、生死についての見方にもいっそう思考があった。
この事件はその後、志賀直哉の他人と違う死生観の形成に伏線を敷いた。
終わりに
『城の崎にて』は作者が怪我して城崎で安静