日本酒.docx
《日本酒.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《日本酒.docx(51页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
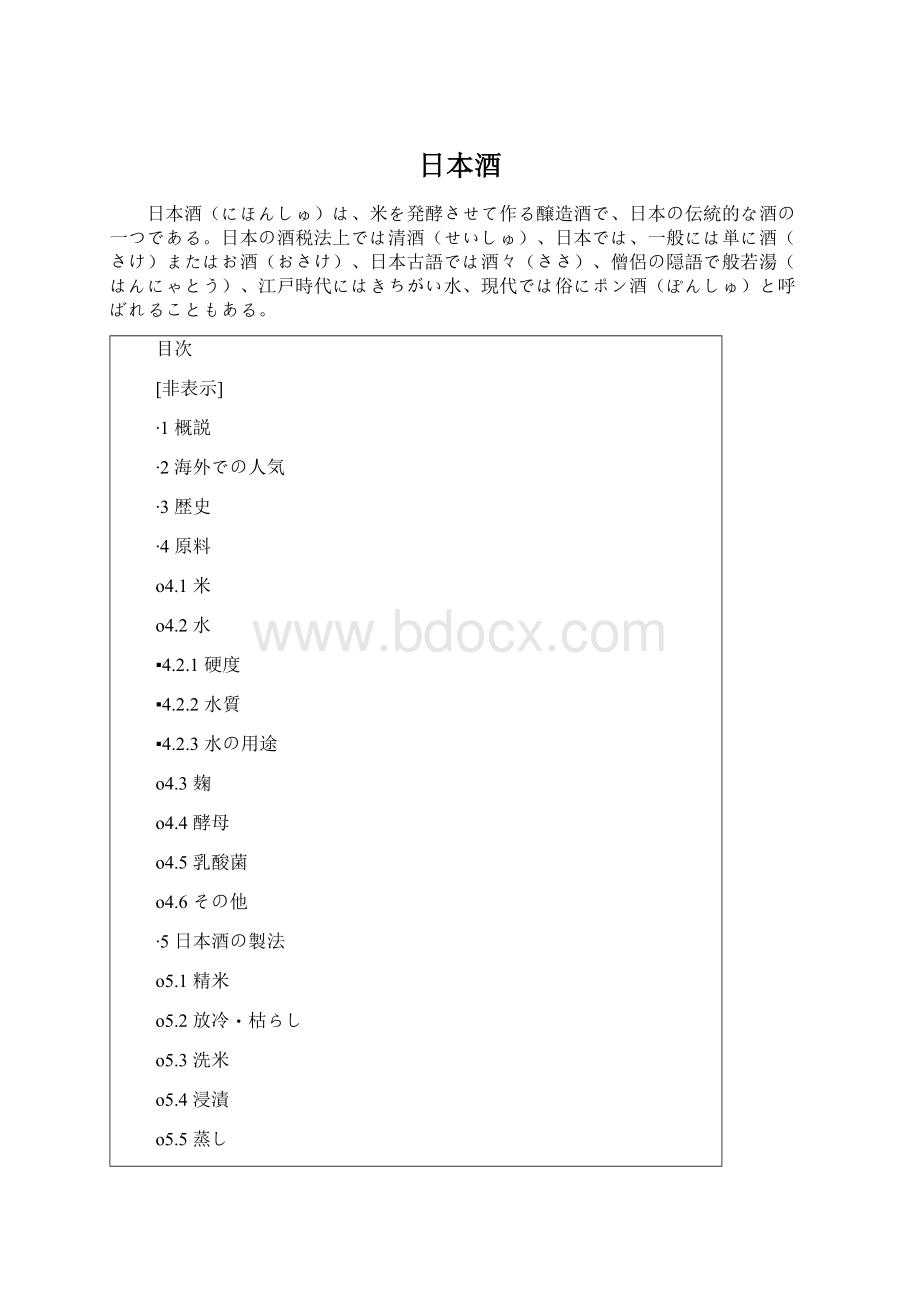
日本酒
日本酒(にほんしゅ)は、米を発酵させて作る醸造酒で、日本の伝統的な酒の一つである。
日本の酒税法上では清酒(せいしゅ)、日本では、一般には単に酒(さけ)またはお酒(おさけ)、日本古語では酒々(ささ)、僧侶の隠語で般若湯(はんにゃとう)、江戸時代にはきちがい水、現代では俗にポン酒(ぽんしゅ)と呼ばれることもある。
目次
[非表示]
∙1概説
∙2海外での人気
∙3歴史
∙4原料
o4.1米
o4.2水
▪4.2.1硬度
▪4.2.2水質
▪4.2.3水の用途
o4.3麹
o4.4酵母
o4.5乳酸菌
o4.6その他
∙5日本酒の製法
o5.1精米
o5.2放冷・枯らし
o5.3洗米
o5.4浸漬
o5.5蒸し
o5.6麹造り
▪5.6.1破精込み具合
▪5.6.2蓋麹法
▪5.6.3箱麹法
▪5.6.4床麹法
▪5.6.5機械製麹法
o5.7酒母造り
▪5.7.1生酛系
▪5.7.1.1生酛
▪5.7.1.2山廃酛
▪5.7.2速醸系
o5.8醪造り
▪5.8.1泡の状貌
o5.9アルコール添加
o5.10上槽
o5.11滓下げ
o5.12濾過
o5.13火入れ
▪5.13.1火入れと「生酒」の関係
▪5.13.2「生酒」をめぐる表示問題
o5.14貯蔵・熟成
▪5.14.1熟成の概要
▪5.14.2熟成のメカニズム
▪5.14.3日本酒の賞味期限の問題
▪5.14.4食との相互補完
▪5.14.5新酒・古酒・秘蔵酒
▪5.14.6ひやおろし
▪5.14.7大古酒
o5.15割水
o5.16瓶詰め・出荷
o5.17製法の用語・表現
▪5.17.1「歩合」
▪5.17.2「仕込み」「造り」
▪5.17.3「酛」「酒母」
▪5.17.4その他
∙6特定名称分類
o6.1普通酒
o6.2特定名称酒
▪6.2.1本醸造酒
▪6.2.2純米酒
▪6.2.3吟醸酒・純米吟醸酒
▪6.2.4大吟醸酒・純米大吟醸酒
∙7ラベル表示用語
o7.1任意記載事項
o7.2その他の表示
∙8外国産日本酒
o8.1経緯
o8.2現状
∙9日本酒に関する単位
∙10日本酒の評価基準・用語・表現
o10.1日本酒度
o10.2酸度
o10.3甘辛度
o10.4濃淡度
o10.5アミノ酸度
o10.6味の表現
o10.7色の表現
o10.8香りの用語・表現
o10.9温度の表現(飲用温度)
∙11日本酒に関する道具
o11.1酒器
o11.2醸造器
∙12日本酒に関する施設
o12.1宗教施設
▪12.1.1祀られている主な神々
▪12.1.2主な神社
▪12.1.3神社以外
o12.2博物館・資料館
∙13日本酒に関する文化行事
o13.1家庭行事
o13.2祭り
∙14日本酒に関する創作作品
o14.1文芸・漫画
o14.2音楽・演劇・舞踊・落語
∙15脚注
o15.1注釈
o15.2出典
∙16関連項目
∙17外部リンク
概説
日本独特の製法で作られた酒の一種を指す言葉である。
日本伝統の酒には他にみりん・焼酎(沖縄では泡盛)がある。
約5℃から約60℃まで幅広い飲用温度帯がある(参照:
#温度の表現(飲用温度))。
同じアルコール飲料を同じ土地で異なった温度で味わうのを常としているのは、他に紹興酒などがある程度で比較的珍しい(詳しくは燗酒を参照)。
料理で魚介類の臭み消しや香り付けなどの調味料としても使用される。
なお日本では酒税法の関係上、一般に「清酒」として販売されている日本酒のアルコール度数は22度未満(合成清酒の場合は16度未満)であることが求められているが(酒税法第3条7・8項)[1]、それより高いアルコール度数の日本酒を製造することも技術的には可能で、実際『越後さむらい』(玉川酒造)のように、日本酒の製法で製造されながらもアルコール度数が46度に達する酒(酒税法上はリキュール扱い)も存在する。
日本酒の5割が関西地方で作られており、特に灘のある兵庫県(30%)と伏見のある京都府(15%)での生産量が多い。
海外での人気
近年、発祥国日本での消費は減退傾向にある一方、アメリカ合衆国・フランスの市場では日本酒、とくに吟醸酒の消費が拡大し、イギリスでも2007年、伝統ある国際ワインコンテストに日本酒部門が設置されるなど、「sake」として親しまれるようになっている。
(参照:
「日本酒の歴史」-昭和時代以降)
韓国でも数年前から日本酒がブームとなっている。
しかし関税が高く現地では高級酒扱いである。
韓国語では“正宗”と呼ばれていた(桜正宗にちなむらしい)が最近では「サケ」が定着してきている[2]。
歴史
詳細は「日本酒の歴史」を参照
原料
日本酒の主な原料は、米と水と麹(米麹)であるが、それ以外にも酵母、乳酸菌など多くのものに支えられて日本酒が醸造されるので、広義にはそれらすべてを「日本酒の原料」と呼ぶこともある。
専門的には、香味の調整に使われる「醸造アルコール」「酸味料」「調味料」「アミノ酸」「糖類」などは副原料と呼んで区別する。
米
用途によって、麹米(こうじまい)用と掛け米(かけまい)用の2種類がある。
麹米には通常酒米(酒造好適米)が使われる。
掛け米には、全部または一部に一般米(うるち米)が使われるが、特定名称酒の場合、酒米のみが使われることが多い。
普通酒は麹米、掛け米ともにすべて一般米で造られるのがほとんどである。
しかし、一般米からも高い評価を得る酒が造られており、高級酒となるとかつて山田錦一辺倒の傾向すらあった原料米の選び方や使い方も、近年は新種の開発などにより変化が著しい。
「酒米」も参照
水
水は日本酒の80%を占める成分で、品質を左右する大きな要因となる。
水源はほとんどが伏流水や地下水などの井戸水である。
条件が良い所では、これらを水源とする水道水が使われることもあるが、醸造所によって専用の水源を確保することが多い。
都市部の醸造所などでは、水質の悪化のために遠隔地から水を輸送したり、良質な水源を求めて移転することもある。
酒造りに使われる水は酒造用水と呼ばれ、仕込み水として、また瓶、バケツの洗浄用水として利用される。
蔵元の一部は、仕込み水を商品として販売している。
硬度
水の硬度は、酒の味に影響する要素の一つである。
日本の日常生活では、硬度の測定にアメリカ硬度を用いているが、醸造業界では長らくドイツ硬度を用いてきた。
最近はアメリカ硬度へ移行する兆しも見受けられる。
[要出典]
造られる酒の味は、おおざっぱに言えば、軟水で造れば醗酵の緩い、いわゆるソフトな酒、硬水で造れば醗酵の進んだハードな酒になる。
理由は、醸造過程で硬水を使用すると、ミネラルにより酵母の働きが活発になり、アルコール発酵すなわち糖の分解が速く進み、逆に軟水を使用するとミネラルが少ないため酵母の働きが低調になり発酵がなかなか進まないからである。
江戸時代以来、高品質な酒を産出してきた灘では宮水と呼ばれる硬水が使用されていた。
一方、1897年(明治30年)には広島県の三浦仙三郎により軟水醸造法が開発された。
かつては、硬水が酒造用水としてもてはやされていたが、軟水で醸した酒の味わいが現代人の味覚に合っているとして、近年では軟水も見直されている傾向もある。
[要出典]
水質
水は、酒の原材料のなかで唯一、表示義務の対象とされていない。
したがって、原料水が、井戸水であるか水道水であるかを明らかにする必要は無い。
ただし、酒造用水に課せられている水質基準は、水道水などと比べるとはるかに厳格である。
酒蔵は、使用する水を事前にそれぞれの都道府県の醸造試験所、食品試験所、酒造指導機関などに送って監査を受けなくてはならない。
監査は以下のような項目で行なわれる。
∙臭気
∙味
∙色度
∙濁度
∙pH
∙塩素イオン
∙カルシウム
∙総硬度
∙マグネシウム
∙トリクロロエチレン
∙全燐
∙亜硝酸性窒素および硝酸性窒素-不検出でなければならない。
∙過マンガン酸カリウム消費量
∙一般細菌数-不検出でなければならない。
∙大腸菌群-不検出でなければならない。
∙水銀
∙鉄-許容範囲は0.02mg/l以下(水道水では0.3mg/l以下)。
∙マンガン-許容範囲は0.02mg/l以下(水道水では0.3mg/l以下)。
日本の水は各地によって小差はあるもののほとんどが中硬水であり、香味を損ねる鉄分やマンガンの含有量が少ないので、醸造に適していると言える。
例えば、太平洋戦争前に満州へ渡り、在留日本人のために当地で日本酒を造ろうとした醸造業者たちが利用できる水を見つけるのに苦労したという話が多く聞かれる。
なお、発酵、および麹菌や酵母菌の繁殖を促進するのに有効なだけの微量のカリウム・マグネシウム・燐酸については、成分調整として添加することができる。
水の用途
酒造りに用いられる酒造用水は、以下のように分類される。
∙醸造用水-醸造作業の最中に酒のなかに成分として取りこまれる水。
o洗米浸漬用水-米を洗い、浸しておく水。
仕込みの前に米の中に吸収される水でもある。
o仕込み用水-醸造時に主原料として加える水。
酒が「液体」として商品になるゆえんともいえる。
o雑用用水-洗浄やボイラーに用いられる水。
これにも、水質の項で述べられているような厳しい基準を通過した酒造用水が用いられる。
∙瓶詰用水
o洗瓶用水-瓶を洗う水である。
o加水調整用水-アルコール度数を調整するために加える水。
醸造後に酒にとりこまれる。
o雑用用水-タンクやバケツの清掃に用いる水。
これにも、水質の項で述べられているような厳しい基準を通過した酒造用水が用いられる。
杜氏や蔵人の日常生活(食事や洗面など)には、一般人のそれと同じく水道水が用いられる。
なお、興味深いことに、蔵人たちが入る風呂には酒造用水を用いる酒蔵が多い。
すでにその段階から「仕込み」が始まっているとの酒蔵の考えによるものであり、縁起かつぎとして行っている。
麹
日本酒に用いる麹は、蒸した米に麹菌というコウジカビの胞子をふりかけて育てたものであり、米麹(こめこうじ)ともいう。
これが米のデンプンをブドウ糖に変える、すなわち糖化の働きをする。
穀物である米は、主成分が多糖類であるデンプンであり、そのままでは酵母がエネルギー源として利用できないので、麹の働きによって分子量の小さな糖へと分解せねばならない。
言いかえれば、酵母がデンプンから直接アルコール発酵を行うことはできないので、アルコールが生成されるには酵母が発酵を始められるように、いわば下ごしらえとしてデンプンが糖化されなければならない。
その役割を担うのが、日本酒の場合は米麹である。
米麹は、コウジカビが生成するデンプンの分解酵素であるα-アミラーゼやグルコアミラーゼを含み、これらの働きによって糖化が行われる。
米麹は、ほかにタンパク質の分解酵素も含んでおり、分解によって生じたアミノ酸やペプチドは、酵母の生育や完成した酒の風味に影響する(参照:
#麹造り)。
洋酒では、ワインに代表されるように、原料であるブドウ果汁の中にすでにブドウ糖が含まれているので、わざわざこうした糖化の工程が要らず、そのため単発酵文化圏となった。
東洋においては、日本酒だけでなく、他の酒類や味噌、味醂、醤油など多くの食品に麹が使われ、それが食文化的に複