关于日语的否定表现.docx
《关于日语的否定表现.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于日语的否定表现.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
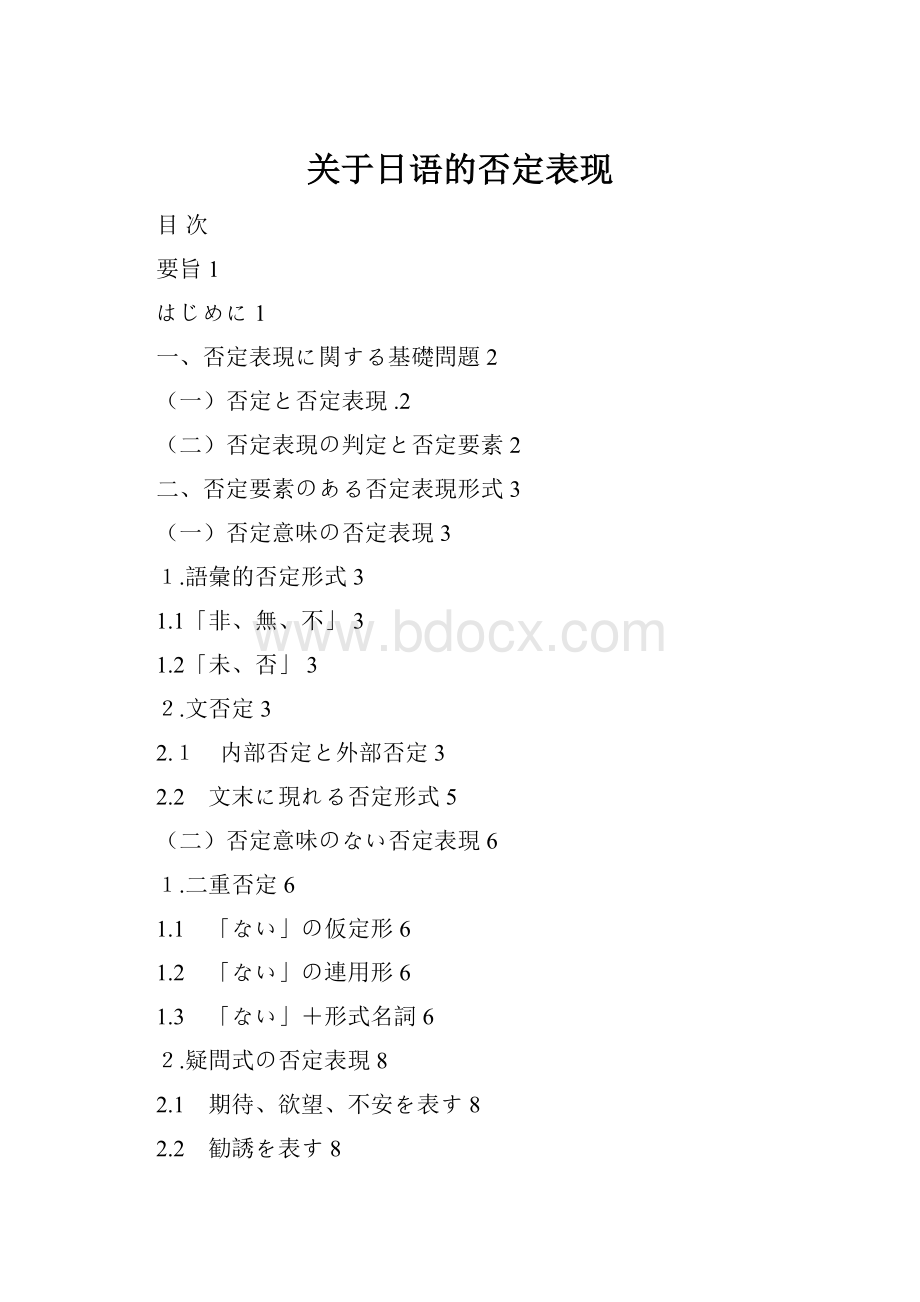
关于日语的否定表现
目次
要旨1
はじめに1
一、否定表現に関する基礎問題2
(一)否定と否定表現.2
(二)否定表現の判定と否定要素2
二、否定要素のある否定表現形式3
(一)否定意味の否定表現3
1.語彙的否定形式3
1.1「非、無、不」3
1.2「未、否」3
2.文否定3
2.1 内部否定と外部否定3
2.2 文末に現れる否定形式5
(二)否定意味のない否定表現6
1.二重否定6
1.1 「ない」の仮定形6
1.2 「ない」の連用形6
1.3 「ない」+形式名詞6
2.疑問式の否定表現8
2.1 期待、欲望、不安を表す8
2.2 勧誘を表す8
2.3 確認を求める、主張と勧誘などを表す「ではないか」8
3.その他の非否定意味の否定表現9
3.1 「にちがいない」と「かもしれない」9
3.2 「ほかはない」、「にすぎない」、「しかない」9
三、否定要素のない否定表現形式9
(一)「~かどうか」9
(二)「拒絶」「禁止」「欠席」など。
9
(三)「~かねる」「~がたい」「~にくい」など。
10
終わり10
参考文献12
日本語の否定表現について
要旨 日本語には、曖昧表現、敬語表現など、さまざまな表現方式がある。
その中には、否定表現という表現方式がもっとも重要なものの一つと言える。
日本語の否定表現が否定の意味を表すほかに、具体的な言語環境によって、反対語および曖昧語を組み合うこともできる。
否定表現はそのような特質を持つからこそ、日本語の学習者にとってなかなか難しいものになっているとともに、研究する価値もある。
本稿は否定表現に関連する先学の研究を参考にして、否定要素と否定表現の関係を基にして、日本語否定表現の形式を分類し、帰納する。
否定要素のある否定表現、否定要素を含まない否定表現などの分類がある。
第一章、否定表現に関する基礎問題、基礎概念についての説明である。
第二章は、否定要素のある否定表現形式の分類である。
第三章は否定要素のない否定表現形式の分類である。
終わりでは、本文の結論と謝辞である。
下位分類には語彙の否定、文の否定などがある。
本文はたくさんの例を挙げて、具体的な言語環境とあいまって、否定表現の形式を概括することを目的にする。
キーワード 否定表現 否定要素
はじめに
言語とは、コミュニケーションのための記号の体系である。
日本語は複雑性と曖昧さを以って、世界の言語システムに名を聞かせている。
その複雑性と曖昧さをもっともよく伝えている表現の一種は否定表現なのである。
日本人は否定表現をよく使うという点も否定表現が日本語の主な一環ということを反映する。
否定表現にはさまざまな表現形式がある、たとえば、語彙の中「不十分」、「不必要」の「不」、「非公式」の「非」、「無愛想」の「無」など;文の中の「ない」「なければ」「ず」「ぬ」「まい」[1]など;その他、意味的否定表現「だめ」「大丈夫」、反義語的否定表現「ものか」「か」[2]など否定要素のない否定表現もたくさんある。
否定表現は肯定表現を元にしてできるという説が普通であるが、肯定表現に置き換えられて、必ず否定表現として成立することはまったく適切とは言えないのである。
本文は否定要素と否定表現の関係を中心として、詳しく分類し、説明するつもりである。
一、否定表現に関する基礎問題
本格的な否定表現の研究をする前に、否定および否定表現に関する基礎問題と基礎概念を明らかにしなければならない。
(一)否定と否定表現
否定という文法用語が使われている「現代言語学辞典」(田中春美、成美堂、1988、2)「英文法辞典」(清水 護 培風舘 1965.0)「新英語学辞典」(大塚高信ら、研究社、1982.11)などでは、否定の概念を「否定要素を使うこと」と解釈する。
現代日本語には、否定辞「ない」「まい」「ぬ」などが現れた時、否定表現、否定の表現、否定文、否定構文など、いろいろと呼ばれたが、否定表現と呼ばれたのは普通である。
具体的に、ここではちょっと「日本文法大辞典」(松村明編 1971)の「否定表現」の項目と「日本語学辞典」(杉木つとむ、岩淵匡編、1990)の「否定文」の項目を引用したいのである。
まずは「否定表現」についての解釈:
否定は肯定に対立するものとして考えられているが、これが古典的論理学の流れを込むものである。
…(中略)…否定表現の形式には次の五類がある。
1
「非、不、否、無、未」等の漢語から来た否定の接頭語によるもの。
2
打ち消し(否定)の助動詞「ず、まじ、じ(以上文語)、ない、ぬ(ん)、まい(以上口語)」によ
るもの。
3
形容詞「ない」によるもの。
4
感動詞「いいえ」「いや」により否定の応答を表す。
5
否定の陳述と呼応する陳述の副詞「つゆ、をさをさ、ゆめ、ゆめゆめ、よも、え、な(そ)(以上
文語)、決して、ちっとも、ろくに、いっこう(以上口語)」を伴うもの。
次は「否定文」についての解釈[1]:
否定要素が文という文法的作用をとった場合。
たとえば、「僕は本を読まない」など。
否定要素とは否定的な意味をもつ素性のことで、ナイ、イイエ、決して…ナイ、スコシモ…ナイ、ドコニモ…ナイ、忘れる(覚えていない)、キライ(好まない)、不可能だ(可能ではない)など。
以上の解釈を見て、大体同じことを言う。
重なるところも多いが、基本的には同一なものとして扱うことが分かる。
否定表現は否定文より指している範囲が大きいので、本文は「否定表現」という言い方を採用することにした。
(二)否定表現の判定と否定要素
否定表現は否定の形式を採用することも必要であるし、否定の意味を表すことは言うまでもないのである。
つまり、否定要素さえあれば、もしくは、否定の意味さえ表せば、否定表現になる。
この否定表現の認定について、小川輝夫(1984)は否定表現を次のように分類している。
(一)
否定することを任務とする表現。
(二)
否定語が用いられている表現。
(三)
否定語が用いられて否定することを任務とする表現。
前述したように、「日本語学辞典」(杉木つとむ、岩淵匡編、1990)は否定要素をこのように解釈している:
否定要素とは否定的な意味をもつ素性のことで、ナイ、イイエ、決して…ナイ、スコシモ…ナイ、ドコニモ…ナイ、忘れる(覚えていない)、キライ(好まない)、不可能だ(可能ではない)など。
本文も小川輝夫の立場をとって、日本語の否定表現を否定要素のある否定表現形式と否定要素のない否定表現形式の二種類に分けることにする。
否定表現についての基礎問題を明らかにして、次は否定表現についての具体的な分類と説明である。
二、否定要素のある否定表現形式
(一)否定意味の否定表現
1.語彙的否定形式
日本語の否定については、工藤真由美(2000)は『時、否定、取り立て』で、否定を「<派生>による語彙的否定形式」(例:
不自由)と「主語と述語との結びつきを否定する文否定(自由ではない)」とに分けている。
本文は下位分類が主に語彙否定と文否定に分けることにする。
語彙的否定形式には、「不幸せだ(不器用だ)、無関心だ(無愛想だ)、非常識だ、未婚だ、予想外だ、無理だ、駄目だ、否定的だ、欠けている、欠席する、否定する、打消し、否認する」[1]などがある。
否定接頭詞のある単語が主な一環である。
薄红昕の『日本語における否定表現』によると、それらの中では、否定接頭詞としてよく使うのは「不、無、非、未」である。
しかし、「不、無、非、未」がふくまれているものであっても、接頭辞と認められるのは不可能である。
例えば「無地、不幸、非常、非行、未来、不在、未遂」のような単語のうちにある「不、無、非、未」を接頭辞とは認めにくい。
ただ一つの熟語化した単語とする方が正しい。
次にもっと詳しい分類をさせていただく。
1.1「非、無、不」
まず幾つの例を見てください:
不幸、不在、不礼儀、不入り;無益、無期、無意識、無届け;非運、非行、非動物[2]。
サトー(1982)は「不」「非」「無」の基底構造として、名詞、動詞、形容詞という三つの場合を次のように挙げている。
名詞:
Nがないこと Nに/が/を/をしないこと Nが悪いこと Nでないこと Nに反すること;
動詞:
Vしないこと Vされないこと;
形容詞:
Aでないこと、など。
(N:
名詞、V:
動詞、A:
形容詞)
これで以上に挙げられた例を分析してみると、表1になる。
表1
Nがないこと
不幸=幸運がないこと
無益=利益がないこと
非行=行為が悪いこと
無意識=意識がないこと
非運=運がないこと
無期=期限がないこと
Vしないこと
無届=届け出ないこと
不在=ある場にいないこと
A/Nでないこと
非動物=動物でないこと
不礼儀=礼儀が正しくないこと
表1の分析から見て、「非、無、不」が単語をなす時に、名詞、動詞、形容詞という三種類の基底単語を元に造語していることがわかる。
また、「非、無、不」が強い造語能力を持っていることも分かる。
1.2「未、否」
サトー(1982)の基底構造の論述を利用して分析すると、「未」は「まだVしないこと」「まだvされないこと」「Aでないこと」など、「否」は「でないN」「しない/でないとVすること」と定義する。
例:
未熟、未刊、未解決、未曾有、未届、否運、否定、否認.では、この理論で、以上の例を分析してみると、表2になる。
表2
まだVしないこと
未熟=まだ成熟しないこと
未解決=未だ解決しないこと
未曾有=いまだかつて起こったことがないこと
未届=まだ届けていないこと
まだvされないこと
未刊=未だ刊行されないこと
でないN
否運=よくない運
しない/でないとVすること
否認=否と認めること
否定=そうでないと打ち消すこと
表1と表2の例から見ると、「未」「否」は「不」「非」「無」の使い方と意味と少し違うのである。
「未」は事柄が未了であること、あるいはある状態に達していないことを表しているので、直接名詞を否定することができない。
「否」は打ち消すという意味で、その自身が名詞であるため、専ら動詞と結合して否定動詞を形成させる働きを持つ以外に、形容詞として名詞を修飾することもできる。
2.文否定
2.1 内部否定と外部否定
文否定というと、工藤真由美(2000)は『時、否定、取り立て』で、述語が表す属性の非存在を表す「しないのだ」と、話し手の打消しの「するのではない」とが存在する[1]。
例えば、「食べない」は「食べないのだ」と「食べるのではない」との二つに解釈できる。
前者が「食べない」とを断定するのに対して、後者が「食べる」ということを否定する。
つまり、前者が述語内部の否定のに対して、後者が語句外部の否定である。
二つの相違点について、内部否定が客観的であるが、外部否定がもっと主観的だと思う。
具体的な例を見てください。
例1:
その時、彼がここにいなかった。
例2:
その時、彼がここにいたのではない。
例1が内部否定の形式「いなかった」で、「ここにいた」という事態を否定して、つまり、「ここにいた」という事実が存在しないことを強調するので、客観的な傾向がある。
例2が「ここにいたのではない」の形式で、「ここにいた」という想像する事実を否定する。
つまり、例2のように使うときは、外部否定が話し手の主観意識で物事を判定すること。
2.2 文末に現れる否定形式
文末に現れる否定形式がたくさんある。
それと呼応する分類方も多い。
本稿が否定の形式から、主に「~がない」と「~ではない」という二種類に分けている。
次は具体的な例を挙げて、各形式の用法と特徴を説明する。
「~がない」の中には、「ことはない」、「わけがない」、「つもりはない」を例にする。
表3
「ことはない」
用法1
「ことはない」は動詞連体形について、動詞を否定することによって、動作、作用の非存在
の意を表す。
よく「そうする必要がない」ような意味を表す。
例1
こまったことがあったらいつでも私に言ってね。
ひとりでなやむことはない
のよ。
—『日本語文型辞典』[1]
用法2
「ことはない」はよく「二度と」「実際に」「多分」などの副詞と呼応して、ことの
「起こっていない」という意を表す。
例2
ジョイスは二十二歳で「自発的亡命者」として欧州大陸に渡り、五十八歳で死ぬまで二度と故国に住むことはなかった。
—『読売新聞』
表4
「わけがない」
用法1
「わけがない」の「わけ」は原因理由と話し手の念願を表す、「ない」は「不存在」を
表す、だから、「わけがない」は「物事は成立する理由と可能性がない」と理解してよい、
否定意味が濃いのである。
例1
社会の安全が保証されずに経済が発展するわけがない。
—『朝日新聞』
用法2
「わけがない」は対話文の中に、話し手の強い否定意見を表すときにも使える。
例2
—「暑いな。
タクシーが来るといいんだけど」
—「何言ってんの。
こんなとこにタクシーなんか来るわけないよ」
—『現代日本語文法4』
表5
「つもりはない」
用法
「つもりはない」はよく話し手がある意志を否定したいときに使える。
例
例1:
このけんかはあの人達が始めたことで、わたしにはそんなことをするつもりは全く
なかったんです。
—『日本語文型辞典』
例2:
いますぐ行くつもりはないが、アメリカのことを勉強しておきたい。
—『日本語文型辞典』
表3、4、5の示したとおり、「~がない」などの用法は文末否定の外部否定形に属する、否定要素「ない」は否定形式述語の外部にあり、一般に形式名詞「の」「こと」などと伴って、慣用形式になる。
このような用法を直接に「~が存在しない」と解釈できるものの、具体的な文脈を元に、この以上のように様々な解釈を形づけることができる。
それからは、文末の否定形式のもう一つの形式「~ではない」について説明させていただく。
「~ではない」の中に、「のではない」、「わけではない」、「ものではない」を例にする。
表6
「のではない」
用法1
「のではない」を助動詞「だ」の否定形式と見てよいであろう。
単な否定意味を表す他
に、話題を修正するきらいがある。
例1
例1:
新聞を読んだのではない。
雑誌を読んだのだ。
用法2
「のではない」は「読む」の対象「新聞」を全面的に否定して、修正する意味が含まれている、この時にはよく「~のではない、~のだ」という形式を採る。
例2
例2:
読売も産経も国旗·国歌に対する一般国民の意思表示を問題にしているのではない。
あくまでも公立学校の卒業式における教師の態度として処分に値すると主張している
のだ。
—『朝日新聞』
用法3
「のではない」は話し手が聞き手のすることに対する禁止の意を表す。
例3
例3:
社会に出ても、くじけるんじゃないぞ。
—『現代日本語文法4』
用法4
「のではない」は「へきだ」「必要だ」などとともに使う時、主観的な対比を通って、話し手の強い願望を表す。
例4
高裁では理念や形式だけにとらわれるのではなく、行政の実態も踏まえて審理を尽く
すべきだろう。
—『読売新聞』
医師は報道の制限を望むのではなく、患者にしっかり向き合い、不安を取り除いていく
べきだ。
—『朝日新聞』
表7
「わけではない」
用法1
「わけではない」は現在の状況と描写から出た結果を否定する。
例1
このレストランはいつも客がいっぱいだが、だからといって特別においしいわけでは
ない。
—『日本語文型辞典』
用法2
「わけではない」の前に、よく否定の原因とか、条件とかを添える必要が時にはあるから、
「~のだから、~わけではない」、「~ば、~わけではない」などの形式がよく出てくる。
例2
やっぱりおまえのところへ来るんだから、女嫌いというわけでもなかろう。
—『娼婦たちの暦』
フランスや米国のエリート大学院を卒業すれば、倒産しかけた大企業を立て直せる能力が身につくわけではない。
—『読賣新聞』[1]
用法3
「そのもの~わけではない」、「そもそも~わけではない」などの形式で、緩和と強調の意を
表す
例3
システムそのものは突然変異と自然選択で作られたわけではない。
新しいシステム
が立ち上がる時は突然変異と自然選択以外のメカニズムが必要なのだと思う。
—『日本経済新聞』
そもそも回転ドアそのものが悪いわけではない。
建築の内部と外部の環境を隔てるのに優れている。
—『朝日新聞』
表8
「ものではない」
用法1
「ものではない」は「すべきではない」と他人に「何かをしないでくださいような
アドバイス」をあらわす。
例1
人の悪口を言うものではない。
—『日本語文型辞典』
男は人前で泣くものではありません。
—『日本語文型辞典』
動物をいじめるものではない。
—『日本語文型辞典』
用法2
「ものではない」は「決して」など強調する意味のある副詞とともに使う時、否定の意味を強めて、話し手そのものの主張などを強調する効用がある。
例2
もっとも、人の生き方の根本にかかわるこういう問いは、言葉によって答えようとしても
なかなかうまくいくものではない。
—『私の中のシャルトル』
用法3
「ものではない」は「た」について、「いけない」、「不可能」などの意を表す。
例3
こんな下手な写真など、人に見せられたものではない。
—『日本語文型辞典』
表6、7、8から見ると、「~ではない」などの文末否定形式に、否定要素「ない」が判断を表す助動詞の内部にあり、肯定表現と対立関係を形成する。
「のではない」はよく単な否定意味を表す他に、話題を修正するきらいがある。
「わけではない」はよく現在の状況と描写から出た結果を否定するが、「ものではない」は「すべきではない」と他人に「何かをしないでくださいようなアドバイス」をあらわす。
無論、これらも以上のように、違う言語環境に様々な用法と解釈がある。
(二)否定意味のない否定表現
1.二重否定
否定の言葉を二度重ねて肯定の意味を強めたり、その肯定を婉曲に表したりする語法[1]。
1.1 「ない」の仮定形
この種類はよく「ない」の仮定形が動詞の否定形式とともに使う。
よく使う形式としては、次のようなものがある。
「ないと…ない」、「ないといけない」などが含まれる「ないと」の形式と「なければ…ない」、「なければいけない」などが含まれる「なければ」の形式がある。
具体的な例を見てください。
例1:
この映画は成人でなければ見ることができない。
—『日本語文型辞典』
例2:
教師は、生徒に対して公平でなければならない。
—『日本語文型辞典』
例3:
風邪を防ぐには十分な休養を取らないといけません。
—『日本語文型辞典』
1.2 「ない」の連用形
この種類はよく「ない」の連用形が動詞の否定形式とともに使う。
例えば、「なくてはいけない」「なくてはならない」など。
まずは例1、2を見てください。
例1:
今晩中どうしてもレポートを仕上げなくてはいけない。
—『現代日本語文法4』
例2:
出国の際にはパスポートを提示しなくてはいけない。
—『現代日本語文法4』
意味から見れば、「ない」の連用形は「ない」の仮定形と同じである。
すなわち、例1と例2は次の例3例4のように置き換えていい。
例3:
今晩中どうしてもレポートを仕上げなければならない。
例4:
出国の際にはパスポートを提示しなければなららい。
1.3 「ない」+形式名詞
この種類はよく「ない」+形式名詞+否定形式の形で、強調する意を表す。
よく使うのは「ないものでもない」、「ないこともない」と「ないわけにはいかない」などである。
例1:
この程度の料理なら、私にも作れないものでもない。
—『日本語文型辞典』
例2:
部長は直属の上司なので、結婚式に呼ばないわけにはいかない。
—『現代日本語文法4』
例3:
よく考えてみれば、彼の言うことももっともだと思えないこともない。
—『日本語文型辞典』
2.疑問式の否定表現
疑問式の否定表現の分類としては、「形容詞連用形+ないか」と「動詞未然形+ないか」という二種類が主な中身である。
具体的な言語環境によって、疑問式がたくさんのモーダルを表すことができる。
次は各モーダルの疑問式表現を一覧してください。
2.1 期待、欲望、不安を表す
「否定形式+かな」はよくこのようなモーダルを表す。
終助詞「かな」は感嘆な意味を表す。
例1:
だれか来ないかな?
例2:
成績上がらないかな?
例3:
どうしてあのときもう少し上手に言えなかったかなと思うと悔しくてならない[1]。
例1、2、3から見ると、「否定形式+かな」はよく話し手の心の状態を描くときに用いる。
普通は非対話形の言語環境に用いる。
例1、例2は話し手の期待と欲望を表す、例3は期待などを表す他に、過去に対する行為への悔しさをも表す。
「否定形式+かな」は「期待と欲望」を表すと同時に、その他に何か意外なことが起こるという心配もあるから、「不安」をも表す。
具体的な例を見てください。
例1:
みんなで行ったら楽しくないかな。
例2:
失敗しないかなとても不安だった。
2.2 勧誘を表す
この表現はよく聞き手に欲望などを表すときに、「勧誘」というモーダルが出てくる。
「動詞未然形+ない?
」という形は普通である。
例1:
明日、映画を見に行くんだけど、君も行かない?
—『現代日本語文法4』
例2:
今、渋谷にいるんだけど、出てこない?
食事でもしょうよ。
—『現代日本語文法4』
例1、2から見ると、勧誘は「期待、希望」から派生したものということは分かる。
「期待、希望」は自分の心の状態であるが、このような自分の「期待、希望」を聞き手に話すときに、「勧誘」になる。
つまり、例1は「君も行ってほしい」、例2は「出てほしい」と言うのである。
2.3 確認を求める、主張と勧誘などを表す「ではないか」
「ではないか」は疑問式の否定表現の代表として、言わなければならないのである。
「ではないか」は話し手が聞き手に確認を求めるときに使える。
前提は話し手と聞き手両方も「あること」に一定の程度の了解があるということである。
例1:
高校の同級生に田中君っていたじゃないか