逆都市化时代的都市地域政策.docx
《逆都市化时代的都市地域政策.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《逆都市化时代的都市地域政策.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
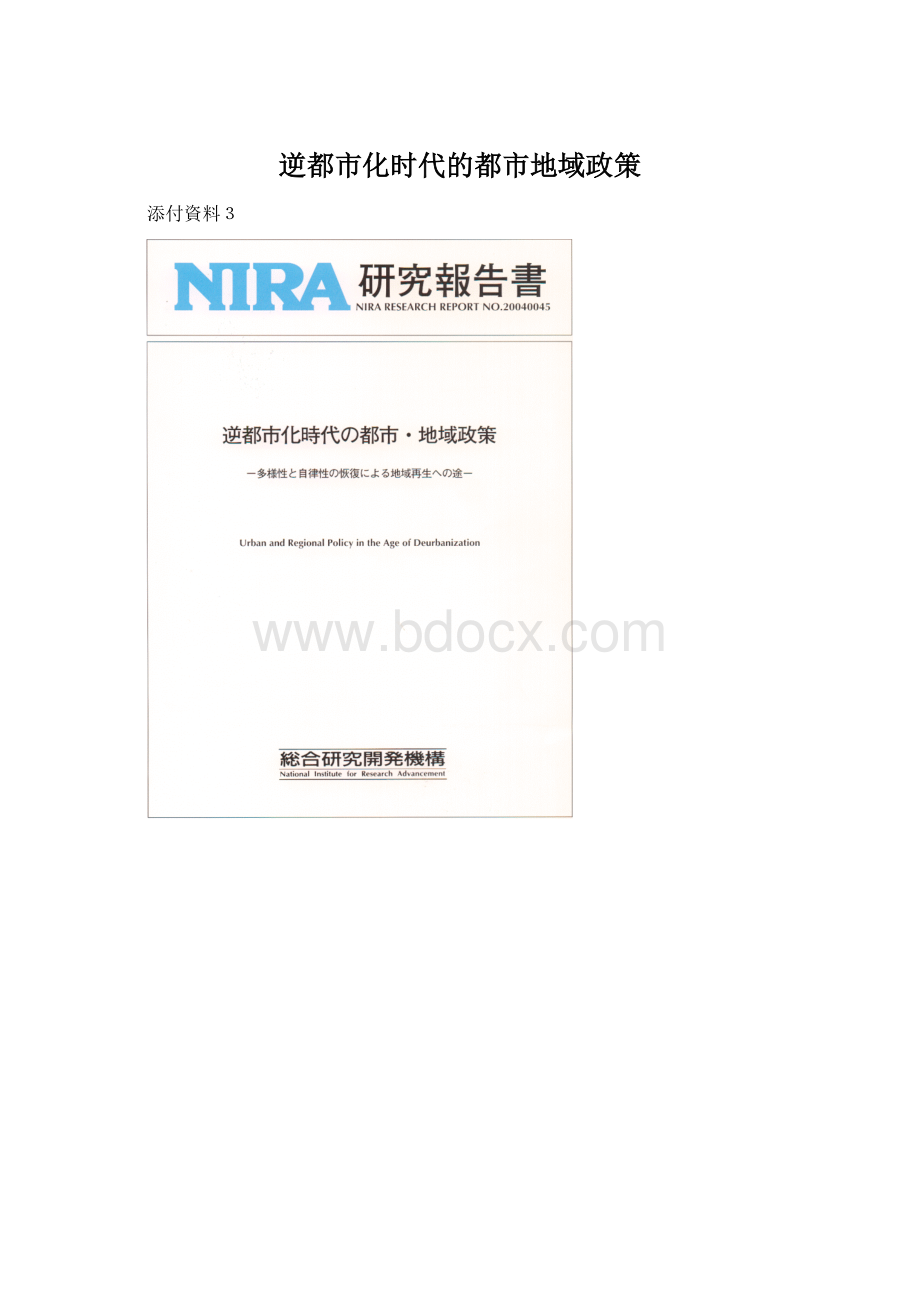
逆都市化时代的都市地域政策
添付資料3
要 約
第3章 逆都市化時代の都市・地域政策の基本的方向
(第3節)
高度経済成長・人口増加時代から先送りされてきた都市構造の根幹に触れる問題として、自動車に過度に依存した交通体系からの脱却という中長期的な政策課題が存在する。
鉄道と自動車を比較した場合、空間利用・エネルギー利用・環境負荷において鉄道は自動車よりも優れており、逆都市化時代と相性の良いコンパクト・シティ型の都市構造に誘導していく上でも有利であることから、鉄道等の公共交通に交通体系をシフトしていくことが求められている。
わが国の鉄道が「公共交通」というレッテルを貼られているために本来の能力を発揮できていないことも改善すべきである。
鉄道は「公共交通」ではなく「共用・集約交通」であると認識を改め、鉄道事業者に利潤最大化の価格設定権を与え、交通ニーズの特性に応じた交通システムが市場機構を通して実現されることを期待すべきである。
基幹輸送は近代化された既設鉄道や新設される路面電車によって担われ、フィーダー(末端)輸送は中型・小型あるいはデマンド方式も含むバスや乗合タクシー(同方面の移動ニーズをITの活用により集約し効率性を高める)によって担われる地方都市の姿は、逆都市化時代において「共用・集約交通」が本来の能力を発揮している姿かもしれない。
NIRA(総合研究開発機構)研究報告書(平成17年3月)
『逆都市化時代の都市・地域政策 -多様性と自立性の恢復による地域再生への途-』
第3章 逆都市化時代の都市・地域政策の基本的方向
第3節 地方都市とTOD(TransitOrientedDesign公共交通重視の都市政策)
-自動車へ過度に依存した交通体系からの脱却を目指して-
阿部 等(NPO法人交通ビジネス研究会)
1.はじめに
自動車は好きな時にドア・ツー・ドアの移動ができ、渋滞に巻込まれずかつ駐車場所にも困らなければ、非常に便利で快適な交通手段であり、また先進国では一般国民でも充分に費用負担可能になっている。
しかし一方、道路渋滞・エネルギー問題・環境問題・交通事故・中心市街地衰退といった負の側面を持っている。
自動車は、低密度な交通ニーズには相応しいが、密度がある値を超えると最適の交通システムではないにも関わらず、他のより相応しい交通システムが不便なために自動車が使われるケースが多い。
多くの人は、京都議定書も発効され、現代社会の生活は自動車へ依存し過ぎだと少なからず思い、「大気汚染や地球温暖化の問題解決にはクルマの利用を控えるべき」と考えていようが、「自分や家族の生活水準は落したくない」というのが本音だろう。
また、全国の自治体で実施される「ノーマイカーデー」といった取組みは、残念ながら大きな成果をあげられていない。
単にクルマ利用を控えることを呼びかけるのでは、「ノーマイカーデー」=「不便な生活を我慢する日」となり、多くの市民の賛同・参加を得られないからである。
そこで本報では、「自動車へ過度に依存した交通体系」の問題点とそれに至った原因を分析した上で、そこから脱却する方策として、利便性高く外部不経済も含めて社会全体にとって低コストの交通サービスを、市場機構の活用により実現することを提言する。
以下、話を単純化して論点を明確にするため、バスその他の議論はあえて省略し、「鉄道対自動車」の構図とする。
「鉄道」と称しているものは「公共交通」全般を指すとお考え願いたい。
また、旅客交通に関する議論のみに注力するが、貨物交通に関しても同様の議論が当てはまる。
2.自動車へ過度に依存した交通体系の問題点
(1)空間利用の非効率性
ここ数十年、人類は世界の多くの都市において、渋滞対策で道路を大量建設しても自動車の増大がそれを上回り、渋滞は一向に解消されないことを経験して来た。
駐車場不足に関しても同様である。
道路と駐車場の万全な整備により自動車で常にスムーズに移動できるようになるというのは幻想であることを、既に世界の全大都市で証明済みである。
原因は、自動車の空間利用の効率性が極めて悪いことである。
例えば、信濃町・千駄ヶ谷付近はJR中央快速線・緩行線と首都高速4号新宿線が並行しているが、朝ラッシュ都心方向の両者の輸送能力を比較してみる。
前者は複々線、後者は4車線で用地幅はほぼ等しい。
1時間当り通過人員は、前者は15万人以上、後者は仮に全車両を自家用車として環状線合流部での道路容量の上限台数が通過したとして3,000人以下で、同じ用地幅で50倍以上の輸送能力差である。
さらに、道路を大量建設すると、都心に到達した車両の駐車用に超高層駐車場ビルが林立することとなる。
また、ハイウェイの発達で有名なロサンゼルスは、都市圏人口は東京の3分の1とはるかに低密度だが、都市面積の3分の1を道路、3分の1を駐車場とし、残り3分の1のみで人間が活動するようにしても、渋滞と駐車場不足で苦悩している。
一方、モータリゼーションの進展に伴い、多くの都市ではバイパスや環状道路沿いへの公共施設・企業・商店・住宅の集積が高まり、中心市街地は駐車場を確保できずに空洞化が進んでいる。
メインの商店街の通りが「シャッター通り」と称されている都市さえある。
(2)エネルギー利用の非効率性
自動車は、以下の3つの理由で鉄道と比較してエネルギー利用効率が圧倒的に悪く、エネルギーを大量に消費する。
第1に、輸送単位が小さい。
移動人員1人当りの移動具重量は、例えば、1.3tのマイカーに1.3人乗車で1.0t/人に対し27tの電車に90人乗車で0.3t/人と、数倍の違いがある。
第2に、走行抵抗が大きい。
自動車のゴムタイヤ・アスファルトの組合せは、鉄道の鉄車輪・鉄レールの組合せと比べて転がり抵抗が数倍大きい。
例えば、自動車はアクセルから足を離すと、エンジンブレーキが効かないようにクラッチを切っても瞬く間に減速するが、鉄道はモーターを切ってもあまり減速しない。
第3に、動力源が異なる。
自動車は燃料と内燃機関を運搬具に搭載するのに対し、鉄道は外部からエネルギーを供給されてモーター駆動し回生ブレーキも活用できる。
後者の方が、エネルギー利用効率を上げるのに圧倒的に優位である。
ハイブリッド自動車は、大容量バッテリーを積んで回生ブレーキによりエネルギー効率を上げるものだが、鉄道の方がスケールメリットが効き相対的に優位であることは変わらない。
(3)環境負荷の大きさ
自動車は、小型内燃機関による駆動力を利用するため有害物質除去対策にコストがかさみ、単位エネルギー消費当りの環境負荷が大きい。
電気エネルギーによる鉄道は、走行の場でなくエネルギー源の上流である発電所で有害物質を排出しているが、スケールメリットがあるため、自動車より有害物質除去レベルが圧倒的に高い。
さらに自動車は、鉄道と比べて輸送人キロ当りのエネルギー消費が多いことと相まって、輸送人キロ当りの環境負荷が極めて大きい。
自動車は大気汚染及び地球環境問題の主原因の1つであり、中国やインドやアフリカの人々が本格的に自動車を使い始める前に、「自動車へ過度に依存した交通体系」から脱却する処方箋を人類が描けねば、地球は環境問題とエネルギー問題で壊滅しよう。
(4)交通事故の頻発
自動車は、ドライバーの注意力に頼った運転操縦を前提としており、車間距離保持・車線変更・信号順守等に関してドライバーのエラーを補完するバックアップシステムはほとんどない。
ITSにより若干のバックアップシステムの開発は進みつつあるが、鉄道と同レベルの安全度にするには膨大なコストを要する。
少なからぬ確率で交通事故が発生するのは当然の帰結であり、日本国内のみで毎年1万人の死者と100万人のけが人を発生させている。
ドア・ツー・ドアの平均速度で都市内40km/h、都市圏内80km/h、都市間150km/hを自動車で実現するには、膨大な安全投資を必要とする。
一方、鉄道を主軸とすれば、はるかに少ないコストで実現できる技術的可能性がある。
3.自動車へ過度に依存した交通体系となった原因
(1)自動車の技術革新と鉄道の停滞
自動車の生産・販売分野は、企業間の自由競争が続き、技術革新により顧客支持を得られた企業のみが生き残り、機能向上と価格低下が次々と進んだ。
そして先進国においては、富裕層のみならず国民全体が自動車を保有できるようになり、その波が中進国や発展途上国にまで達しつつある。
もし仮に、自動車の生産・販売は公共性が高いという理由で、政府による参入規制と価格統制をしていたらどのような結果になっただろうか。
特に低価格の価格統制をし、かつ財政難を理由に公的補助もしなければ、社会全体で自動車業界へのヒト・モノ・カネの投入が進まず、国民全体が自動車を保有することも、自動車業界が隆盛することもなかっただろう。
一方、鉄道は、いわゆる規制産業で競争環境になく、顧客志向と進取の気性を欠きがちである。
また、通勤・通学定期を中心に低価格の価格統制がされ、かつ財政難を理由に公的補助も少ないため、社会全体で鉄道業界へのヒト・モノ・カネの投入が抑制されている。
JR・公営地下鉄・大手民鉄・地方鉄道いずれを利用しても、サービスの悪さにしばしば辟易する。
あるいは、多くの人は鉄道の利用を全く考えず、自動車のみを利用する。
速達性・着席サービス・運転頻度・末端交通との接続性その他、鉄道は技術的に実現可能なレベルと比較して低レベルのサービスしか実現できていない。
(2)道路の大量建設と鉄道の財源不足
道路の建設財源は、道路特定財源制度と有料道路制度という巧妙な仕組みにより、「便利に自動車を使いたいという社会のニーズ」=「利用者の費用支払い意思」を取りまとめられ、潤沢に確保され、道路の大量建設が進んだ。
もし仮に、道路の建設は公共性が高いという理由で、道路利用者から税金や料金という形で徴収せず、一般財源からの投入のみとしていたらどのような結果になっただろうか。
毎年10兆円以上、国民1人当り約10万円が投入されていたとは到底考えられず、これほどの道路建設は進まなかっただろう。
一方、鉄道は、交通事業者が価格決定権を与えられておらず、低運賃たるべしという社会的圧力が強く、「便利に鉄道を使いたいという社会のニーズ」=「利用者の費用支払い意思」を取りまとめられず、良質なサービスを実現する財源を確保できずにいる。
鉄道運賃は自動車と比較して決して安くないという感覚が強いだろうが、それは利用時に固定費と変動費を同時に負担するからである。
一方、自動車はガソリン代・高速代・出先の駐車場代くらいの変動費しか通常は意識されず、鉄道と比較しての割安感があるが、実際は車両購入費・車検代・保険代・保管の駐車場代等の固定費が隠れており、通常意識されるコストの10倍くらいのコストを要している。
人類は、分業しながら共同生活を営む上で、“貨幣”という非常に便利なツールを発明した。
商品やサービスに対するニーズの強さは、人々の支払い意思の集積によって示され、それに応じて労働力・土地・エネルギー・各種資源といった経済学で言う“資源”が社会的に配分される。
“貨幣”がそれを調整する。
低価格による販売を強いられ、かつそれを補填する公的補助がされねば、資源配分が社会的に望ましい水準より低くなる。
「鉄道対自動車」という構図の中で、前者のみが資源配分を低められた結果が「自動車へ過度に依存した交通体系」である。
(3)自動車は費用負担を逃れ、鉄道は相対的不利に
さらに自動車は、排ガスや騒音による環境負荷をユーザーが負担していない。
つまり、自動車利用者は他者の迷惑の上に利便性を享受し、道路運送事業者は他者の迷惑の上に事業を営んでいるのである。
しかし日本は法治国家であるから、法律等で定められた排ガス規制を守っている個々の自動車利用者は責められない。
一方、鉄道は、環境負荷がはるかに低く、ユーザーが負担していない度合いは自動車と比べて非常に少ない。
また現在、自動車の用に供している道路空間の大部分は、有史以来蓄積された公共空間の多くを自動車向けに転用したものであり、自動車利用者の負担によらずに確保されている。
また、都市高速道路の多くは、河川敷や旧運河の空間に建設されている。
既成市街地で独自に用地確保しようと思ったら天文学的コストを要するが、それも自動車利用者は負担していない。
また、道路建設財源の相当割合は道路特定財源制度と有料道路制度により確保され、その部分は受益者負担と言えるが、それ以外に一般財源も投入されている。
以上の議論は、宇沢弘文氏の『自動車の社会的費用』により多くの人に知られるところとなったが、その他に直接的費用を負担していないことに多くの人は気付いていない。
地方では、公共施設も民間店舗も無料駐車場のあるところが多く、また2000円以上買物すると駐車場代2時間分無料といったサービスが多い。
駐車場コストは実際には相当を要し、税金で賄われているか、自動車以外の来訪者の買物代金に含まれているのである。
特に公共施設の無料駐車場というのは、民間のラーメン屋の店先で官が無料のソバを配給するようなもので、鉄道・バス事業者に対する民業圧迫である。
有料化には反対が強かろうが、「自動車へ過度に依存した社会」から脱却するには、ぜひとも実行するかあるいは鉄道・バスによる来訪者に駐車場コストと同額の補助をすべきである。
以上いくつもの理由から、鉄道は、不当に価格競争力で不利となっている。
鉄道の方が短時間で行けるが、自動車の方が安いので自動車を使うというケースの多くは、自動車が本来の費用負担をするようになれば、鉄道に転換しよう。
4.自動車へ過度に依存した交通体系からの脱却
(1)交通システムの所有から利用へ
交通は、政治・行政・業界・学界・マスコミいずれにおいても、習慣的に「私的交通」と「公共交通」に区分されている。
しかしこの区分は合理性を欠き、「私的交通」=自由な価格設定、事故は自己責任、「公共交通」=低運賃、コスト度外視の安全至上主義といった考えをもたらし、交通問題解決の処方箋を見えなくさせているのではないだろうか。
あえて交通を区分するなら、「個別交通」と「共用・集約交通」に区分するのが良い。
交通ニーズが低密度であれば「個別交通」、高密度であれば「共用・集約交通」が効率的である。
高密度な都市部において、マイカーのように個人が交通手段を所有・管理することは、社会的には極めて不経済である。
ビルの中で、エレベータの待ち時間が長く速度が遅いことに我慢できない多くの人が、移動及び保管ともに大きなスペースを要する内燃機関付き移動具を持ったらどうなるだろうか。
執務やコミュニケーションの場が取れなくなり、皆が排ガスに苦しみ、費用負担も膨大になろう。
高密度地域では、1人1人が「個別交通」システムを「所有」するのでなく、皆で「共有」さらには移動ニーズを「集約」して処理した方が全員の幸せとなる。
皆が、その支払い意思に応じて、あるいは後述する「社会的互助制度」により、「共用・集約交通」システムを便利に「利用」できる社会を実現したいものである。
(2)公的補助による公共交通充実の問題点
多くの立場の人が、旧来の区分による「公共交通」を充実させるために公的補助の実施を主張し、実際に様々な補助制度がある。
しかし、公的補助を受けている交通事業者は、モラルハザードとなり顧客志向と創意工夫に欠け低サービス・高コスト体質となっている例も数限りない。
また、緊縮財政のなか、「自動車へ過度に依存した交通体系」から脱却するに足る財源を確保することは容易でない。
筆者は、交通事業者への公的補助へは基本的に反対である。
交通事業者の収入は公的補助の多寡により決し、交通事業者の存続・発展が、提供するサービスの良質さでなく官への取込み度によることとなるからである。
(3)自由な民間活動による共用・集約交通の充実
通常の業界では、企業間の自由競争を通し顧客支持を得られた企業のみが生き残り、進取の気性や技術革新により良質で低額な商品やサービスが社会的に提供される。
一方、古典的な経済学の教科書によると、交通産業は、サービスの生産費用が逓減し自然独占となる「市場の失敗」があることから、企業間の自由競争に任せず、政府が参入規制と価格統制を行うことが社会厚生を最大化するには不可欠だとされている。
しかし現実の世の中を見ると、「市場の失敗」より「政府の失敗」の方が大きいように思える。
交通事業者へ価格設定権を与えることにより資源配分が適正になされ、また自由競争を通して民間活力が発揮され、社会的に必要な設備投資とサービスの提供が低コストで実現されることが望ましい。
すなわち、交通ニーズの特性とその時代に人類が獲得した技術レベルに応じて、鉄道・自動車・航空・船舶・自転車・徒歩・路面電車・タクシー・バス&ライド・パーク&ライド・キス&ライド・レンタカー・カーシェアリング・レンタサイクル・動く歩道といった様々な交通システムの中で最適のものが実現され、社会厚生を最大化するようにしたい。
公共交通事業を参入規制と価格統制で制御しようというのは社会主義発想であり、最適な交通システムは政府でなく市場が決すべきである。
全ての交通ニーズが、ましてや出発から到着までの全区間の移動が、鉄道を中心とした共用・集約交通システムのみにより達成される必要もないし、べきでもない。
しかし、市場機構を活用して鉄道に対して民の自由な企業活動を認めれば、そのシェアは高まり、「自動車へ過度に依存した交通体系」からの脱却が進み、社会的に望ましい結果になると信じる。
(4)民間活力の源泉は収益、収益は社会貢献の証し
自動車産業が大発展し、社会に利便性高く低価格な自動車が供給されるようになったのは、事業の成功者へ巨万の富を認めたことがその大きな理由である。
鉄道事業の成功者にも巨万の富を認めれば、かつてのアメリカの鉄道王時代、あるいは日本の明治末期から戦前のように、鉄道は本来の能力を発揮できるようになろう。
“民でできることは民に!
”、“努力した者が報われる社会に!
”というスローガンが各所で言われるが、そのためには努力した“民”が収益を上げられる社会的仕組みにすることが必須である。
民間活力の源泉は収益である。
収益第一主義は日本の気風では潔しとされず嫌われるが、収益は社会への貢献の証しと見ることができる。
販売する商品やサービスが人々から選択され、社会に役立ってはじめて収益を上げることができる。
低サービス・高コストで赤字を垂れ流している時代遅れの鉄道を存続・延命さす方が、鉄道事業の成功者に巨万の富を認めるよりはるかに大きな社会的マイナスである。
(5)交通弱者へ公的補助し交通機関選択は任す
市場機構の活用とは言っても、通学者・高齢者・障害者等あるいは過疎地域といった交通弱者への配慮は当然すべきである。
ただし、それは民間企業ではなく政府の仕事である。
年代・貧富・健康・地理的条件等の差により相対的に恵まれた者の負担により交通弱者の費用負担を少なくする、すなわち交通における「社会的互助制度」を構築すべきという点に関しては、社会的合意を得られよう。
そして、その財源は民間企業の内部補助でなく公的補助とすべきである。
その際、交通事業者へ直接公的補助をするとモラルハザードの原因となり、時代遅れの交通システムを温存することになりかねないので、利用者へ交通バウチャーといった形で付与し、交通機関の選択は利用者へ任せる。
それにより、市場機構を通して場面毎に最適な交通システムが出現することになる
(6)提言のまとめ
市場機構を機能させなくしている現行の様々な歪みは、3.で述べた通りである。
それを改めるために政府がなすべきことは以下の3点である。
1)鉄道事業者へ利潤最大化の価格設定権を与える
2)自動車へ負担を逃れている全費用を負担さす
3)交通事業者でなく交通弱者へ公的補助をする
5.完全な市場機構活用の前段階の次善策
(1)次善策の提言
前項の提言は、理想解ではあっても現行の制度との乖離が大きく、社会的合意を容易に得られないだろう。
特に、自動車へ負担を逃れている全費用を負担さすことは、関係者にとっては死活問題で大反対が起きようし、また短期間に理想状態へ移行させると大不況や大失業を出現させることとなり、社会的にも決して好ましくない。
そこで、理想的状態の前段階の次善策として、鉄道事業者の意欲を引出して鉄道の利便性を向上させ、自動車利用のできるだけ多くを鉄道に転換させる方策を、現在の鉄道の選考度合いに応じて、以下に提言する。
必要により、鉄道事業者のモラルハザードをできるだけ招かない範囲で実質的な公的補助も行う。
自動車の利用を鉄道に転換させることのより、「自動車へ過度に依存した交通体系からの脱却」を図る。
(2)現在でも自動車より鉄道が選択されている領域
大都市圏の鉄道各路線に対して、利潤最大化の価格設定権を与えたら、どうなるだろうか。
例えば現行の運賃を2倍にしても利用者が半分に減ることはあり得ず、全体的に大幅に値上げされ、特に通勤・通学定期は需要の価格弾力性が小さいので、大幅に値上げされよう。
鉄道事業者の収益性は大幅に向上し、サービス改善のための経費投入も若干は増えようが、利用者負担が大幅に増え、社会的に望ましい結果とは言えない。
官による価格統制は残しつつ、鉄道事業者のサービス改善のインセンティブが働く運賃制度とするため、着席と立席での価格差別を提言する。
立席での輸送を基本運賃とし、着席に対しては割増運賃を設定する。
JR東日本の普通列車グリーン車のように、ITの活用により多大な人手を要さずに価格差別することが容易な時代となった。
基本運賃は現行運賃より安く、基本+割増運賃は現行運賃より高くし、現行の着席率で鉄道事業者の収益が増減しない水準で運賃認可する。
そうすれば、鉄道事業者はどの時間帯も提供座席数を増やすインセンティブが働く。
夜間に多くの旅客を立たせながら車両基地には大量の車両が留置、長距離利用の多い路線に立席主体の車両を投入などといったことはなくなろう。
鉄道事業者にとっては、同じ輸送人員でも提供座席数を増やせば平均客単価が向上して収益性が向上することとなり、商売としての“旨み”が生まれ活力が増す。
鉄道の利便性が向上し、自動車から鉄道への転換が進む。
(3)現在は鉄道より自動車が選択されている領域
大都市圏以外では、鉄道を独立採算で事業経営することは難しいと言われている。
鉄道事業者へ利潤最大化の価格設定権を与えず、かつ自動車が本来の費用負担を逃れているのであるから、公正な競争環境の下では事業経営が可能な領域における利便性の高い鉄道の実現の芽を摘んでいることになる。
交通弱者へ交通バウチャーを支給した上で、鉄道事業者へ利潤最大化の価格設定権を与えることを提言する。
それにより、相当の領域で鉄道が事業として成立して利便性の高い鉄道サービスが提供され、自動車からの利用転換が進もう。
さらに自動車へ本来の費用負担をさせるべきであるが、すぐには社会的合意がまとまらないだろうから、次善策として公正な競争環境に近付けるため、鉄道に政治的に実現可能な範囲の実質的な公的補助を与えることを提言する。
近年、土地と地上設備の保有主体と、列車の運行・営業主体を分ける「上下分離」方式が普及しつつある。
「下」は公的資金の投入も含めて公的セクターが担い、「上」は民間活力を発揮できるよう民間セクターが担う。
それを応用し、自治体等が「下」を保有して格安リース料で「上」会社へ賃貸し、「上」会社は良質なサービスの提