利益追求とCSR.docx
《利益追求とCSR.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《利益追求とCSR.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
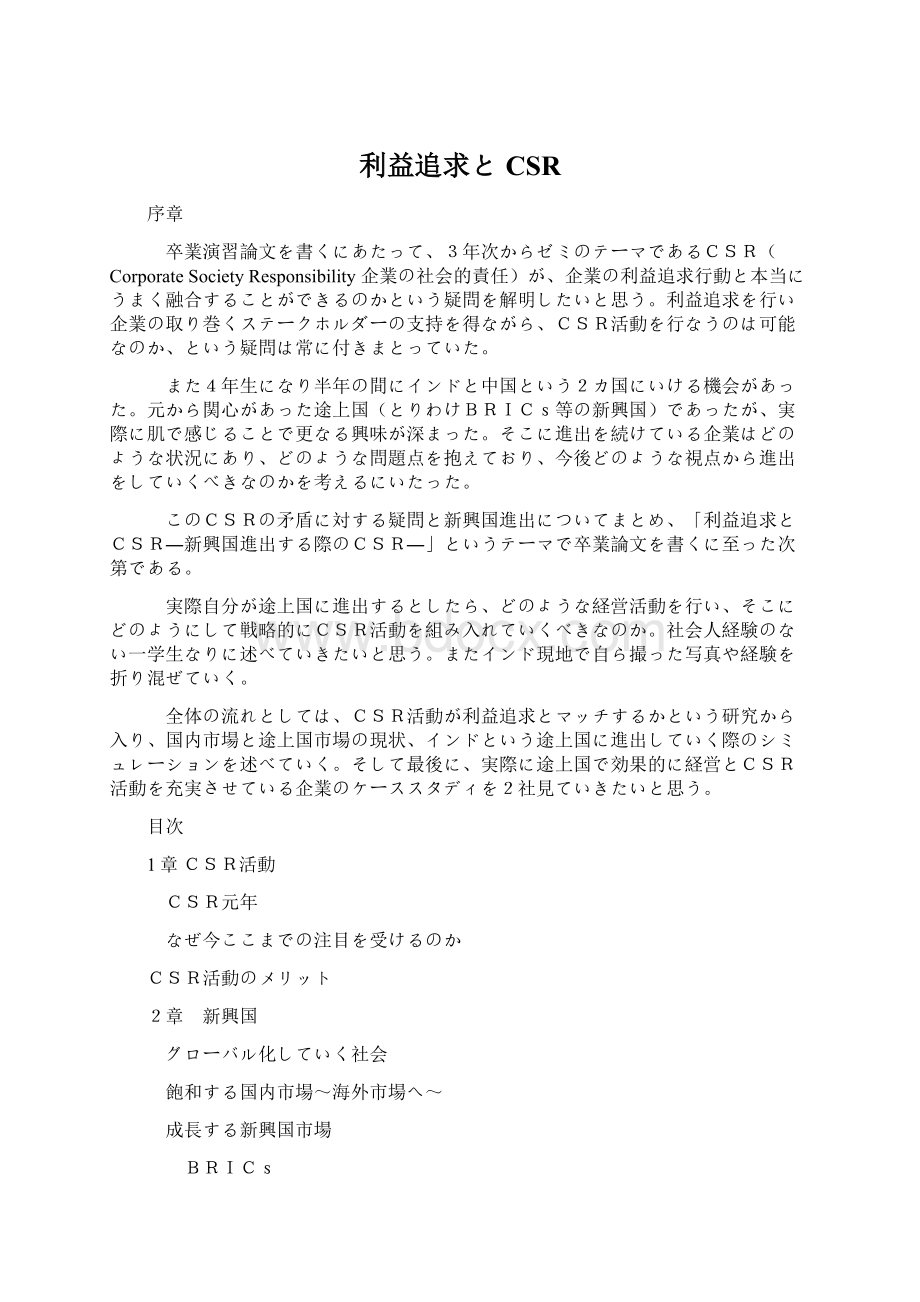
利益追求とCSR
序章
卒業演習論文を書くにあたって、3年次からゼミのテーマであるCSR(CorporateSocietyResponsibility企業の社会的責任)が、企業の利益追求行動と本当にうまく融合することができるのかという疑問を解明したいと思う。
利益追求を行い企業の取り巻くステークホルダーの支持を得ながら、CSR活動を行なうのは可能なのか、という疑問は常に付きまとっていた。
また4年生になり半年の間にインドと中国という2カ国にいける機会があった。
元から関心があった途上国(とりわけBRICs等の新興国)であったが、実際に肌で感じることで更なる興味が深まった。
そこに進出を続けている企業はどのような状況にあり、どのような問題点を抱えており、今後どのような視点から進出をしていくべきなのかを考えるにいたった。
このCSRの矛盾に対する疑問と新興国進出についてまとめ、「利益追求とCSR―新興国進出する際のCSR―」というテーマで卒業論文を書くに至った次第である。
実際自分が途上国に進出するとしたら、どのような経営活動を行い、そこにどのようにして戦略的にCSR活動を組み入れていくべきなのか。
社会人経験のない一学生なりに述べていきたいと思う。
またインド現地で自ら撮った写真や経験を折り混ぜていく。
全体の流れとしては、CSR活動が利益追求とマッチするかという研究から入り、国内市場と途上国市場の現状、インドという途上国に進出していく際のシミュレーションを述べていく。
そして最後に、実際に途上国で効果的に経営とCSR活動を充実させている企業のケーススタディを2社見ていきたいと思う。
目次
1章CSR活動
CSR元年
なぜ今ここまでの注目を受けるのか
CSR活動のメリット
2章 新興国
グローバル化していく社会
飽和する国内市場~海外市場へ~
成長する新興国市場
BRICs
NEXT11
BOPビジネス
3章 途上国進出シミュレーション
戦略的CSR活動の手順
STEP1 CSRの現状把握
STEP2 CSRビジョンの設定
STEP3 CSRを経営戦略に組み込む
STEP4 PDCAの仕組み、浸透・推進体制の整備
STEP5 コミュニケーションの戦略と仕組みを構築する
4章 ケーススタディ
デンソー
ヒンドゥスタン・ユニリーバ
5章 今後の進出
途上国進出の危険性
参考文献
1章CSR活動
・CSR元年
2003年はCSR元年とも言われる。
「CSR」という文字がマスコミに露出する回数がこの年を境に徐々に増え始め、2004年から爆発的に増えるに至った(2003年1月には3件であった記事数が2年後には61件まで膨れ上がった。
「日経テレコン調べ:
日経・日経産業・日経金融・朝日・毎日・読売・産業各新聞」)。
しかし、CSRの概念は決して最近できたもののわけではない。
企業が社会的責任を果たしていこう、という考えは国内外問わずして昔から存在していた。
日本国内を見てみても江戸時代に栄えた「近江商人」という現在の滋賀県の承認の商売の基本理念に、社会的責任と同じような内容のものが見ることができる。
「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」の理念である。
近江を本拠地として、全国各地の縁もゆかりもないような土地で行商をしていた彼らは、その土地の信頼を獲得するために自然とこの理念を持つようになったのだ。
この言葉を現代に当てはめて考えると「売り手=企業」、「買い手=顧客・消費者・取引先」、「世間=社会」とすることができる。
つまり、売り手と買い手が満足する「経営」をしながら、「社会」が満足しなくてはならない、というもので現代のCSRの概念と一致する。
このように3、4百年も昔から存在したCSRの概念が、なぜ今になって名前を変え、これほど社会からの注目を浴びているのであろうか?
・なぜ今注目されるのか?
野村総合研究所経営コンサルティング部、伊吹英子氏は、著書「CSR経営戦略」の中で、日本のCSR活動の現状として「待ちの姿勢」という言葉にて表現している。
昔からなんとなしにCSRの考え方はあれども、事業の課題を優先し、流行物には慎重に対応するといってCSR活動の規格化を待つ姿が日本の企業にはあるようだ。
そんな日本の受身の体質が近年多くの業種でおき続けている一連の不祥事を起こしてしまっている。
この機会にメディアがそういった現状を問題視していることが一つの理由なのではないだろうか。
とくに2000年におきた雪印の不祥事や同年の三菱自動車のリコール隠しなどは企業社会だけでなく、世間一般に対し大きなショックを与えた。
こうした流れも起因してか、企業を取り巻くステークホルダーの行動や要求も変化してきている。
株主・投資家行動の変化
社会的責任投資(SRI)が欧米を中心に拡大している。
社会の調和の取れた経営に対して積極的に投資をするようになって経営に対し投資家が直接的な影響を持つようになった。
株主行動も盛んになり積極的にCSRに関わる商品の開発などの要求を求めるようになってきた。
消費者行動の変化
メディアや近年の食品不祥事などの影響から、消費者の商品・サービスに対する目は厳しくなり、責任の果たせない企業への風当たりは一層強まっている。
米国の非営利組織、経済優先評議会(CEP)は消費者向けの企業の格付け冊子“ShoppingforaBetterWorld”を発行しており、現地消費者はこうした冊子を元に日ごろの購買行動の参考にしているようだ。
この冊子によって5人のうち4人が購買行動を変えているという。
取引先行動の変化
直接的に企業と取引を行なう取引先にも昔とは違った流れが見られ、その選択に「社会的要件を満たしているか」といったような条件を課している企業や自治体も増えているようである。
実際にコンプライアンスルールに違反した取引先との取引を停止するまで至るケースも近年の食品偽装の不祥事などに見られる。
こうした直接的なステークホルダーの他にもNPO・NGO団体、地域社会・住民、従業員、行政などがステークホルダーとして挙げられ、近年の流れから企業にCSR活動を求める行動への変化は見られる。
メディアのCSR活動への報道の活発化に加えその流れに影響を受けた企業以外の各集団の動きの変化も、企業のCSR活動の要請の流れに拍車をかけているようである。
・CSR活動のメリット
このように注目度が熱くなるCSRであるが、最近のCMなどで紹介される活動は植林活動や障害者支援、芸術活動支援などといったものが多い。
こういった活動を見ていると実際にそれが経営に生かされているのだろうかという疑問が残る。
またこうした活動はするだけでも多くの人的・資金的費用がかさむはずである。
特に海外の社会問題に対する支援やインフラ整備などというケースではその費用も莫大となるはずである。
それにたいする費用対効果は期待できるのであろうか?
企業のCSR活動のメリットとして一般的に挙げられるものとしては
・社会的信頼の確保
・株主・投資家からの支援
・経営リスクの軽減
などが挙げられる。
しかし、こうしたものは決して数字として現れるものではなく、ただ曖昧なものとして存在している。
もし企業がこうした曖昧なメリットを目標として掲げているとすれば、それは伊吹氏のいう「待ちの姿勢」の時代の流れに乗っただけのCSRなのかもしれない。
CSR活動の大きなメリットの一つとして経済産業省勤務の藤井敏彦氏は「社会の要請」を読むチャンスであることを挙げている。
同氏はCSRの取り組みと事業戦略の一体化を考えるとき企業はその経営の中で「ゲームのルール」の中にあるという言葉で表現している。
このルールの中で企業は「市場の要請」と「社会の要請」という2つの波を乗り越えて進歩していくとたとえており、小さな「市場の要請」でなく大きな「社会の要請」の波を読んで進むことの重要性を説いている。
「市場の要請」とは例えば秋葉原の流行などのことで刻一刻と変化していく市場のニーズの変化のこと。
経済活動のマーケティングや市場調査などはこれの研究に当たるのかも知れない。
それに対し「社会の要請」とは調査などではなかなか見えてこない社会の変化に付随した要請であり、環境破壊が進んでつくられた家電リサイクル法や、プライバシーが叫ばれるようになりつくられた個人情報保護法などのものがこれに当たる。
藤井氏はいかにこの「社会の要請」をCSR活動の中で多くのステークホルダーから汲み取り、社会的イノベーションにつなげていくかという点の重要性を述べている。
CSR活動から多くのステークホルダーと接し、社会の流れをつかむ。
そこから新たに事業のビジョンの手がかりとして更なる発展を目指す。
そういった活動がCSR活動の一つの大きなメリットとなっている。
戦略的に計画を立てCSR活動をすることにより、売り上げの向上に役立てられ、今後の事業ビジョンを立てる手がかりともなる。
社会からのレピュテーションを上げるだけのものにはとどまらず、直接的にも財務的リターンの望めるポテンシャルを秘めた活動なのである。
今回は戦略的CSR活動を途上国進出の切り口から見ていきたい。
そのために次に途上国・新興国を見ていく。
2章新興国
・グローバル化していく社会
利用が研究機関や一部の大学に限られていたというインターネットの普及により国際的なコミュニケーションの速さも著しく上昇した。
また航空機など空の運送技術なども発達し国際間での人・物の移動自体手軽になった。
こうした流れから生産・金融にも世界化の波がある。
1993年にアメリカのフォード社が世界各地で生産した部品を組み立てたワールドカーを販売したのを皮切りに製造業の世界化は急速に進んだ。
日本のメーカーもアジアをはじめとする他国への工場移転が進み、その場で売る傾向もある。
金融に関してはネット取引の発達化などにより、一瞬で世界の株を売り買いできる世の中になり、原油価格・世界の株価は毎日めまぐるしく変動していうる。
外貨の売買も盛んで1日の取引高は1兆3千億に及び、1年の世界の貿易額よりも上回っている。
多国籍企業の数は増加を続け、1995年までの時点で3万8千社以上のこうした企業と25万以上の外国支店及び系列会社が存在しているといわれ近年のグローバル化の動きを考えると現在の数は計り知れない。
総売上げは5.2兆ドルと見積もられているが、これは世界貿易の総価値を上回り、また10年前の多国籍企業の売り上げの2倍に至っている。
・飽和する国内市場 ~海外市場へ~
一方で国内に目を向けてみると、人口減少、少子高齢化の局面を迎えており、国内市場の先行きは暗い。
人口は平成18年に12億7770万人なのに対し、100年後には4460万人まで減少し、65歳以上の人口構成比は現在20%であるのに対し100年後は40.6%とほぼ2倍となるに見込みである。
(総務省調べ)
人口が減り、労働生産世代も減れば勿論市場としての活力は減り、国内市場は縮小する一方である。
規模の拡大は見込めず飽和状態となっている。
そんな中大企業だけでなく内需型業種や中小企業も積極的に海外に販売を進めていく流れすら生まれてきている。
日本貿易振興機構であるJETROが2008年4月~5月に行なった「日本企業の世界消費市場戦略に関するアンケート調査」の結果によると回答企業の9割が海外での販売拡大を考えており、また海外販売を「現在行なっていないが今後行なう計画・可能性がある」と答えたのは大企業が2%であるのに対し、中小企業が16%という結果にあった。
海外での販売活動の理由としても1位が「新興国市場の成長性に期待」で55%、2位が「国内市場が成熟・飽和しているから」で51%(複数回答可)となっており、いかに国内市場が飽和していることで大企業だけでなく中小企業でさえ今後海外(特に新興国)に活路を見出していかなくてはならないかがわかる。
今後こうして海外進出していく中小企業はさらに増えていくと考えられる。
・成長する新興国市場
ではこの新興国とはどのようなものでどのような視点から成長が期待されているのであろうか。
BRICsとNEXT11についてみていきたい。
BRICs
写真1 インドのコルカタのマーケットにて
とにかく人が多く活気がある。
彼らが経済的に豊かになり、大量の物を消費したら、と考えると多くのメリットと問題点を感じた。
上のJETROの調査でも出てきたように、海外進出として今注目を浴びているのが急速に成長している新興国だ。
中でもBRICs(B:
ブラジル、R:
ロシア、I:
インド、C:
中国)と呼ばれる4つの新興国は今ではなじみ深い。
2003年に米国最大の投資銀行ゴールドマン・サックスが報告書の中でこのBRICsという言葉を使い今後のこれらの成長に関して焦点を当てた。
それ以後メディアからのBRICsという言葉はたびたび使われ、世界から注目を浴びている。
先程紹介したJETROの調査の中でも現在重視している海外市場の質問に対しては1位中国52%、2位米国32%、3位インド25%、4位タイ22%、5位ロシア20%であった。
BRICsの中でも日本企業からは距離などで取引に難のあるブラジルですら9位につけた。
いかにBRICsの4カ国への重要度が高いかがわかる。
写真2 TATA製のバスの連なり
2008年10万ルピー(約25万円)の新車nanoを発表したTATAモーターズだが、インドの町を走るのは乗用車、バスからトラックまで同社のものばかりだった。
この中でも一番成長の潜在性を有しているといわれるのが11億という世界2位の人口を誇るインドである。
実際現地に行って見てもその人口が持つダイナミクスと活気が伝わってくる。
ニューデリーの中心部以外の都市化はさほど進んでいないが、どこへ行けども人と車にあふれ、消費市場としてのポテンシャルを大きく感じた。
(写真1)地元の財閥であるTATAグループの成長もこの国の成長を支えている。
中でも街中を走る自動車のほとんどがTATAモーターズ製であり(写真2)、同社を中心としたこの産業の技術の急成長が世界の自動車企業の進出を促しているのではないだろうか。
無骨でもその市場の規模のダイナミックさ(国土・人口・資源など)を有する点がBRICs各国で共通する点といえる。
国名
人口
GDP(億$)
2005
2050
増加率
2005
2050
韓国
4,780
4,463
-6.6
7,786
36,840
フィリピン
8,310
12,707
52.9
983
24,730
ベトナム
8,420
11,665
38.5
524
28,990
インドネシア
22,280
28,464
27.8
2,872
39,230
バングラディッシュ
14,180
24,293
71.3
600
12,600
パキスタン
15,790
30,470
93
1,107
22,870
イラン
6,590
10,194
54.7
1,963
22,510
トルコ
7,320
10,121
38.3
3,633
27,570
エジプト
7,400
12,592
70.2
893
24,610
ナイジェリア
13,150
25,810
96.3
990
37,080
メキシコ
10,700
13,902
29.9
7,684
78,380
NEXT11
表1 NEXT11の予想人口・GDP比較 (2005は実績)
アジア&ワールド協会より
BRICsの次に発展していく新たな新興国として挙げられている国々である。
またもゴールドマン・サックス社が2005年12月に経済予測レポート(「HowSolidaretheBRICs?
」)の中で紹介した。
今後健全な発展が期待できる国家軍として取り上げた「新興経済発展国家群」といわれる。
具体的には韓国、フィリピン、ベトナム、インドネシア、バングラディッシュ、パキスタン、イラン、トルコ、エジプト、ナイジェリア、メキシコの11国が挙げられている。
BRICsのように大きな国土や人口、豊富な資源といった共通点があるわけではないが、人口やGDPの成長性を見ていくと大変魅力的である。
今後の投資等を考えると大きな市場になる可能性を有している。
(表1)
・BOPビジネス
そんな新興国、途上国に対してBOPビジネスという1つのCSR活動につながる概念が存在する。
米ミシガン大学教授のC.K.プラハラード氏が著書「ネクスト・マーケット」の中で、1日2ドル以下で暮らす貧困層のことを”BottomofthePyramid”(BOP)と呼んだことがきっかけである。
日本だけに限らず市場が飽和していく先進国が海外に目を向けて、右図の貧困層である40億人を大きな市場としてとらえるビジネスプランである。
C.K.プラハラードはこのことを「貧困層が自ら選択し、自尊心をやしなう機会を創り出す」と表現している。
つまり、こうした貧困層に対して彼らが抱えている問題や課題を解決に協力することで、経済的・社会的に楽にさせ市場を開拓していくというものである。
途上国の貧困層に対し企業が援助、開発などをし、貧困層から自社製品の消費者へと変えていく。
「ちりも積もれば山となる」ではないが、40億もの貧困層が積極的な消費者へと変わればそのビジネスチャンスは果てしない。
といえど、貧困層の市場とは本当にそこまで大きくなるものなのであろうか。
世界銀行グループの国際金融公社(IFC:
InternationalFinanceCorporation)と世界資源研究所(WRI:
WorldResourceInstitute)から出されたBOP市場についての詳しい報告書である“TheNext4Billion”を見ていった。
産業別のデータを見ていくと、1位の食品分野では2兆8950億ドルになり、エネルギー分野(4330億ドル)、住宅分野(3320億ドル)と続く。
また急成長中の情報通信分野は510億ドルにとどまっていたが、調査時点からの伸びにより現在では約2倍という予想がある。
いずれも莫大なものであり、BOP市場は生活必需産業だけでなく、情報分野まで成長を続けていることがわかる。
地域別での市場規模も下図のようになっており、アジア・東ヨーロッパ・ラテンアメリカ・アフリカをあわせてみると4兆8660億ドルの市場となった。
いかにこの市場規模が莫大なのかがわかる。
しかも今後さらに成長を続けていくことを考えるとそのビジネスチャンスは計り知れない。
BOP層人数
総所得額
アジア
28億6000万人
3兆4700億ドル
東ヨーロッパ
2億5400万人
4580億ドル
ラテンアメリカ
3億6000万人
5090億ドル
アフリカ
4億8600万人
4290億ドル
地域別のBOP市場規模
産業別のBOP市場規模
市場規模
水道
200億ドル
情報通信技術(ICT)
510億ドル
保険医療分野
1580億ドル
運輸
1790億ドル
住宅
3320億ドル
エネルギー
4330億ドル
食品
2兆8950億ドル
“TheNext4Billion”より
こんなBOP層であるがその貧困の理由としてBOPペナルティというものがある。
貧困であるがゆえにその市場アクセスの乏しさ、金融サービスのアクセスの乏しさから一般の人よりも多い支出を余儀なくされているのである。
例としては次のようなものがある。
BOPペナルティ例1
BOP層の大半は銀行口座を持たず、現代的な金融サービスへのアクセスもありません。
もしお金を借りる場合でも、地場の金貸しから非常に高い利息で借りるのが典型的。
大半は電話もありません。
“TheNext4Billion”、”アジアのCSRと日本のCSR”
BOPペナルティ例2
BOP層の多くはフォーマル経済に十部統合されることなく、経済的機会も限られています。
生産者として自らの労働力や手工業製品や作物を売るための市場へのアクセスが十分でなく、彼らを搾取する地元の雇用主や仲介人に売るほかに選択の余地がありません。
“TheNext4Billion”、”アジアのCSRと日本のCSR”
BOPペナルティを生むようなこうした社会的課題に取り組み、少しでもBOP層の状況を改善させ負担を軽減させることで、BOPビジネスとしての可能性の拡大へと向かっていく。
このような貧困層への取り組み、途上国への進出がBOPビジネスとしてマーケティングの一つとしてC.K.プラハラード氏により提唱され一つの話題を生んだ。
こうして飽和した先進国は途上国、新興国に進出しビジネスチャンスをつかんでいく流れにありその市場をいかに戦略的に開拓していくかが鍵となっている。
その戦略にCSRの概念を積極的に取り入れていくことが必要となっていく。
では実際進出していく際にどのような手順でCSR活動に取り組んでいくべきなのであろうか。
3章途上国進出シミュレーション
・戦略的CSR活動の手順
CSR活動を行なう際のステップはいくつか紹介されているものがある。
例えばトーマツCSRグループ(白潟敏郎氏、青木茂男氏、北島隆次氏)が推奨する中長期ビジョンに基づいた推進コースは、事前準備フェーズ⇒SSP作成フェーズ⇒実行フェーズ⇒評価・情報公開フェーズに分けたものである。
まず全社的推進体制を整備してからPDCAを実行していくというものだ。
ちなみにSSPとはStakeholderSatisfactionPlanningのことで、CSR中長期ビジョンの方針・目標を設定するものでPDCAのPに当たるものである。
また、それとは別に前出の野村総合研究所、伊吹英子氏はCSR活動を右図のような5ステップの手順で行なうことを推奨している。
自社の強みを生かし競争力へとつなげるような効果的なCSR活動を行なう方法としてより戦略的な視点から手順を紹介している。
「待ちの姿勢」に対する攻めのCSRとして、今後の多くの国に進出していく日本企業が必要とするステップなのではないだろうか。
今回はこの手順に従って実際に海外進出する際のCSR活動のシミュレーションをしてみた。
モデルとしては実際訪れることができたインドへの自動車組み立てメーカーの進出。
具体的には国内市場の飽和を感じ、将来の消費国として見込みのあるインドの市場に進出する自動車組み立てメーカー(架空)とする。
自動車産業の伸びているインドで市場を開拓するのが目的。
現地企業や進出している日本自動車メーカーの組み立てを行なう。
一部自動車部品の製造も行なう。
海外進出は今回が初めてで手探りの状態。
STEP1 CSRの現状把握・課題抽出
・ガイドラインの選定
まず現状把握を行なうツールとしてCSRガイドラインが多く存在する。
CSRガイドラインとは様々な機関が多様な価値観に基づき設定したものでガイドラインの類型として大きく「マネジメント規格」「情報開示ガイドライン」「社会的責任投資評価インデックス」「CSR行動原則・規範」の4類型に分けることができる。
今回は、海外での初のCSR活動ということもあり、多くの日本企業から採用されている情報開示ガイドラインとして「GRIガイドライン」を選択する。
このGRIガイドラインは国際基準とも活用されており、2007年では全体