日本大学の教育にあたえたバブル経済の影响.docx
《日本大学の教育にあたえたバブル経済の影响.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《日本大学の教育にあたえたバブル経済の影响.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
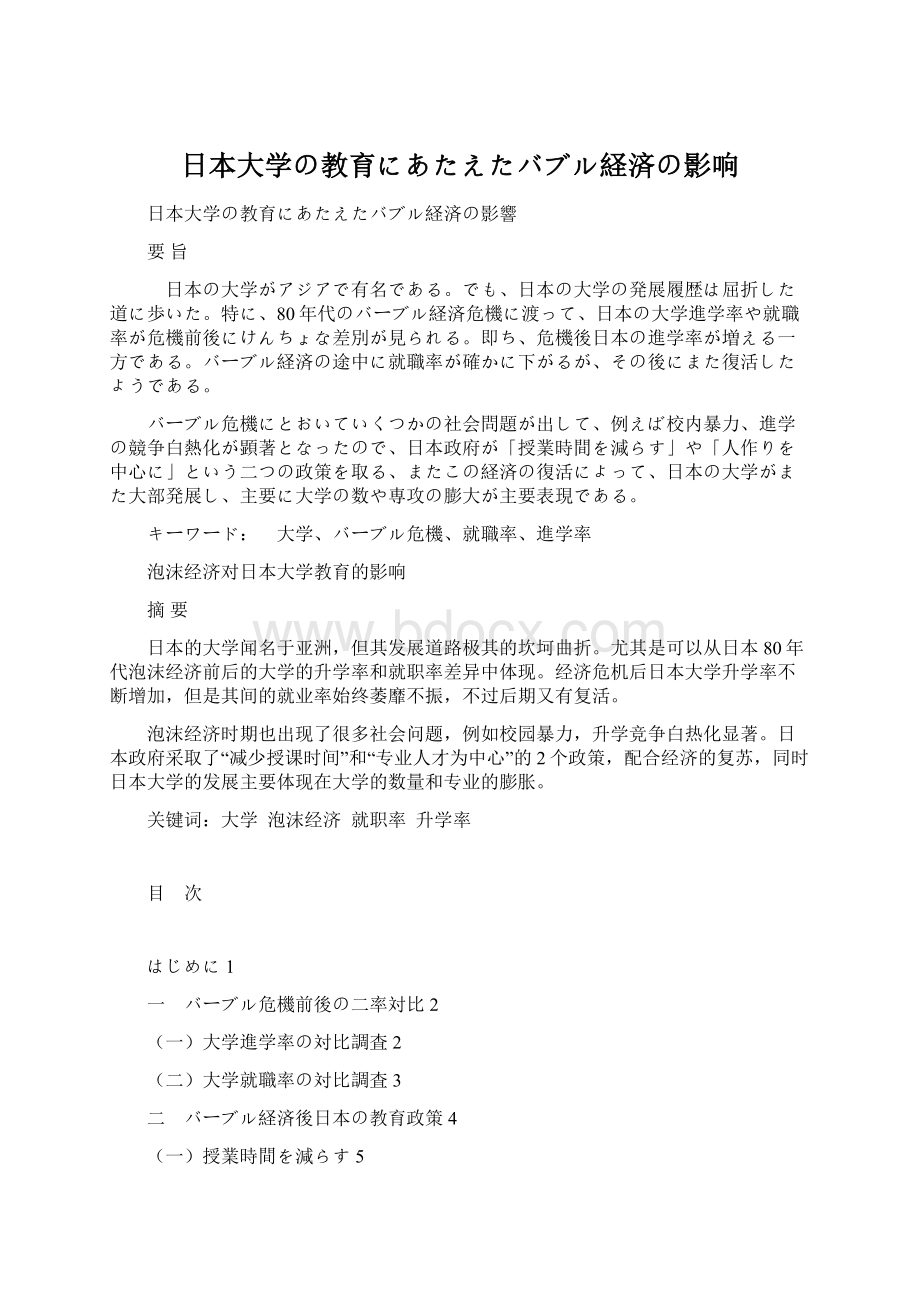
日本大学の教育にあたえたバブル経済の影响
日本大学の教育にあたえたバブル経済の影響
要旨
日本の大学がアジアで有名である。
でも、日本の大学の発展履歴は屈折した道に歩いた。
特に、80年代のバーブル経済危機に渡って、日本の大学進学率や就職率が危機前後にけんちょな差別が見られる。
即ち、危機後日本の進学率が増える一方である。
バーブル経済の途中に就職率が確かに下がるが、その後にまた復活したようである。
バーブル危機にとおいていくつかの社会問題が出して、例えば校内暴力、進学の競争白熱化が顕著となったので、日本政府が「授業時間を減らす」や「人作りを中心に」という二つの政策を取る、またこの経済の復活によって、日本の大学がまた大部発展し、主要に大学の数や専攻の膨大が主要表現である。
キーワード:
大学、バーブル危機、就職率、進学率
泡沫经济对日本大学教育的影响
摘要
日本的大学闻名于亚洲,但其发展道路极其的坎坷曲折。
尤其是可以从日本80年代泡沫经济前后的大学的升学率和就职率差异中体现。
经济危机后日本大学升学率不断增加,但是其间的就业率始终萎靡不振,不过后期又有复活。
泡沫经济时期也出现了很多社会问题,例如校园暴力,升学竞争白热化显著。
日本政府采取了“减少授课时间”和“专业人才为中心”的2个政策,配合经济的复苏,同时日本大学的发展主要体现在大学的数量和专业的膨胀。
关键词:
大学泡沫经济就职率升学率
目 次
はじめに1
一 バーブル危機前後の二率対比2
(一)大学進学率の対比調査2
(二)大学就職率の対比調査3
二 バーブル経済後日本の教育政策4
(一)授業時間を減らす5
(二)人づくり中心へ6
(三)財政支持の増加7
三 経済回復後大学の発展9
(一)大学数量の増長9
(二)大学専攻の膨大9
おわりに11
参考文献12
インタネット資源13
謝 辞14
はじめに
近代のいう大学が日本につくられたのは明治時代であった。
徳川時代に、幕府が、語学を軸に西洋の文物を学ぶ開成所と西洋医術を学ぶ医学所を設置していたが、それを明治政府が、東京開成学校、東京医学校とし、それらを合併した法理文医4学部を備えた東京大学が1877年に日本初の大学として誕生した。
1886年の帝国大学令によって東京大学は「東京帝国大学」となる。
明治初年の開成学校が、貢進生として全国の藩から学生を集めたように、帝国大学も優秀な学生を集めるために、多くを官費給費生として遇した。
明治維新で没落し、薩長閥といった強力なコネのない士族や、平民にとって、帝国大学や師範学校、陸軍士官学校、海軍兵学校などの学校は、成功への階段であった。
外国語や科学技術、政治などの私塾を母体とする慶応義塾や、キリスト教主義の学校である同志社英学校や東京英和学校、専修学校、東京専門学校、明治法律学校、英吉利法律学校などの自由民権運動の影響を受けて設立された政治・法律の専門学校、京都、大阪、愛知、新潟、金沢、熊本、長崎などの府県立の医学校などが、私立、公立の学校として次々とつくられた。
これらは専門学校という区分であった、1918年の大学令によって帝国大学以外の学校も大学と認められるようになると、それら専門学校が学士授与権をもった大学へと昇格した。
しかし、大学への昇格基準の厳しさのために、1930年の官公私立大学総数は46に留まった。
しかし、日本の大学の発展途中に日本経済からの影響も軽視することが出来ないと思う。
特に、日本のバーブル経済期間に日本の就職率や進学率などが経済方面から多大な影響を受けられる、本論文はこの「二率」を土台に、日本のバーブル経済が大学への影響に興味を持ったので、研究したい。
また、バーブル経済以後は日本の大学はどの様に発展したのか、また日本政府はどの政策を取るのかは、まだ系統な研究はなかったので、本論文はこれらの問題点を持って研究を始めよう。
一バーブル危機前後の二率対比
(一)大学進学率の対比調査
先ずはバーブル危機前後の進学率について対比しよう。
大学進学率は1930年の4.3%から1980年の37%まで上昇したが、学部別に見ると、理工系、特に工学部学生の増加が著しいです。
10年ことに、大学生総数は2倍ぐらい上る、人文社会系の学生は2.2倍、工学部の学生は3.1倍、理学部の学生は2.6倍と、理系が文系を上回った。
さらに大学院では、文科系が2,000人から43,000人へと20.5倍に増えたのに対し、理・工学部では1,500人が2,3000人へと15.3倍以上に増えた。
でも、90年代初期のバーブル危機によって人数の増長は勢いが横ばいとなった。
でも、10年の回復によって日本の経済体系が建てなおした。
2010年まで、日本の進学率が61.8%までに上る。
以下の図を見てください。
図1 進学率調査
上述したのように、高校学生の総数進学率は70年代中期から横ばいの勢いが見られる。
理工学の増長率が留まらずに伸びる一方です。
特に重化学工業への産業転換が起こり、メーカーの多くは積極的に新技術の開発、導入により競争力を高めようとした。
そのための技術者の養成は時代の要請であり、大学の理・工学部はその技術者の輩出を担った。
このような産業界の需要もあり、また日進月歩の科学技術とそれがもたらす豊かさを目の当たりにしている若者の中には、理系学部へと進学するものが多かった。
文史学の伸びるがバーブル危機から回復したあとに見られる。
でも、文史方面の学生がの基数が低いで、倍率は高いです。
70年代までに、一歩一歩に伸び上げる、でも、バーブル危機から回復した後の増長率が大幅に伸びる全部が60%以上に上がる。
(二)大学就職率の対比調査
1960年代の求人率の高さは、大学時点から積極的に採用活動を行う企業の増加に繋がり、「青田買い」としてメディアに大きく取り上げられた。
1973年のオイルショックによって高度成長がおわり、不況が訪れると就職率は70.7%と大きく下がった。
不況による求人率の低下に加え、大学の大衆化が長年続いたためもはや大卒の学歴は大きな意味をもたなくなってしまったとも考えられる。
1980年代は、日本が世界に先駆けて不景気から復興し、バブル経済へと突き進んでいく時代であった。
企業による活発な採用活動は、1960年代初頭の青田買いと似た様相を現し、説明会と称した接待や、内定の乱発が見られた。
企業の中には、学生の囲い込みのために内定を出し過ぎ、後に内定取り消し料を支払って取り消す「内定切り」を行うところや、学生で、内定をいくつももらって、どの企業に就職するか悩み、ノイローゼになる「内定病」といった特殊なケースも少なからず存在した。
このような状況の1980年代でも、就職率は75%~80%であり、1960年代の80%超を推移していた時期には及ばない。
改めて1960年代の就職率のよさが見て取れる。
それで、以下の就職推定図を見てください。
図2 就職率線
曾て有名一流大学といわれる大学の学生が、一人で内定を5、6つ簡単にとりが、「内定病」などが問題になった時代が終わり、「平成不況」「失われた10年」の不景気の時代が訪れ、「就職氷河期」「超氷河期」といった言葉が社会現象になる時代を経た現在の状況が、このような実学志向、無為無策な学生生活では就職してやっていけないという危機感を生み、大学生の変化をもたらしたと考えられる。
90年代初めに発生したバブル経済の崩壊は、深刻な需要の縮小とともに大量の不良債権の発生を通じた金融機能の低下により、日本の経済社会に深刻な影響をもたらした。
その影響は労働市場にも及ばして、それまで2パーセント台で安定的に推移していた失業率が一貫して上昇傾向をたどり、90年代後半には3パーセントを超え、2000年以降4パーセントを上回る水準にまで上昇した。
失業率の上昇はもっぱらバブル崩壊に伴う労働需要の縮小という、需要面からの景気変動要因による部分が大きいとみられる。
これに加えて、高齢化の進展により高齢者の賃金負担が増加する中でその分の費用調整が若年雇用に対する需要減という形で行われたこと、さらに、女性の社会進出が失業水準を押し上げる方向で寄与したことなどの供給要因も重なった。
本部分の統計したデーターから見れば、日本の進学率も、就職率も日本のバーブル経済危機が爆発したの期間に外部の影響を受けられるようである。
例えば、進学率は理工、文史総合にいえば、この期間に渋滞したのである、単なる理工方面はこのバーブル経済からの影響は文史より少ないということかい分かる。
特に影響を受けられるのは就職率である。
この方面は下降の勢いが顕示した。
特に、図2の顕示したのようで、1970年から1980年にかけて、就職率はぐんと下がった、だから、企業の人材使用は下がる。
二 バーブル経済後日本の教育政策
1980年頃からの高度経済成長が完全に終わった。
以前の高度経済成長政策の中で、教育内容が高度化になって、高学歴を求める学歴の競争が白熱化し、学校が荒れ、いじめや不登校の子どもが多くなって来た。
先生達の意識もバーブルの破裂直後に、熱心のあふれる先生はどんどん減らした。
このような中で、臨時教育審議会という首相直属の大規模な教育会議が開かれ、ここで「個性尊重」という今までの日本の画一的教育政策を変える方針がつくられました。
これが「ゆとり教育」の本格的出発点でした。
臨時教育会議の方針により、87年には、文部省は、より積極的にゆとり教育の必要性を説くようになりました。
子どもがゆったりと授業を受けられるように、教材内容を削減する方針を出しました。
事実、日本は当時他の先進国に比べて、小中学生の学習時間が飛び抜けて多かったのです。
文部省は、受験競争の緩和に着手していた。
しかし、90年代初めのバブル崩壊以後、日本社会は長い混迷期に突入しました。
その間に自民党が政権を手放さなければならなかった一時期もあったが短期間で終わり、また自民党支配の時代が続いて強力な教育政策は出された。
例えば、子供の圧力を緩和しようと授業時間の縮小、これがバーブル経済前後に顕著な対比が見られるし、人材培養の中心も転変したが、日本の教育への財政支出が増長した。
(一)授業時間を減らす
日本の教育の策略の転変が従業時間の変わることです。
調査によって従業時間の減らすが著しいです。
水木楊の調査書にだした数字を以下のような図を作った。
図3 授業時間
その結果、大学一年生の総授業時間数は、1960-1970年度の年間1085時間から、70-80年度の1015時間を経て、90年度には945時間と、30年の間に140時間も減少した。
また、主体的意欲や思考力を育てようとした「総合的な学習の時間」も導入されて、その分だけいわゆる「教科」の時間が減った。
日本語の授業時間を例に、1960-1970年度には245時間あった授業が、80年度の210時間、90年度の175時間へと、70時間も授業時間が減少した。
これらの策略をとって学生たちの圧力を減らすためのである。
即ち、日本の教育方向が実際の能力の育成に転変した。
授業時間が減らしたが、1998年、文部省はゆとり教育をさらに進めるため、教材、教育内容を大幅に精選した教育課程を採用した。
その後、文科省はゆとり教育に対応した多様な入試制度の改革や中高一貫教育の創設など、高等教育の多様化を急速に進めました。
2002年4月1日から、学校の完全週5日制が実施されることになり、年間授業日数は202日程度まで縮小した。
しかし、この2002年という年は、世界の学力比較調査で日本の大学生の学力水準が低くなっていることが明らかになり、世論の学力低下を心配する声がますます高まった時期で、だから、授業時間が減らしたが文科省は実質的に学習内容を増やし、高度化する方向に少しずつ転換し始めていた、即ち教育の内容が豊富となった。
80年代後半から日本が追求してきた「ゆとり教育」は、今までの画一化された詰め込み教育で、序列化され、意欲もなくなりがちな大部分の生徒に、従来の既成の価値観にとらわれない多様な選択肢を与え、社会体験を豊かにし、自主的で意欲的な子どもを多くしてゆこうというねらいでした。
80年代後半から日本が追求してきた「ゆとり教育」は、今までの画一化された詰め込み教育で、序列化され、意欲もなくなりがちな大部分の生徒に、従来の既成の価値観にとらわれない多様な選択肢を与え、社会体験を豊かにし、自主的で意欲的な子どもを多くしてゆこうというねらいでした。
(二)人づくり中心へ
民主党の政策の自民党と大きく違う点は、今までの「物づくり中心社会」から「人づくり中心社会」に転換してゆくという事です。
従って、これから予算面で教育や福祉などに積極的に投資し、製造業や建設・土木業などへの公共投資は大きく減らす方針です。
「人づくり中心社会」にしてゆく現れとして、今日に何倍も増額した子ども一人あたり月27000円(年間312000円)の教育手当がマニュフェスト(政権公約)のトップにあげられた。
この月27000円という額は、日本で高校生までの子ども一人にかかる教育費と言われる。
これは、子どもの教育を経済面でその家庭の責任とするのではなく、国・社会の責任とすることです。
何故「人づくり中心社会」に目指したのか、バーブル経済期間にこうな暴力の増長が顕著となったからだ。
子供への関心を寄らさずに行けない状況となった。
以下の図が顕示した大学校内暴力の発生頻度と件数です。
図4 暴力発生頻度
「人づくり中心社会」を作るためには、教員養成の改革案も大きな事です。
日本の小学校から高校の教師は、基本的に4年間の大学教育で養成されるが、これを修士課程卒業(6年間)を基礎資格にし、また最後の一年間は教育実習にあてるという考え方です。
また、大学の教師になりたいなら(改下)、せめて博士の資格を得なければならぬ、学校によって外国の留学経験も必要です。
彼等の教員が人本精神を持って子供達に愛心教育を行われる。
日本社会を根本的に転変しようとする。
上述した、日本の大学の授業時間が減少したが、教育方法や方式が豊富なったし、「人づくり中心社会」を作るための教員たちの培養などによって、、教育経費を増えなくてはならない。
(三)財政支持の増加
最近の発表でも、日本の近10年の公的財源からの大学教育支出の対国内総生産GDP比を出した、その中、過去最低の3.3%となったことが分った。
OECD加盟国の平均は4.9%(前年比0.1ポイント減)で、加盟30カ国のうちデータが比較可能な28カ国中、最高はアイスランドの7.2%、日本はトルコに次ぎワースト2位。
前回05年と03年は最下位、04年と02年はワースト2位と、低迷が続いています。
この20年余に他国が教育予算を4-5倍に伸ばしたのに、日本は2倍弱の伸びに止まっている。
そればかりでなく、日本の教育経費の数量が年々上昇した勢いが見える。
泉信三(2010)が『近代日本の教育』という本には2002-2010年の教育投資についての数字をだした、筆者はその増長をはっきりに見えるように、2002年以後の教育への投資財政伸び率表を作る。
年度
今年/昨年
同比増長
環比増長
2002
93.2%
0.0%
0.0%
2003
97.2%
4.0%
4.0%
2004
99.8%
5.6%
2.6%
2005
99.9%
6.7%
0.1%
2006
102.3%
9.1%
3.6%
2007
103.8%
10.6%
1.5%
2008
105.4%
12.2%
1.6%
2009
106.2%
13.0%
0.8%
2010
107%以上
13.8%以上
0.8%以上
表1 教育投資表
以上の教育支持政策には大きな財源が必要で、それは主に、今まで実質的に日本のありかたをリードしてきた官僚機構の無駄使いやこれまでの政権と結びついた権益を厳しくチェックし是正して、税金の無駄遣いを減らす事で生み出そうとしている。
又、教育など人への直接投資が景気刺激にもなるという考え方をしている様で、これらの財源確保や景気刺激がほんとうに上手く行けば、国民に支持され長く維持できると思う。
三経済回復後大学の発展
十年の不景気から回復した後、日本の経済がまた二位の経済大国の位置を占める。
これと同時に、日本の大学も雨後春筍のように発展した。
この発展は主に二つの方面に含む。
大学の数量の増加や専攻の膨大が主要表現である。
(一)大学数量の増長
まずは、21世紀に入ると日本の大学の数が恐ろしい速度に上昇した。
以下の十年の日本の大学の数量について図を作った。
図5 大学数量増長
以上の図を見れば、日本の伝統的な大学でも、短期大学でも増長の勢いが見える、特に短期大学の増長がはっきりで、2010年の短期大学の数量が02年より2倍以上に超えた。
何故というと、十年の不景気から回復して日本の会社にとって技術人材が必要だし、短期に人材を培養しなければならない。
特に、専門会社を目指して人材の培養が多くとなった。
だから、日本の大学も商業化になった勢いがだんだん顕てまた。
(二)大学専攻の膨大
日本の大学の発展がまた専門科目方面の膨大にも体現できる。
バーブル経済の崩壊以前には主に伝統の機械、建築、経済、物理、化学などの科目の分類が大まかであるが、バーブル経済後、機械が機電、機設に分ける。
2006年に、機電がまた模擬機電、数字機電などに分ける。
化学が有機化学、無機化学に分けて、有機化学が高分子化学、小分子化学に分けられるようとなった。
そればかりでなく、これらの専門科目がもっと詳しく分ける勢いが見える。
統計によると日本大学の専攻の増長が年々3%ぐらいの増長率で上回る。
そればかりでなく、日本の新生した専門科目も増える一方です。
例えば、調酒師、幼師の培養、雷電保護科学技術、しいては日本の漫画も大学の専門科目の一つとなった。
水木楊(2005)統計によると、00年から05年まで日本の新増した専攻が395個であった。
小谷敏(2010)の最新統計では新興した専攻も分化しようとし、05年より796個多くとなった。
だから、日本の大学がバーブル経済危機を渡って、発展勢いが史上最高である。
これと同時に、日本の進学率がまた昇って2011年の平均進学率が70%以上となった。
たとえ高校に進学しなくても、大学に入れるとなった。
おわりに
以上の分析によれば、日本の大学はバーブル経済から消極的な影響をうけることが分かる。
特に、論文の第2部分の検討した「二率」から見れば、以前の勢いに接続しなかった、横ばいや下降の勢いとなった。
でも、このバーブル経済から日本の大学の教育制度の不足点も顕示したようで、日本政府や教育機構が一連の政策をとって、例えば、教育中心は人づくりに変更した、財政は大幅に増加したで、教育時間を減らした、学生にもっと多く自由時間を与えることがわかる。
だから、このような不況状態から出して、史上のない発展趨勢が見れれる、特に大学の数量の増加や専攻の膨大などが顕著となた。
周知の通り、教育は国家の未来や運命を決定した。
教育問題は世界各国に重視される。
しかし、各国の教育制度は何かの問題点が存在したに違いない、だから他国の教育経験を取り出して、例えば、「授業時間を減らす」ことや「人づくり中心」、「財政支持の増加」などの方法を本國に適当に運用すれば思い出せない効果があるかもしれない。
また、現在に中国の大学生の就職率は非常に低い、だから「就職氷河期」「超氷河期」とも言える。
本論文の研究に通して、多少の指導の意見を提供できれば幸いであると思う。
でも、本論文が不足点も存在した、例えば、大学の進学難度を低くなった原因は高齢化、少子化とも関連があるに違いない。
本論文ではちっとも分析しなかった。
参考文献
[1]阿部謹也『教養とは何か』[M].講談社現代新書1997
[2]栗原彬『やさしさのゆくえ-現代青年論』[M].筑摩書房1981
[3]関峋一、返田健『大学生の心理』[M].有斐閣選書1983
[4]青木一ほか編『教育学事典』[M].労働旬報社1988
[5]泉信三『近代の日本教育』[M].大月書店2010
[6]丸山眞男『丸山眞男集』[M].岩波書店1995
[7]小此木啓吾『モラトリアム人間の時代』[M].中央公論社1978
[8]小此木啓吾『モラトリアム人間を考える』[M].中央公論社1982
[9]水木楊『東大法学部』[M].新潮新書2005
[10]竹内洋『教養主義の没落―変わりゆくエリート文化』[M].中公新書2004
[11]沢木耕太郎『バーボン・ストリート』[M].新潮社1984
[12]武内清『キャンパスライフの今』[M].玉川大学出版部2003
[13]小谷敏『若者たちの変貌―社会学的物語』[M].世界思想社2010
[14]西本鶏介.『バーブル経済とは』[M].株式会社ポプラ社,1995.
[15]柴田武.『現代大学の教育』[M].朝日新闻社,1976.
[16]史全生.『日本教育の欠点』[M].人文出版社,1984.
[17]王晓秋.『子供養育』[M].新华出版社,1998.
[18]朱红勤.『首都圏の暴力調査』[J].国际关系学院学报,1995.
[19]王晓秋.『日本の一百周年道徳综述』[J].历史研究,1998.
[20]今橋盛勝.『学校教育』[Z].阿衣得如研究所.1984.
[21]赵瑞芳.『暦年校内暴力件数調査』[J].思想战线,1994.
インタネット資源
1日本贸易振兴会:
www.jetro.go.jp
2文部省:
www.monbu.go.jp
3人材教育机构:
www.jcipo.org.jp
4統計年鑑:
www.iti.or.jp
謝 辞
二ヶ月あまりの努力を尽くして、やっと卒業論文を完成させることができました。
この過程を振り返ると、本当に感慨無量です。
卒業論文が大学四年間の勉強の集大成であるので、私は非常に重視していました。
ずっと前から卒業論文のことを考えていたが、三月の末まで、有意味かつ興味深いに適切なテーマが見つかりませんでした。
幸いなことに、先生から貴重な意見をいただき、最後に、日本の企業を研究対象にしました。
卒業論文を書くのをきっかけに、私は資料の収集方法を身につけました。
また、本論文の完成を通して、私は日本の企業についての資料をよく整理しました。
筆者の研究テーマと周りのよく見える間違いを報告しますが、同分野もしくは近隣分野の学者や専門家からいささかでもご関心やご指導がえられれば幸甚に思うのである。
最後に、再び手伝ってくださった諸先生方にお礼を申し上げます。